【書評】「昭和と日本人 失敗の本質」半藤 一利
2025/03/28公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(83点)
要約と感想レビュー
新聞は満州事変・国際連名脱退を正当化
昭和5(1930)年生まれで、昭和20(1945)年の日本敗戦を15歳で迎えた著者が、日本人の特質を考察します。著者の生まれた翌年昭和6(1931)年に満州事変が勃発。昭和8(1933)年の国際連盟脱退までの2年間、日本の新聞は、率先して陸軍に歩調を合わせて世論を作っていったという。
「東京朝日新聞(現朝日新聞)」「東京日日新聞(現毎日新聞)」ともに、陸軍の謀略ではじまった満州事変を正当化し、国際連盟脱退を肯定したのです。そもそも昭和7(1932)年には、全国132の新聞社が連名で「満州国の承認、妥協を断固拒否せよ」と共同宣言を出しているのです。
「文藝春秋」だけは、松岡洋右が「連盟の脱退は我輩の失敗である。帰国の上は郷里に引上げて謹慎するつもりだ」との告白を示した上で、「国際連盟脱退は日本の焦土外交であり失敗であった」と批判し、内田外相の責任が糾弾されなければならないのに、新聞はこれを問わないと批判していたという。
マスコミが一つの世論だけを信奉し、本来、さまざまな主張について議論しあうという機能を喪失するのが、日本の特徴であると著者は総括しています。冷静な議論ができないマスコミは、感情的な反発によって国際連盟を脱退した全権松岡洋右を英雄に仕立て上げてしまったというわけです。
「朝日」「日日(毎日新聞)」両紙ともに、連盟脱退を肯定・・陸軍の謀略によって発火した満州事変を「厳粛無比の事実」として、日本の新聞が正当化した・・マスコミは、既成事実を積み重ねながら・・声高に世論を引っぱった(p11)
政治と軍部の対中強硬派
こうした世論は、どうやって作られたのでしょうか。
昭和2(1927)年、瀋陽総領事であった吉田茂は、対中国強硬派の外交官として、外務次官の森恪(つとむ)と連携し、満州における日本の権益を擁護を求める意見書を提出しています。外務次官の森恪、満鉄社長の山本条太郎、総領事の吉田茂らの意思が、関東軍をして昭和3(1928)年の張作霖爆殺から満州事変と日本を戦争へ向かわせたというのです。当時、森恪外務次官は、陸軍の鈴木貞一と知り合い、関東軍の河本大作参謀や石原莞爾陸大教官と意見交換していたという。
昭和7(1932)年の五・一五事件では、犬養毅首相が撃ち殺されています。満州の張作霖の息子張学良の家から、犬養毅の領収書が発見され、犬養を襲撃した青年将校が「キサマも張学良からカネをもらっておろうが」と詰問し、これにたいして犬飼首相が「そのことなら話せばわかるから、こっちへ来い」といったが、問答無用と撃ち殺されたのです。
海軍においても、米内・山本・井上といった対英米協調派は傍流でした。海軍の主流は加藤寛治・末次信正ら対英米強硬派だったのです。昭和8(1933)年からの大角岑生海相の「大角人事」では対米協調派の山梨勝之進、堀悌吉、左近司政三らが予備役となっています。さらに軍司令部条例改正で、対英米強硬派が多い軍令系が、協調派的な軍政系の上位に位置づけられるのです。この流れで海軍の対英米強硬派は、昭和9(1934)年ワシントン・ロンドン軍縮条約を破棄するのです。
対英米強硬派が放った決定的な第三段が、ワシントン・ロンドン両軍縮条約の廃棄であった(p103)
陸軍北進と海軍南進の対立
その後の陸軍と海軍の対立も、日本ならではでしょう。
陸軍は昭和14(1939)年、ノモンハン事件でソ連機械化部隊に大敗しましたが、作戦立案を担当した服部卓四郎中佐と辻政信参謀は、責任を取ることなく、参謀本部に栄転します。その後の「武力を用いて南進」が、陸軍参謀本部で服部・辻を中心に、計画されたのです。
実際、昭和15(1940)年に成立した第二次近衛内閣は、陸軍の主導で「武力を用いて南進」という国策を決定。実は、組閣前の首相、陸相、海相の候補との会談で、日独伊同盟の強化と、日ソ不可侵条約締結を外交方針として決めてしまっていたという。
日本は明治以来、国策としてソ連を主敵として軍事力を強化してきました。著者はノモンハン事件の損害でショックを受けた服部・辻が、ソ連との戦いに「懲り懲りした」と推察しています。根拠なき自己過信、驕慢な無知、底知れない無責任が二人の特徴であるというのが著者の分析なのです。
昭和16(1941)年、独ソ開戦への対応として、外相松岡洋右・陸軍の対ソ開戦論と、海軍の南進論(南部仏印進駐)が対立します。7月の御前会議で、南北併進の二正面作戦という国策を日本は選択することになるのです。
関東軍において辻政信参謀とともに、ノモンハン事件をミス・リードした最大の責任者の一人、服部卓四郎中佐がその年の10月には参謀本部作戦課へ栄転した・・服部・辻コンビを中心に・・東南アジア侵攻一色にそめあげられていった(p91)
マスコミに煽られやすい国民性
著者は山本五十六の手紙を引用し、山本五十六が日露戦争の経験から、日本のに衆愚の世論を恐れていたことを指摘しています。例えば、日露戦争中、ロシア海軍のウラジオ艦隊が日本周辺で輸送船を撃沈するようになったとき、海上警備を担当していた第二艦隊の司令長官上村彦之丞中将の自宅が暴徒に襲われる事件が起きています。
また、日露戦争終結の講和条約では、朝日新聞が講和条約反対キャンペーンを行い、群衆が日比谷に焼討ちをかけた事件が発生しています。著者の推定では、日本人は無意識に群衆心理があり、マスコミの宣伝などに簡単に煽られ動揺しやすい国民性があるのではないかとしています。
昔も今も、マスコミは日本国民を煽っているように感じました。そんなマスコミにコントロールされないよう気をつけたいものです。半藤さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・過去のあらゆる外戦のときに明示されていた「国際公報の条項を守れ」の一行を、なぜに昭和の指導者は削りとって、てんとして恥じなかったのだろうか。それも忘却したわけではなく、意図的削除なのである(p38)
・ジュネーヴ捕虜条約を日本が批准していなかったことが、アジア民衆や捕虜に対する虐待虐殺につながらなかったか、どうか(p37)
・(昭和)20年2月に司令官がカーチス・ルメイ少将にかわると、一転して木と紙の家屋がひしめく住宅地への無差別焼夷弾攻撃にと変わっていった・・・昭和39(1964)年12月7日、時の日本政府(佐藤内閣)は、米空軍参謀総長として来日したルメイ大将に勲一等旭日大綬章を贈った(p142)
▼引用は、この本からです
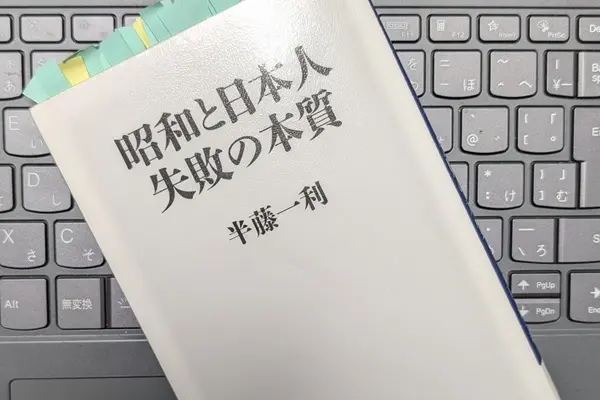
Amazon.co.jpで詳細を見る
半藤 一利、KADOKAWA
【私の評価】★★★★☆(83点)
目次
第1章 大日本帝国の戦争目的
第2章 「大艦巨砲」よ、さらば!
第3章 「最後の聖断」が訴えたもの
著者経歴
半藤 一利(はんどう かずとし)・・・1930年、東京都生まれ。作家。東京大学文学部卒業後、文藝春秋新社(現・文藝春秋)へ入社。「週刊文春」「文藝春秋」編集長、専務取締役を歴任。2015年菊池寛賞受賞。2021年1月逝去。
太平洋戦争関連書籍
「昭和と日本人 失敗の本質」半藤 一利
「なぜ、日本は戦争したのか?~17の質問から読み解く歴史物語」清田直紀
「復刻・日本とナチスドイツ」末次信正
「なぜ日本は同じ過ちを繰り返すのか 太平洋戦争に学ぶ失敗の本質」松本 利秋
「グリーンファーザーの青春譜―ファントムと呼ばれた士(サムライ)たち」杉山龍丸
「なぜ必敗の戦争を始めたのか 陸軍エリート将校反省会議」半藤一利
「日本海軍400時間の証言: 軍令部・参謀たちが語った敗戦」NHKスペシャル取材班
「失敗の本質―日本軍の組織論的研究」戸部 良一 寺本 義也 鎌田 伸一 杉之尾 孝生 村井 友秀 野中 郁次郎
「大本営参謀の情報戦記」堀 栄三
「日本はなぜ敗れるのか―敗因21ヵ条」山本七平
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!






































コメントする