【書評】シーパワーの地政学「海軍戦略家マハン」谷光 太郎
2025/07/09公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(88点)
要約と感想レビュー
アルフレッド・マハンとは
アルフレッド・T・マハンは、1840(天保11)年に生まれたアメリカの海軍大佐です。第一次大戦が勃発した1914年に亡くなっています。ちなみに山県有朋は天保9年生まれでマハンより2歳年上、東郷平八郎は弘化4年生まれでハマンより7歳年下です。
マハンは1890年の著作「海上権力史論」で、これまでの常識では陸上戦闘の勝敗で、国家間戦争の勝敗が決するとされていたのに対し、海上権力(シーパワー)によって勝敗が決まると主張したのです。
マハンは大英帝国の通商が、1800年から着実に増大していることを示し、大英帝国の繁栄は制海権の確保によって決まると主張しました。
したがって、将来の海戦は小型艦艇ではなく、戦艦によって勝敗が決まると予想したのです。この主張は、海軍増強派と大英帝国を勇気づけ、結果して各国は海軍を増強したのです。その予想は、1905年の日露戦争の日本海海戦によって証明されることになりました。
マハンによれば、米海軍の伝統的考えは沿岸防衛と商船護衛だったが、マハンによれば、米海軍の主目的は敵海軍であり、制海権確保のためには何より戦艦が必要で、従来の防衛的な巡洋艦中心は改めるべきだ、とした(p54)
マハンの海外覇権主義
マハンの基本的な主張は、アメリカの孤立主義から海外覇権主義への政策変更でした。つまり、大英帝国の覇権はインドを英国の収入源にしたことにあり、それはインドへの海上路の制海権を英海軍が確保したから。
したがって、アメリカが中国市場で主導的立場に立つためには、大英帝国と同じように海上権力(シーパワー)を増強すべきというわけです。
シーパワーを確保するためには、アメリカ海軍を巨大化しなければならず、ハワイ領有による給炭基地の確保、戦艦を大西洋から太平洋に移動できるようパナマ運河をアメリカのコントロール下に置くことを主張しました。
もちろん、当時の民主党クリーブランド政権の考えと異なる論文を次々と発表するアメリカの現役海軍大佐のマハンは、政権にとって目ざわりな存在だったという。
ちなみに、アメリカがハワイを併合したのは、1898年、ハワイ併合に反対するクリーブランド大統領の次のマッキンリー大統領です。パナマ運河は1904年着工し、1914年に完成しました。
米国のコントロール下にあるハワイ群島に何万人という黄色人種移民がなだれ込んでいる・・・野蛮な黄色人種の流入の流れをせき止めるには、文明海洋国米国によるハワイ群島の獲得が必要だ(p122)
マハンの日本人移民排斥論
マハンはアメリカの海外覇権を主張しながら、同時に英米アングロサクソン民族の優秀性を強調し、反対に米国に流入する黄色人種の日本人移民の危険性を指摘し続けました。
著者は、マハンによる日本人移民阻止の主張は、全米規模の日本人移民排斥運動の一因となり、さらに日本人を憤慨させ、太平洋戦争の大きな原因の一つになったとしています。
当時、ハワイやカリフォルニアで農地にならないと思われていた荒地を日本人移民が豊かな土地に変え、カルフォルニア全人口の1%の日系人が農産物の50%を生産するまでになっていました。
その結果、経済的地位を脅かされ、嫉妬に駆られた白人が排日運動を劇化させていったという。
1906年にはサンフランシスコ市学務局が、日系人の隔離教育を決定しました。日本人学童教育施設は、劣悪な場所にあり、日本人は反発したのです。
当時、日本は日英同盟を締結しており、排日運動は英国は日本側に立たざるをえず、マハンは危機感を持っていました。対日戦争の準備のためにも、アメリカは日英同盟を失効させることに注力するのです。アメリカにとって幸いなことに、日英同盟は1923年失効します。
その結果、1922年の連邦最高裁判決で、日本人は帰化権は持てないことが決まり、すでに帰化していた日系人の権利も剥奪されました。1924年の絶対的排日移民法によって、マハンの主張する黄色人種日本人の米国への流入、土地所有、米国への帰化の禁止が完成したのです。
1941年の日米開戦では、マハンの友人であったフランクリン・ルーズベルト大統領は、日本人移民を強制収容所に隔離しました。同じ敵国ドイツ、イタリアの白人系はそのままとし、日系人のみ砂漠に急造した強制キャンプに送り込み、財産を没収したのです。
黄色人種は進化の遅れた劣等民族だという考えが米国白人間では、牢固として存在していた・・フランクリン・ルーズベルト大統領・・「日本人の頭蓋骨の発達が白人に比べ2000年も遅れている」との発言(p157)
覇権国家アメリカの源流
マハンは海軍大佐でありながら、アメリカの帝国主義化を主張し、海軍軍拡論者たちの論理的な支柱であったことがわかりました。
マハンは海軍次官であった友人ルーズベルトに「ハワイがごたごたしていると、日本艦が間違いなくハワイに向かうだろう・・・米国が無関心なら、これら重要な島々を日本が支配するようになる。まず、これらの島々を米国が先に取る・・・太平洋岸には戦艦一隻と、沿岸防衛に特化したモニター艦が一隻のみだ。この海域に日本が戦艦二隻を派遣してきたら、どうしようもない」と軍事力増強の必要性を説明しています。
仮に海軍にマハンやフランクリン・ルーズベルトがいなければ、太平洋を日本が支配し続けていたかも知れないと思うと、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」という憲法前文がジョークのように思えてきました。
また歴史は繰り返すのか、もう少し勉強していきたいと思います。谷光 さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・ルーズベルトの外交政策は「太い棍棒を持って、静かに話す」だった・・・米国人の生命財産保護のために迅速に現地に派遣できる武力集団が不可欠である(p165)
・利害が対立している二国間での平和維持は武力によってのみ保持できる(マハン)(p27)
・マハンも実戦に参加したことは皆無で、船乗りに向いていない、ともいわれた。操艦は下手、海への恐怖心も強く、できるだけ海上勤務を避けようとした(p17)
▼引用は、この本からです
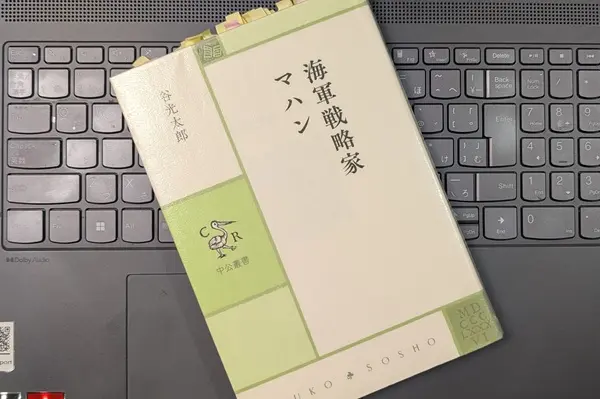
Amazon.co.jpで詳細を見る
谷光 太郎 (著)、中央公論新社
【私の評価】★★★★☆(88点)
目次
第一章 おいたち
第二章 日本来航
第三章 中南米艦長時代
第四章 海軍大学校と海上権力史論
第五章 ドイツ海軍とマハン
第六章 シカゴ号艦長として渡英
第七章 退役と文筆活動
第八章 ハワイ併合、米西戦争、比島領有、ハーグ平和会議
第九章 マハン、ルーズベルト、ロッジのトリオ
第10章 米国の海外政策
第11章 日本とマハン
第12章 近代海軍問題
第13章 晩年のマハン
著者経歴
谷光 太郎(たにみつ たろう)・・・1941年、香川県生まれ。1963年、東北大学法学部卒業。三菱電機入社。1994年、山口大学経済学部教授。2004年、大阪成蹊大学現代経営情報学部教授。2011年、同校退職
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!

































コメントする