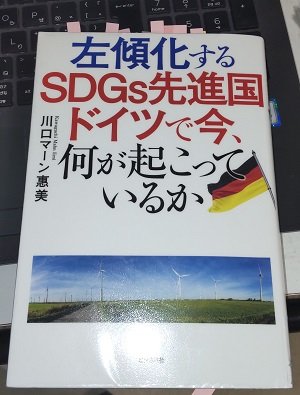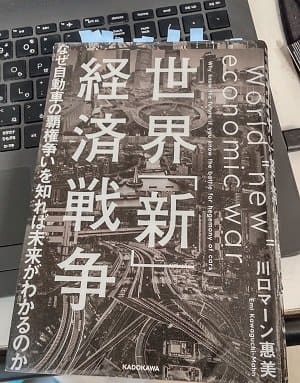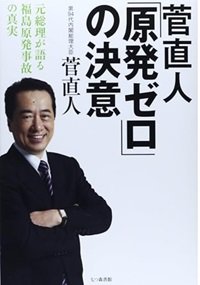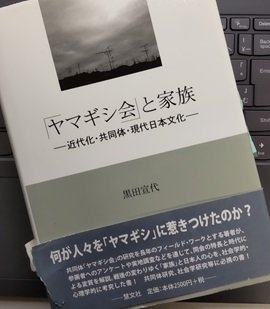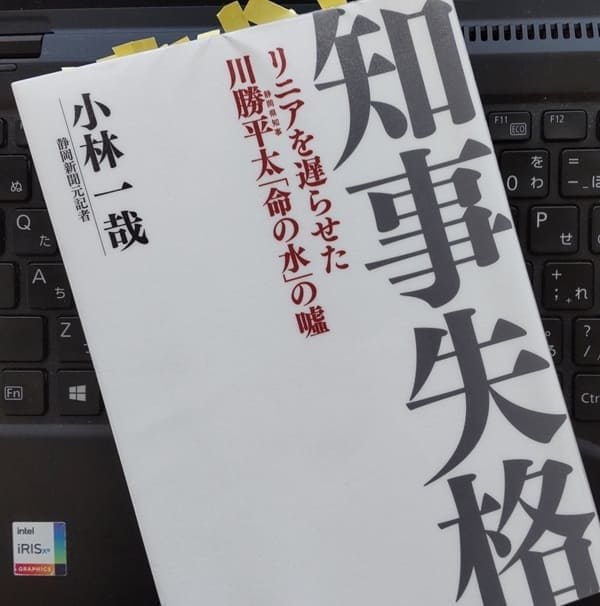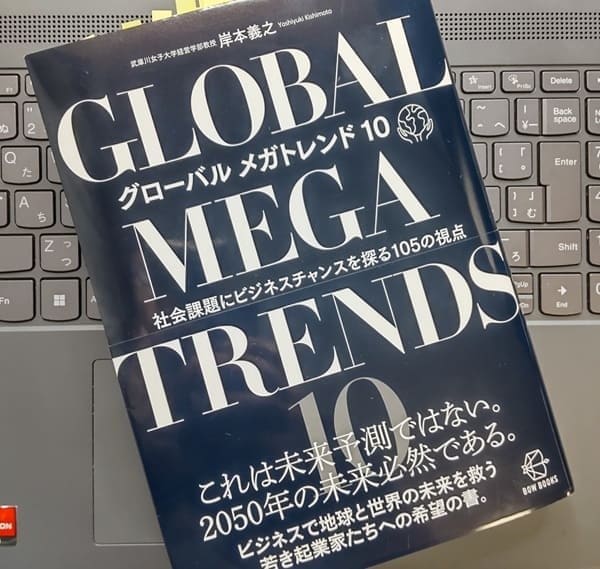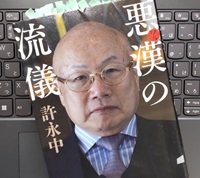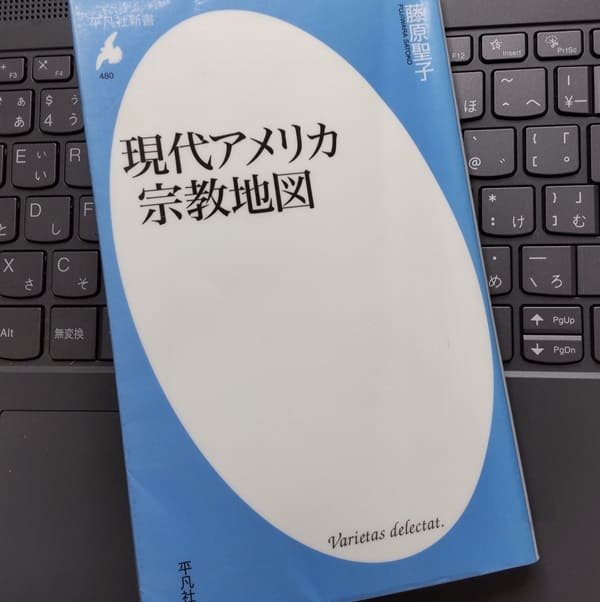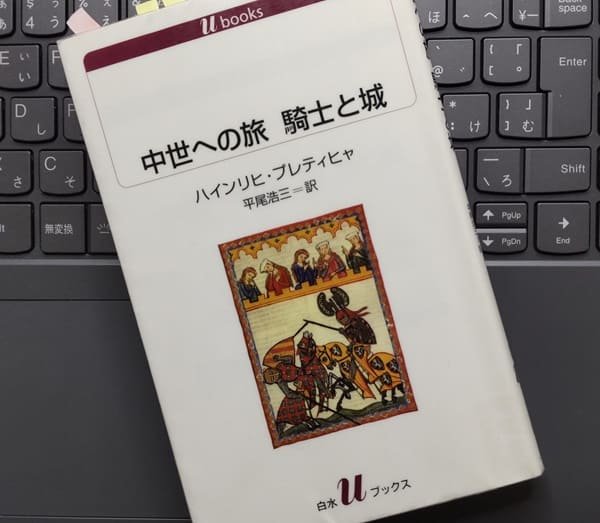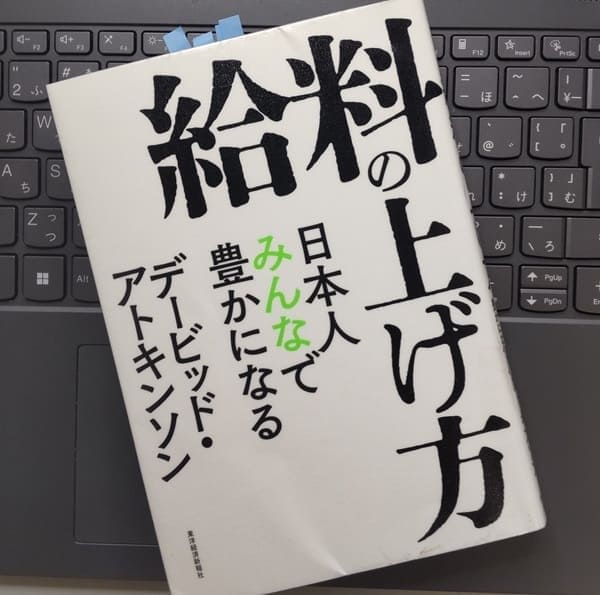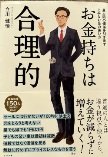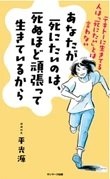「復興の日本人論 誰も書かなかった福島」川口 マーン惠美
2018/06/06公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(78点)
要約と感想レビュー
ドイツに住んで40年、思考がドイツ人になっている川口さんが見た福島の復興の状況です。地元のボランティア活動を続ける東京電力社員と、それを受け入れつつ許せない地元の人々がいます。ドイツ人思考では、会社の責任を現場の社員が引き受け、謝罪し、ボランティアを行う状況に違和感を持つようです。
もし東京電力がドイツ電力であったなら、以下のような主張をして、裁判となり、判決が出るまで謝罪・賠償はしないのでしょう。"原子力発電所は国の指針に基づいて適切に建設・運営されており、当社に責任はない。さらに、原子力損害賠償法では「異常に巨大な天災地変」に責任免除の条項があり、今回の地震・津波はそれに該当するので当社は免責される"
つまりドイツ人なら、法治国家である以上、賠償に関して感情などいっさい入らず、是か否かの判断は、法律のみが指針であり裁判で決着するであろうということです。
・ここでは、会社の責任と一社員の役割が、限りなく混同しているように思えた。この社員たちは経営者ではない。何か罪を犯したわけでもない。なのになぜ、被災者の「許すことができない」という感情を、正面から一手に引き受けなければならないのか(p60)
さらに、福島第一原発事故の対応では、合理的な判断がされていないという事例が多すぎます。汚染水を処理した後のトリチウム(三重水素)を放流できない。除染の基準である年間1ミリシーベルト(1時間当たり0.25マイクロシーベルト)は、ラドン温泉が1マイクロシーベルト以上であることを考えるとあまりにも低すぎるのです。
そもそも、通常の空間線量が0.1マイクロシーベルトで、規準の半分になっている。海外の原子力事故では運転しながら安全対策を行っているのに、日本はすべての原子力を停止してしまった。長期停止で、逆に原子力設備の劣化の可能性が高まり信頼性を低下させているのではないか。
なぜ廃炉を急ぐのか。「廃炉」という言葉が、解体撤去と同意語になっていることが間違いだと著者は断言するのです。なぜなら廃炉を急げば、いきおい人海戦術に頼らざるを得ず、その副産物として、膨大な人件費と無用な作業員被曝を伴うからです。しかも、取り出した放射性物質の処分場や仮置き場所の目処も立っていないのです。
さらに原子力がダメなら自然エネルギーとなって、なぜヨーロッパでうまくいっていない再生エネルギー買取制度を採用し、高値で不安定な電気を買うことにしたのか。故意か天然かわかりませんが、当時の政権の判断があまりに酷かった、ということなのでしょう。
・「やわらぎの湯」の飲泉場では、湯治客が「302.5マイクロキューリーで、世界でもトップクラス」の水を飲んでいる・・・ベクレルに換算すると1120ベクレルとなる・・福島では、何年もかけて、すごい手間とお金をかけて放射能の除染をしていたのに、同じ福島のそれも目と鼻の先の三春温泉は高い放射線量を堂々と誇り、しかも放射能入りの水を皆が飲んでいるのである(p86)
民主党政権の残した原子力規制委員会は、原子力発電所を再稼働させないことを是とし、この10年間、確実に日本の経済に毎年3兆円以上の負担をかけています。著者の意見は、震災の被害を受けなかった原子力発電所の安全強化は、稼働しながらでもできたのではないかということなのです。
ドイツ人の眼から見ると、不思議なことが多いようです。良く言えば、理想論・精神論で頑張る日本人。事実とルールに基づくドイツ人。悪く言えば、事実に基づかず、情緒的な日本人。融通のきかないドイツ人。どちらが良いのか分からなくなってきました。川口さん、良い本をありがとうございました。
この本で私が共感した名言
・東電の社員は現場に行かないというのは、昔から有名でしたね。運転も保安もメンテナンスも、全部下請けに発注しておしまい。報告を受けるだけで、自分では見にいかない(p73)
・チェルノブイリでは、400ヘクタールで草が枯れた。福島では枯れなかった。今、汚染土壌を詰めたはずのフレコンパックからは、草が生えている(p80)
・再エネの買取値段は、何を勘違いしたか、現在、ドイツより高値だ。これを決めたのも当時の民主党政権だ・・再エネ法の数度の改訂により、2014年、ドイツはすでにプロデュース&フォーゲットの買取制度を事実上停止している・・・入札制度が取り入れられはじめた。もちろん、まだ補助金は付いているが、従来のような保障付き買取制度とはすでに違う(p157)
▼引用は下記の書籍からです。
グッドブックス (2017-11-22)
売り上げランキング: 48,711
【私の評価】★★★☆☆(78点)
目次
序章 ドイツから3.11後の福島へ
1章 巨額の賠償金が生んだ「分断」
2章 東電は謝罪していないのか
3章 風評を作り続けるマスコミ
4章 報道よりもずっと先を行く福島
5章 ドイツの失敗を繰り返すな
6章 日本が原子力を選択した日
7章 復興への希望と力
著者経歴
川口マーン惠美(かわぐち まーん えみ)・・・1956年大阪生まれ。日本大学芸術学部卒業。1985年、ドイツ・シュツットガルト国立音楽大学大学院ピアノ科卒業。シュツットガルト在住。
放射線・放射能関連書籍
「小説1ミリシーベルト」松崎忠男
「世界一わかりやすい放射能の本当の話 完全対策編」宝島社
「復興の日本人論 誰も書かなかった福島」川口 マーン惠美
「放射線医が語る福島で起こっている本当のこと」中川 恵一
「はじめての福島学」開沼博
「ヤクザと原発 福島第一潜入記」鈴木 智彦
この記事が参考になったと思った方は、
クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓ ![]()
![]()