【書評】「成毛眞の超訳・君主論」成毛眞
2014/11/25公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(88点)
要約と感想レビュー
元マイクロソフト社長が教える君主(社長)論の使い方です。成毛さんは、社長時代、君主論に書いてあることを、そのままやったという。具体的には、社長になったら、年上の副社長をクビにした。まず、君主は怖れられなくてはならないのです。
つまり『君主論』に書いてあることは、「冷酷であっても残虐であっても、組織を守り抜くしたたかさを持つリーダーこそ、世の中に貢献できる」という現実なのです。リーダーがどんな振る舞いをするのか、組織の内部はもちろん、外部からも常に注目されているのです。
・私の考えでは、4割は猫かぶりの偽善者で、6割がまともな人という印象だ。それでも、猫かぶりの4割の偽善者に寝首をかかれないためには、鬼キャラになることが必要なのである(p66)
そして、前任者の方針を180度変更する。前任者が、日本独自仕様に固執しているなら、自分は、世界統一仕様にする。日本では前任者を会長にして、方針追従が多いようですが、成毛さんは外資系らしく自分のスタイルを通した。最終的に決定する権限を持っているのは、君主なのです。
ただ、改革が成功するのは、リーダーの力が発揮されたときではなく、周りが改革に乗り気になったときです。だから、諦めない人が最後には勝つのです。そこまでの熱意を持って挑まないと、悪しき習慣など打破できません。成功に必要なのは熱意と冷静な判断力なのです。
・決断力のない君主は中立を選び、滅んでいく(p102)
日本では成毛さんのように君主論をそのまま実行は難しいのでは、と思いました。ただ、人から畏れられる必要があるのは間違いないと思います。だから、君主らしい性格でなくても、君主らしい気質を兼ね備えているかのように振る舞うのが大切です。つまり「演技でOK,偉そうなふりをしていればいい」ということです。
君主でなくても、あなたが上司であるなえば、「オレがすべての責任をもつから、自由にやってみろ」と部下にすべてを任せて、見守っているふりをすることです。そして、部下が失敗したときは、自分が上司から叱られて、責任をとっているふりをすればいい。部下からは尊敬され、上司からも責任感が強いと評価が高くなるというわけです。
成毛さん、良い本をありがとうございました。
この本で私が共感した名言
・いずれにしても、誰かを飲みに連れていくと、誘わなかった部下からは、多少なりとも恨みを買うことになる・・・一部の人だけに便宜を図ったり、えこひいきしたりすれば、他方からは必ず恨みを買うことになる(p59)
・フィロポイメンが平時でも非常時に備えてイメージトレーニングをしていたように、あらゆる場面を想定しておかないとピンチを切り抜けられない。・・・最悪なのは、何も準備しておかないことである(p154)
・ゴマするになるにしても、志の高いゴマすりになるべきである。組織の歯車であっても、心までは簡単に従ってはいけない。役を演じる役者になるのだ(p190)
▼引用は、この本からです。
メディアファクトリー
売り上げランキング: 174,934
【私の評価】★★★★☆(88点)
目次
はじめに 今こそ強いリーダーが求められる時代
第1章 マキアヴェッリはビジネスマンの教師である
第2章 『君主論』はこれだけ知れば大丈夫
第3章 『君主論』を体得すれば人生が変わる
第4章 これから頑張る人が『君主論』を読むべき理由
付録 もっと知りたい人のためのブックガイド
著者経歴
成毛 眞(なるけ まこと)・・・1955年北海道生まれ。元日本マイクロソフト代表取締役社長。1986年マイクロソフト株式会社入社。1991年、同社代表取締役社長に就任。2000年に退社後、投資コンサルティング会社「インスパイア」を設立。現在は、書評サイトHONZ代表も務める。
この記事が参考になったと思った方は、
クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
人気ブログランキングへ
読んでいただきありがとうございました!







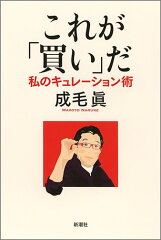


































コメントする