【書評】「賢者の書」喜多川 泰
2007/03/28公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★★(93点)
要約と感想レビュー
先週の喜多川 泰さんの「君と会えたから・・・」に感動して、喜多川 泰さんのデビュー作も購入してみました。また、驚きでした。素晴らしい内容とそれを伝えるための物語になっているのです。
人生に落胆した主人公が、偶然であった少年から「賢者の書」を読ませてもらうというストーリーです。単なる成功法則本のかき集めではなく、著者のなかで再構築した『賢者の書』は独創性があるのです。
まず、( 成功するまで行動し続ける )ということについては、人生をモザイク画と対比させています。つまり、人生とはモザイク画を描くようなものであり、行動したことに対して、一つのピースがもらえる。そして、そのピースを一個一個、自分の描いた夢、つまり大きな絵の一部に貼り付けていくのです。
あなたは、自分の夢を描くために、たくさんの行動を起こさなくてはならないのです。そしていつ、その絵が完成するかはわかりません。ただ、その絵をイメージして行動するだけなのです。そして、あなたが努力を続ければ、いずれあなたオリジナルの絵が見えてくることでしょう。
・大きな絵、つまり夢を思い描く。そして行動を起こす。そうすると、ひとつだけその絵を完成させるのに必要なピースが手渡せる。(p50)
また、世の中には自分の幸せだけを願い、不満に満ち溢れた生活を送っている人がたくさんいます。もし、あなたが、自分の幸せを願うだけでなく、他人の幸せを祈ることができるならば、世の中にはたくさんの不幸な人たちがいるわけですから、あなたにとって世の中とはチャンスに満ち溢れた場所となるのです。
・この世は、自分の幸せばかりを願うものにとっては・・・試練の場かもしれないが、他人の幸せばかりを願うものにとっては・・・チャンスに満ちた輝ける場所なのだよ。(p152)
小説形式で読みやすく、内容も著者の独自性が光るだけでなくレベルの高い一冊でした。文句なく★5つとします。
この本で私が共感した名言
・人生において欲しいものを手に入れるためには、手に入れたいと思うものを与える側にならなければならない。(p202)
・大切なのは、必要なピースを集めるためにできるだけ多くの行動を起こすこと、そして、行動の結果返ってきたものをよく見て、どうやってこれを使うかを考えることだ。(p59)
・人生は、言葉によってつくられている。その人に起こるすべての出来事は、その人が発したり、心の中で思い描いたりする言葉に起因する当然の結果にすぎない。(p176)
▼引用は、この本からです。
【私の評価】★★★★★(93点)
目次
衝動
出会い
序章~旅の始まり
第一の賢者
第二の賢者
第三の賢者
第四の賢者
第五の賢者
第六の賢者
第七の賢者
第八の賢者
発見
最後の賢者
新しい旅立ち
著者経歴
喜多川 泰(きたがわ やすし)・・・1970年生まれ。東京学芸大学卒業後、1998年横浜市に学習塾「聡明舎」を設立。高校生を中心に英語を教える一方、授業に自己啓発を取り入れるべく研究を続け、執筆活動を開始。
読んでいただきありがとうございました!
この記事が参考になった方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
人気ブログランキングに投票する

![]()
| メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」 42,000名が読んでいる定番書評メルマガです。購読して読書好きになった人が続出中。 >>バックナンバー |
| 配信には『まぐまぐ』を使用しております。 |
お気に入りに追加|本のソムリエ公式サイト|発行者の日記














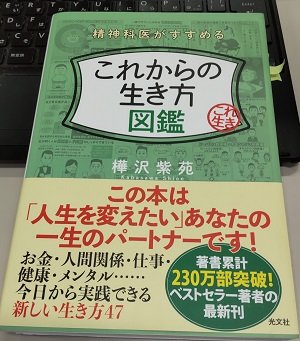



























喜田川さんの本は、賢者の書も読んで感動しました。
とても読みやすくてさらに教えがとても納得でき、
すっと心に入ってきます。
何になりたいかではなく、どうなりたいか。
職業は目的ではなく、手段。とても納得。
目からウロコです。
夏の甲子園が始まる前に、花巻東高校の菊池君の特番を見た際、彼の机にはこのメルマガでも紹介されていた「賢者の書」(青い表紙?)が置かれていました。
インタビュアーは特に気も留めなかったようですが、その時は優勝の予感がしました。
結果的には怪我で優勝を逃しましたが、春の大会が終わってからのチームの立て直しや朝正門での生徒への声かけなど、彼のグラウンドを離れたところでもすばらしい姿勢に感心させられます。
ソムリエさんのメルマガの素晴らしさを再認識するとともに、彼がどんな進路を選んでも問題ないと感じました。
心を動かされる本や人との出会いは素晴らしいことだと思います。
最近感動した本は新装版になり出版された「賢者の書」です。
このメルマガで紹介されたのを拝見し、ずっと読みたい読みたいと思って探していたところ新装版で再出版されているのを比田井和孝先生の講演会で見つけました。
比田井先生はお子さんへの遺書代わりとして購入されているそうですが、本を読んでその理由がわかりました。
自分も子供はまだ小さいですが子どものためにもう一冊購入しようと思いました。
ファンタジー風の自己啓発書です。
自己啓発書は好きで何冊も読んで来ましたが
かなり好きな本の一冊になりました。
その中に二つの民族の話が出てきます。
与える民族と奪う民族なのですが
不思議なことに二つの民族はとても仲が良い。
ところがどんどん富が増えていく民族は
与える民族という話が出てきます。
なるほどと感心してしまいました。
読了後の何ともいえない爽快感が
もう一度読みたい気分になりました。