【書評】なぜ二宮尊徳は本を読んでいるのか「二宮金次郎に学ぶ生き方」中桐 万里子
2025/08/04公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★★(93点)
要約と感想レビュー
なぜ二宮尊徳は本を読んでいるのか
二宮金次郎(尊徳)の7代目の子孫である著者が、金次郎の素顔を語ります。
まず、私たちが二宮金次郎を知っているのは、1920年頃から金次郎の像が日本全国の学校に勤勉・倹約の象徴として建てられたからです。著者は、多くの成功者の中からなぜ金次郎だけ像が建てられたのかといえば、彼が農民出身であり、政治には口を出さず、農村と藩財政の再建に成功したからだと推察しています。
では、なぜ金次郎は薪を背負って、本を読んでいるのでしょうか。
実は、金次郎の家は裕福な農家でしたが、父親が学問好きで、お人好しのため無理をして村人を助けることで家は疲弊し、天災も重なり、過労で父も母も亡くなってしまうのです。
親戚の家に預けられた金次郎が、働きながら本を読んでいたのは、父が大切にしていた本を読むことで、両親が自分に教え示そうとした道を見出そうとしていたのだと著者は解説するのです。
彼(尊徳)が読んでいるのは、父親の本・・父が亡きあと、金次郎は父が大事に読んでいたその本のなかに、両親が自分に教え示そうとした道を見出そうとします(p25)
きちがい金次郎
そんな金次郎を、村人たちは「キ印(きちがい)の金次郎」などと呼び、「問題児」「変わり者」と見ていました。
金次郎を預かった万兵衛伯父さんも、金次郎の両親が亡くなったのは、農民でありながら本を読み、お金に困った村人を助けるなどという身分不相応なことにまで手を出してしまった弟に原因があると考えていました。
本など読まずに、農民は農民らしく地道に農業だけをしていれば、弟夫婦は亡くなることはなかったのに!と思っていたら、その息子も本を読んでいるのです。だから金次郎が夜に本を読んでいるのを見て、「灯りに使う油がもったいないから本など読むな」と叱責するのは金次郎の将来を考えて、当然のことだったのです。
しかし金次郎は、とてつもない頑固者でした。たとえ周囲から「きちがい」と言われても、伯父さんから農民らしくしろと言われても、本を読むことを辞めなかったのです。なぜ父親の人助けが失敗したのか、どうすれば農業で成功するのか考え、学び、実践しながら、農家として金次郎は成功していくのです。
金次郎のあの像は「いい子に勉強しなさい」と伝えいているのではない・・・「たとえ「変な子」「変わった子」と言われたって、それでも自分にとって大事なことを、大事にして歩いていきましょう」というメッセージ(p27)
金次郎の失敗と学び
農家として余裕の出てきた金次郎の才能と評判を聞いた当時の藩主が、金次郎に藩の財政再建と農村再建を依頼をします。金次郎は断りますが、自分のやり方でやることを約束してもらい了解するのです。この本では書いていませんが、そのやり方とは、藩から農民に支援金を出さないこと。農民への年貢を10年間、現状支払えるレベルに下げることです。
(支援すれば弱くなる。不況には減税で活性化させる。金次郎は経済の基本を知っていたのです)
農村再建といえば、当時は藩から農民に支援金を出して、農民のやる気を出させるという方法が主流でした。一方、金次郎のやり方は農民自らが金を積み立て、開墾し、副業するという手法でした。支援金をもらえないので、やる気のない農民からの反発は大きかったのです。
また、藩の財政再建として、支出を大きく削減して武士が生活に苦労している一方、農民は安い年貢で余裕ができて、幸せそうなのが、下級武士には許せなかったらしいのです。
(日本のバブルを財務省が叩き潰したことを思い起こさせます)
金次郎が活動をはじめてから8年経ったとき、やる気のない農民と不満を持った武士の妨害活動がひどくなり、金次郎は辞表を出し、行方不明となります。金次郎はお寺で断食修行をしていたというのですから、その悩みは大きかったのでしょう。
金次郎がこの挫折で気付いたのは、「半円の見」です。自分は「半円」でしかなく、円を回すのは村人一人ひとりであるということを悟ったというのです。自分に相手を責める気持ちがあったから、その気持ちがはね返ってきたにすぎないとも気付いたのです。
それからは、村人一人ひとりの意見を取り入れる形で、反対者が出にくい仕組みを作っていったという。
半円の見・・・決定について、村人一人ひとりに票を与え、投票によって考えていくよう制度をととのえた(p103)
無利子の資金貸付
金次郎の父は、困っている人にお金を貸して、返してもらえずに没落しました。金次郎は、絶対に全額返すようにグループで連帯保証したうえで、無利子の資金貸付業を立ち上げます。
「五常講」とか「報徳金」と呼ばれますが、現在の金額にして二千万円程度で立ち上げ、金次郎が亡くなる頃には1億5千万円になっていたという。基本的に無利子ですが、返済後には、「感謝をカタチであらわしなさい」と、追加で払いたい人は追加でお金を払ったのです。これが「報徳」です。
無利子で貸してもらえたのだから、少しでもその徳に報いるべくお金を出そうということです。受けた徳(恩)を返すことで、それがまた他の人の未来を生み出すことに使われていくという好循環が生まれるのです。
「幸せになる=報われるためにがんばろう」ではなく、「幸せだからがんばろう=報いよう」、それが金次郎の報徳なのです(p148)
感謝して徳に報いよう
金次郎は、各地域の復興スタート時には、かならずその村の神社や仏閣を清掃して、きれいにしたと言われています。これは金次郎の報徳の思想であり、こんなに素晴らしい地域に生まれたのだから、こんな可能性のある土地なのだから、感謝してその徳に報いようということです。
金次郎は「わが道は至誠と実行のみ」と自らの人生を表現していました。そして、彼の遺言は「私の名をのこさず、おこないをのこせ」というものです。つまり、本を読むことも、理論も大事だけれども、一番大切なのは、行動すること、一歩を踏み出すことということなのです。
経緯がかなり省略されていますので、「二宮翁夜話」などと合わせて読むことで、より金次郎の素顔が見えてくることでしょう。中桐さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・親孝行ちうこともまた、親から受けたものを、子に返していくことができたとき、はじめて成立する・・金次郎流の「恩返し」は、単に元に戻していく意味の「返し」ではなく、そうやって未来を生み出す創造的な意味やはたらきを持っています(p207)
・金次郎を経済的にも大きく支援してくださった剣持家・・・剣持の家には、金次郎さんの借財の念書が残っていて、大事にしているんですよ・・・借金を返さずに死んだ(p39)
・お金もエネルギーも、あくまでも公のため、村のため、未来のために使われているのだと・・そうした個人的な思い込みのつよさから、きっと彼は「貸してくださったスポンサーに返さなければならない」という、きわめて基本的で現実的なこの世の理屈をすっかり忘れてしまっていたのではないか(p41)
・金次郎という人物は、大変なメモ魔だった・・・日記、家計簿などをこまめにつけ、手紙にかんしても自分から出したものまでかならず複写を手元に置くなど、とにかくよくメモをのこした(p75)
▼引用は、この本からです
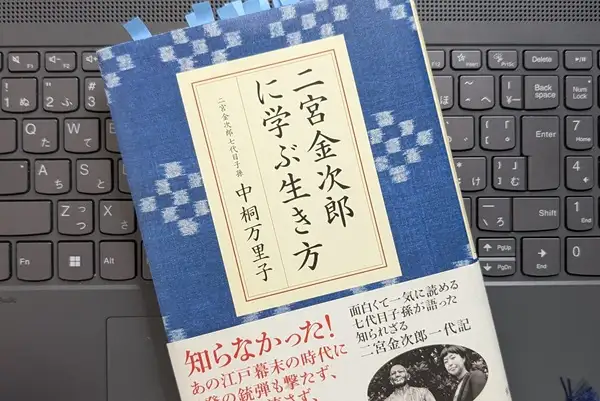
Amazon.co.jpで詳細を見る
中桐 万里子(著)、致知出版社
【私の評価】★★★★★(93点)
目次
第1章 多くの人に愛され、育てられた金次郎
第2章 すべてはまず「知る」ことからはじまる
第3章 金次郎がぶつかった人間関係という壁
第4章 すべてのものにはプロセス=徳がある
第5章 報徳とはtake and give
第6章 「報徳」こそ目の前の現実を豊かにするための秘訣
第7章 どんなときも一歩踏み出すことを忘れなかった金次郎
著者経歴
中桐万里子(なかぎり まりこ)・・・1974年東京都生まれ。神奈川県で育つ。二宮金次郎(尊徳)の7代目子孫。慶應義塾大学環境情報学部卒業。その後、京都大学大学院教育学研究科に進学し、臨床教育学を学ぶ。2005年同大学院にて教育学の博士号を取得し、課程修了。2007年より「親子をつなぐ学びのスペース『リレイト』」を主宰。国際二宮尊徳思想学会常務理事、聖和大学専任講師を経て関西学院大学講師
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!












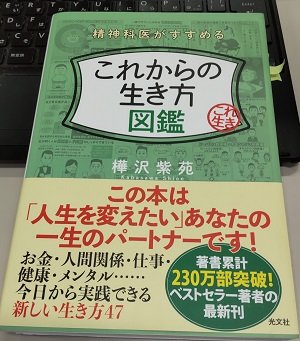



























コメントする