【書評】金次郎の素顔「二宮尊徳」大藤 修
2025/09/02公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★★(90点)
要約と感想レビュー
積小為大と貸付運用
これまで読んできた「二宮尊徳」本のなかで、もっとも素顔の二宮尊徳に出会える一冊だったのでご紹介します。
二宮尊徳の荒廃した農村の復興手法は、継続的な減税を藩に認めさせ、借金があれば低利の資金を提供して借り換えさせることでした。
当時の年貢は村単位に課税され、村の連帯責任で納税していました。したがって、納税できない百姓が出れば,他の百姓たちが肩代わりるることになり、税負担がますます重くなり、支払えない百姓が増えるといった悪循環におちいっていたのです。
また、生活の苦しい農民が借金をすると、年利は15~20%と高く、利子を払っても借金は減らない状況だったのです。
このように農村が疲弊し人口減少が進むのは、年貢が生産量に比べて高く、借金しても年利10%以上の高利であることが真因であると尊徳は見抜いていたのです。
尊徳が年貢の固定化と、借金借り換えを含めた復興手法を確立できたのは、尊徳自身が、貸金で没落した二宮家を復興できたことが大きな影響を与えていると思いました。
尊徳は金も土地も持っていないときに、捨苗を拾って植えつけ、収穫された米一俵の売却金を基金としました。尊徳は自分の所有地は小作に出して、小作料の米を販売して基金に繰り入れ,自分も藩の職員となって給料を稼ぎました。そして、その金を貸し付けて、その利息を積み立てることで,洪水被害で失った田畑を買い戻し,二宮家を復興したのです。
奉公稼ぎに出た文化8年以降は,小作人十数名,小作面積2町歩弱,小作料30~40俵余にのぼる経営に成長している・・・帳簿の記録からも米相場に常に注意を払っていた(p47)
貧民の救済と村の復興
尊徳は小田原藩の仕事を手伝う中で、家老の財政再建を計画・実施し、成果が出てしまいました。その能力に目をつけた小田原藩主の大久保忠真が、分家である宇津家の下野国芳賀郡桜町(現在の栃木県)の財政立て直しを尊徳に命じたのです。
尊徳は藩主の命を請けるのですが、苦労して再建した家から離れ、何も知らない栃木県に出向くのは複雑な心境だったと思われます。しかし、尊徳は藩主の命は、貧民の救済と村の復興という公的に重要な使命であり、自分の人生を捧げることを決断しています。さらに、それまで苦労して家を再建してきたことを,幸せに暮らしたいという「私欲」であったと反省さえしているのです。
その証拠に、再建したばかりの田畑と家屋家財をすべて売却し、その売却代金全額と,引越費用として支給された50両を加えた資金から134両を桜町仕法の「土台金」に織り込んでいるのです。
尊徳の桜町復興の施策は次のとおりです。意欲を喚起をさせるため出精者の表彰。基盤の整備として、荒地地開発,用排水・道・橋の修繕、生活再建のため借財整理や農間稼ぎの奨励、百姓を増やすため入植者を支援しました。
当然のことながら、桜町の仕法は簡単には進みませんでした。尊徳は村を歩いて指導していましたが、村の役人にも百姓の田植終了日を逐一報告させてもいました。村人は監視されているに等しかったと思われます。
また、契約書では,凶作の際は年貢を減じることになっていたのに、小田原藩の代官は拒否しました。「仕法年限中は尊徳の一任するので,藩の指示を仰ぐ必要はない」と明記されていたので,尊徳が抗議すると、上役の指示に慕わない彼を小田原藩は「不忠の至り」と断罪するのです。
金次郎の指導した仕法は多くの場合,領主は分度外の年貢増加分を財政に組み込むようになり,それに抗議する金次郎と対立して,両者は関係が断絶するに至っている(p259)
二宮尊徳の苦難と悟り
このように小田原藩との対立と、一部の村民ら抵抗勢力によって、仕法が進まなくなり、落ち込んだ尊徳は辞任願を出して行方知れずとなります。
尊徳は、千葉県の成田山で3ヶ月ほど修養していました。この時、尊徳は、抵抗勢力に反発されたのは、自分の思いどおりにならないことを,領民や小田原藩役人のせいにして批判したからだと反省しているのです。したがって、我を捨て,穏和な心で接すれば反発されることもない,と悟ったという。
正論を主張するだけでなく、相手との人間関係の重要性を悟ったわけです。悟った尊徳ですが、苦難は続きます。
尊徳は、財政破綻した谷田部藩(茨城県)から仕法を懇願され,桜町仕法の資金の中から1950両も支援しました。ところが、無利息五ケ年賦で返済の予定が,268両しか返済されませんでした。
さらに、復興活動で増えた収入は、藩財政に織り込まず,農村復興の仕法の基金に組み入れるよう尊徳は指導しましたが、谷田部藩は一般財源として使ってしまうのでした。尊徳の主張に対し、谷田部藩は、「財政が再建されてこそ領民の支援もできるのだ」と反論したという。
「景気よりも財政規律が大切」という現在の財務省と同じことを谷田部藩が主張しているのは、興味深いことです。
さらに小田原藩でも、年貢増加分を財政に組み込むだけでなく、村民と金次郎が結びつくことで,「動乱」を恐れた小田原藩は、仕法を撤廃し、尊徳と領民が接触するのさえ禁じたのです。
金次郎の借財整理は・・高利の借財を無利ないし低利に振り返るのである・・一方,農村の復興は・・荒地開発,窮民撫育,人別増加策などによってもたらされた農業生産力回復の成果を,くり返し復興事業に投下する(p231)
民間活発化と貸与による資金循環
尊徳の考え方を現代に当てはめれば、税収と人口を増やすためには、民間の活動が活発になり、豊かになればよいということです。そのためには、一定期間税率を減らして、その増えた税収は、民間の活動支援に使っていくことです。
現実の日本は、デフレ下の民主党政権時に消費税10%を決めるなど、逆のことをやってきたわけです。
また、尊徳は支援金は、無償ではなく貸与としています。無償なら財源はすぐに尽きてしまいますが、低利の貸与なら本人の努力によって返済でき、財源が循環し,さらに多くの人を救うことができるのです。選挙対策で、無償でお金を支給したりしていますが、必要な人に資金を貸与するという選択肢もあるのでしょう。
二宮尊徳が身近に感じられる精密に調査された一冊でした。★5とします。大藤さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・政府が「報徳記」に注目し,普及させようとしたのは,大蔵卿松方正義のデフレ政策により農民の没落が急速に進み,農村の更生が課題となっていたからである(p294)
・農村人口の流出した都市部では,人口密集のために衛生環境が悪く,死亡率が高かった(p13)
・金次郎は母の死後,伯父万兵衛の家に身を寄せて夜学したが,その時に読んだのは・・友人からもらった読み書きの手本や算数の書物であった(p34)
・実は近世社会においては,読み書き計算ができなければ農家経営もできず,社会生活も営めないような状況が生まれていたのである。したがって,農家の子どもの多くが勉強していたのであって,何も金次郎のみが特別だっただけではない(p40)
▼引用は、この本からです
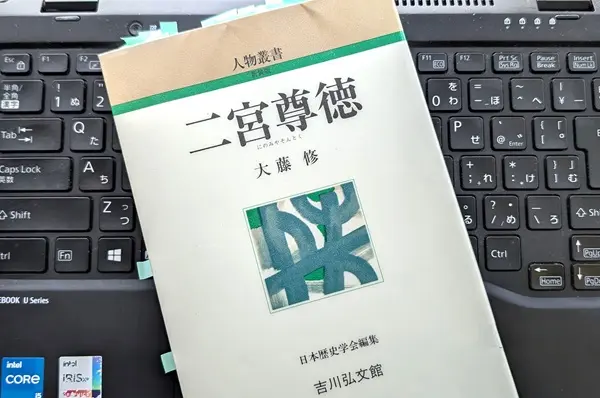
Amazon.co.jpで詳細を見る
大藤 修 (著)、吉川弘文館
【私の評価】★★★★★(90点)
目次
第1 誕生と時代・生活環境
第2 自家・総本家の没落と再興
第3 小田原城下での武家奉公と服部家仕法
第4 野州桜町への道程
第5 桜町領復興の苦難と成就
第6 思想の体系化と報徳思想の成立
第7 報徳仕法の広まりと幕吏就任
第8 領主階級との確執
第9 老いと死
第10 近代報得運動と少年「二宮金次郎」形象
著者経歴
大藤 修(おおとう おさむ)・・・1948年、山口県生まれ。1971年、茨城大学人文学部文学科卒業。1975年、東北大学大学院文学研究科博士課程中退。現在、東北大学大学院文学研究科教授、博士(文学) ※2012年11月現在
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!








































コメントする