【書評】「逆襲される文明 日本人へ4」塩野 七生
2020/06/01公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(79点)
要約と感想レビュー
消費税は消費を罰する税金
イタリア在住の著者が、ローマ帝国の歴史を書きながら祖国日本を考える一冊です。
イタリアではEUの緊縮財政で、失業率が13%と高く、若者は半分が失業しているという。さらに流入する難民問題があります。移民と緊縮政策による不況により、若い世代となると二人に一人が失業者だという。
それを知ってか知らずか、日本は消費税を10%に増税しました。消費税は、消費を罰する税金ですから、日本の景気は落ちていくのでしょう。
イタリアの消費税率は22%という、非人間的な水準にある・・・新聞も雑誌も書籍も売れ行きは落ちる一方で、テレビの視聴率も落ちている・・・消費税を少しくらい低くしても効果はないのだ(p155)
中にいる人材を活用していく
面白いのは、国が停滞期に入ったときにどうするのか、という著者の思索でしょう。著者は、古代・ローマの歴史を見ながら国が停滞期に入ったとしても人材はそこにいる。人材を活用できない仕組みの問題である、というのです。
だから、自分たちが持っている強みと、中にいる人材を活用していく方法を推奨しています。つまり、人材をリストラするのではなく、隠れた人材が活躍できる仕組みを模索するということです。
なぜなら、ローマとヴェネツィアは政体改革で長期の安定を維持したのに対し、ギリシアやフィレンツェでは頭脳流出が起きて、衰退してしまったのですから。
人材は常におり、どこにでもいる。その人材を駆使するメカニズムが機能しなくなってくるだけ、という著者の言葉が印象的でした。日本にも人材はいるはずですので、こうした人材が活躍できる仕組みが 必要なのでしょう。
ギリシアやフィレンツェでは、サビを取り除くのを、リストラという方法に訴える。歴史的に言えば、国外追放。おかげでギリシア時代のアテネやルネッサンス時代のフィレンツェでは、テニストクレスやレオナルド・ダ・ヴィンチのような、頭脳流出の先例を作ってしまうことになる・・リストラしないで国を立て直すのと、リストラしてでも繁栄を手にするやり方を比べてみると、長期的に見れば前者が成功したのは、歴史が示すとおりだ。リストラ主義だと短期に回復を達成できるが、それとて長くはつづかない(p250)
宗教は攻撃的だから政教分離
著者は宗教の本質は、戦闘的であり攻撃的であるという。実際、500年前、ローマ法皇は免罪符キャンペーンを展開し、ドイツ人がだまされました。この詐欺に怒ったのがドイツ人のルターで、プロテスタンティズムが始まったのです。
だからキリスト教世界では、その一神教を守りながら弊害からは逃れるために政教分離しているというのです。日本では宗教の政党がありますが、大丈夫なのでしょうか。
日本が衰退するのか、それとも文明を維持できるのか、人材活用にかかっているのだと再確認しました。塩野さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・言葉ひとつで気分がプラスに向かうという日本社会の真実は、言葉が変わればマイナスの方向に急降下しかねない、ということでもある。もしも日本の現代史を書く外国の歴史家がいるとすれば、日本の衰退が決定的になったのは「保育園落ちた日本死ね」からであった、と書くかもしれないのだ(p177)
・ローマ帝国の終わりの始まりは、驕ったからではなく、絶望したからではないかと思い始めたのだ。この巻の最初の主人公は哲人皇帝と讃えられたマルクス・アウレリウスだが、この人は侵入してくる蛮族への対策中に、ウィーンで死んだのであった(p188)
・指導力を発揮するには、勝つだけでは充分でなく、勝って譲る心がまえが必要になってくる・・・ドイツ人には、歴史的にも気質的にも、これが無い。(p125)
・EUには、建前とはいえ、リーダー国はあってはならないと決まっている。だが、この種の考え方は理想かもしれないが、現実的ではない。なぜなら人類は、現代までの2500年にわたってあらゆる政体、つまり王政から共産主義までのあらゆる政体を考え出し実験してきたのだが、指導者のいない政体だけは考え出すことができなかったという事実を忘れているからである(p54)
・500年も昔にすでに、マキアヴェッリは書いている。統治者は、愛されるよりも怖れられるほうがよいと・・・怖れられていれば相手も行動に出る前に熟慮を重ねざるをえなくなり、それが暴走を阻止する役に立つ、というわけだ。「清」一本槍のオバマは、軽蔑されていたのだ(p43)
・デモクラシーも,引っくり返しただけでデマゴジーに転化する可能性を常に内包している・・・「デマゴーク」・・・実現不可能な政策であろうとそのようなことは気にせず、強い口調でくり返し主張しつづけることで強いリーダーという印象を与えるのに成功し、民衆の不安と怒りを煽ったあげく一大政治勢力の獲得にまで至った人のこと。つまり、扇動家(p218)
・私は、わが日本が、このドイツとイタリアの中間を行ければと切に願っている。つまり、勝たなくてよいが絶対に二度と負けないこと。安全保障問題とは、これに遂きるとさえ思う(p135)
【私の評価】★★★☆☆(79点)
目次
国産できた半世紀
イタリアの悲劇
ユーモアの効用
ヨーロッパ人のホンネ
ある出版人の死
女たちへ
朝日新聞叩きを越えて
一神教と多神教
テロという戦争への対策
悲喜劇のEU
イスラム世界との対話は可能か
一多神教徒のつぶやき
「保育園おちた日本死ね」を知って
ローマ帝国も絶望した「難問」
「会社人間」から「コンビニ人間」へ?
若き改革者の挫折
負けないための「知恵」
がんばり過ぎる女たちへ
政治の仕事は危機の克服
著者経歴
塩野 七生(しおの ななみ)・・・1937年7月、東京生まれ。学習院大学文学部哲学科卒業後、イタリアに遊学。1968年から執筆活動を開始。1970年、『チェーザレ・ボルジアあるいは優雅なる冷酷』で毎日出版文化賞を受賞。この年よりイタリアに在住。1981年、『海の都の物語』でサントリー学芸賞。1982年、菊池寛賞。1988年、『わが友マキアヴェッリ』で女流文学賞。1999年、司馬遼太郎賞。2002年にはイタリア政府より国家功労勲章を授与される。2007年、文化功労者に。『ローマ人の物語』は2006年に全15巻が完結
この記事が参考になったと思った方は、
クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓ ![]()
人気ブログランキングへ
| メルマガ[1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』] 3万人が読んでいる定番書評メルマガです。 >>バックナンバー |
| |
この記事が気に入ったらいいね!
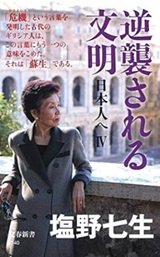









































コメントする