【書評】「人類は21世紀に滅亡する!?[真の豊かさ]への超発想」糸川英夫
2014/04/11公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(77点)
要約と感想レビュー
バブル崩壊は60年周期
逆発想の天才、糸川先生が亡くなる5年前に書いた書籍です。自分が生きられないであろう21世紀を見据えて、私たちに伝えたかったことは何でしょうか。
まず、資本主義は60年サイクルで大きく変動するということです。
1870年 ロンドン大恐慌
1930年 ニューヨーク大恐慌
1990年 日本のバブル崩壊
2050年には、どこでバブルが崩壊するのでしょうか。
暴走(バブル)により経済システムは破綻をきたすのです・・不思議なことに18世紀でも19世紀でも、時間的にはちょうど六十年なのです。(p72)
定年後も働きなさい
そして、60歳で定年で引退するのは止めなさいと提言しています。引退して、ただ生きるというのは、牢獄で生活するようなもの。これからは、60歳から「これからまたひと仕事できる」時代なのです。
仕事をしていれば、人は張りを持った生活ができるのです。生涯現役がいいということです。
「リッチな年金生活」は"地獄"だった・・・仕事をする喜びがない。したがって、それでお金が入るという喜びがないのです。(p164)
グローバル化は不安定になる
資本主義が進んでいくと、グローバル化という名のもとに、人が移動し、世界は不安定化していきます。そして、人が移動すると文化的衝突により、生活習慣が変化し、社会が不安定化していく。
21世紀は不安化の時代なのです。そうした中で大きな紛争は回避するには、強大な世界の警察官が必要となると予測しています。
それはアメリカであり、アメリカの力が弱くなったとき、不安定化が顕在化してくるのです。今の時代をまさに予言しているように感じました。
糸川先生、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・農作業は全部、機械で行っている。トラクターに乗って、それこそ手と指だけで操作するから、足は全然、使わない。・・・足の機能が低下すると、人間の全機能が低下するのです(p186)
・景気はいいのだけれども、職場がないというのが世界の大問題です・・・世界中でお金をもらう人ともらわない人が、はっきり分かれてきたというだけの話です(p93)
・お香というのは実はドラッグだったのです・・・一杯飲むなんていうアルコールだって立派なドラッグです・・・ケミカルなもので人間の体を左右するこういう方法では、「真の豊かさ」は手に入れたとはいえないでしょう(p59)
・何歳でもゼロから達人になる方法・・・基本の点をまず覚える・・一日に一ミリずつ以上には動かさない・・・階段をこまかく分ける・・・階段を一歩上がったときに、周りの人が必ず拍手する(p148)
徳間書店
売り上げランキング: 276,207
【私の評価】★★★☆☆(77点)
目次
第1章 地球の袋小路からの脱出―現代世界は危機でいっぱい
第2章 行き詰まりの経済からの脱出―不況、失業、高齢化の波のなかで
第3章 "豊かな老後"を考えることからの脱出―人はいつも現役
第4章 閉塞した「技術」からの脱出―新しい「科学」に向かって
第5章 民族間対立からの脱出―分かち合うことを説くポピュレーション理論
第6章 「技術国・日本」からの脱出―サイエンスの本質を考える
著者経歴
糸川 英夫(いとかわ ひでお)・・・・日本の工学者。(1912年7月20日生まれ、1999年2月21日没)専門は航空工学、宇宙工学。ペンシルロケットに始まるロケット開発で「ロケット開発の父」と呼ばれる。1967年、東大を退官し組織工学研究所を設立。
この記事が参考になった方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
人気ブログランキングに投票する
![]()
![]()
読んでいただきありがとうございました!




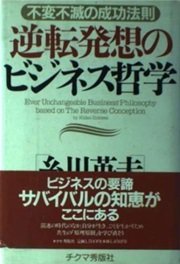



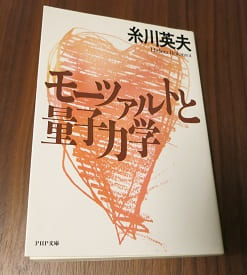

































コメントする