【書評】「人間の器量―人間通"報われる男"の生き方!」童門 冬二
2013/01/17公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(82点)
要約と感想レビュー
歴史に学ぶ人間の器量です。「人間の器量」とは、人に好かれることだと感じました。逆にいえば、人に嫌われないこと。いくら正しくても、いくら良いことでも、人に嫌われたら何もできないのです。頭の良い人ほど、落とし穴に落ちる可能性があるようです。
例えば、石田三成は頭がよく、秀吉に取り立てられましたが、周囲の大名からは嫌われていました。三成が正しいことを主張するたびに、多くの大名は、三成を恨んだのです。主張が正しければ正しいほど、三成を恨んだのでしょう。
・お前(三成)は頭がいい。また、確かに正しい。しかし、その正しさを物差しにして、いつも他人を裁く。人間はすべてお前のように優秀でもなければ、正しくもない。弱い人間もいる。そこを、グサッとやられれば、逆にお前を恨む。(p96)
頭のよい人は、他人がバカに見えます。自分はわかっており、人は分かっていない。確かにそれは事実でしょう。しかし、人に嫌われるということは、人の気持ちがわかっていない、ということでもあります。物の道理はわかっても、心の道理がわからなくては、人の心をつかみ権力を手にすることはできないのです。
人はそれぞれの利害と感情によって動いています。難しい問題があれば、解決策があるとしても利権を持っている人に気兼ねして、中途半端な対応しかできないこともあるのです。そうした人の心の微妙なところを理解しながら対処することが、組織の中で出世する秘訣なのでしょう。
・人の評判ほどアテにならないものはない。皆に評判がいいからといって、本当にいい人間かどうかわからない。(徳川頼宣)(p22)
正しい、正しくないは論理であり、人の気持ちとは感情なのですね。これから10年は人の心を大切にしていきたいと感じました。童門さん、良い本をありがとうございました。
この本で私が共感した名言
・自力で富め。藩は手を添えるだけだ。嘘はつかない(由利公正)(p166)
・江戸で火災が起こったとき、自ら部下を指揮して消火に努めた大名がいた。皆はほめたが、家光は「ばかだ」と言った。理由を聞くと、「消防には専門家がいる。そんなときに、素人が飛び出しても、もし、大事な部下を死なせでもしたら、どうする気だ?」と答えた。(p15)
・立派な家訓が多い家ほど早く潰れる(p47)
・人間、六十を過ぎたら身を退くべきである。六十過ぎても、まだ何かしようというのは、まったく自分を知らないためである。自分を知らない者に、他人のことがわかる道理がない。他人がわからずに、どうして事業ができようか(徳川頼宣)(p26)
・管理人が小作人をいじめたり不正を働くと、すぐクビにした。管理人のほうが終始ビクビクしていた。・・・貧乏な農民の中には、「借りた金を返して土地を取り返すよりも、このまま本間さまの小作人でいたほうが楽だ」という者の多かったという(p177)
・老中たちが脅威に感じたのは、毎日の会議で吉宗がビシビシ質問することだった。「井上、幕府の今年の収入高は?」・・・もちろん吉宗のほうは知っていた。(p242)
三笠書房
売り上げランキング: 191,139
【私の評価】★★★★☆(82点)
目次
第一章 この"器量"があればこそ人は自分を託す
第二章 この"実直な生きざま"に学ぶ
第三章 人徳には理屈を超えた力がある
第四章 「配慮」の知恵を学ぶ
第五章 難局打開もこの器量一つ
第六章 自分の器量を育て上げる
著者経歴
童門冬二(どうもん ふゆじ)・・・作家、本名・太田久行。1927年、東京に生まれる。第43回芥川賞候補。目黒区役所係員を振り出しに、都立大学事務長、都広報室課長、広報室長、企画調整局長、政策室長を歴任。1979年退職。在職中に累積した人間管理と組織の実学を歴史の中に再確認し、小説、ノンフィクションの分野に新境地を拓く。
読んでいただきありがとうございました! この記事が参考になった方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
人気ブログランキングに投票する

| メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」 50,000名が読んでいる定番書評メルマガです。購読して読書好きになった人が続出中。 >>バックナンバー |
| 配信には『まぐまぐ』を使用しております。 |





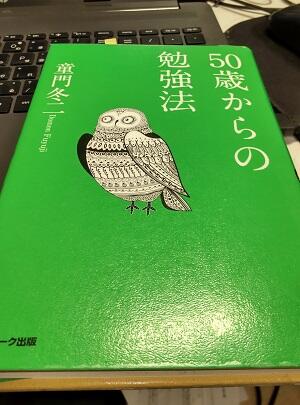





































コメントする