【書評】「マイメンター: 「できない私」卒業! 仕事がちょっと楽しくなるサラの成長ストーリー」尾関克己, 岸良裕司, 岡本崇史
2025/11/24公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(86点)
要約と感想レビュー
100日の在庫と押し込み販売
実話に基づく製造工場での改善事例を、帰国子女のサラと如月おじさんが教えてくれる一冊です。問題の工場では、百日分の在庫を抱え、赤字が累積し、工場の撤退が検討されていました。
営業では百日分の在庫を減らすために、その在庫を販売店に必死で押し込んでいました。例えば、たくさん仕入れてくれたら値下げするとか、たくさん売ったらリベートを渡すなどしていたわけです。
サラと如月おじさんは、どうやって赤字の工場を黒字化させるのでしょうか。
これまでは営業の目標必達で販売店に、半ば無理やりに商品を押し込んでいた(p150)
100日の在庫を7日分に減らす
実話に基づくということなので、答えは在庫を7日分に減らすことです。つまり、販売店で売れたら、工場で作って輸送するために必要な7日分だけ在庫を持つのです。
工場の作業員は「一部の材料は3カ月前に発注しないと納入されないから、在庫7日分なんて無理」と叫びます。それに対して、サラと如月おじさんは、在庫が100日分あるので、在庫を7日間とすると93日生産が止まります。その間に、短期間に納入できるサプライヤーを探し、どうしても短期間に納入できない材料だけ在庫を持つことを提案するのです。
製品の在庫を100日分持つよりも、納入に時間のかかる一部の材料だけを100日分の在庫を持つようにすれば、量も購入資金も少なくて済むというわけです。
では、製品で百日の在庫を抱えるのと、リードタイムの長い一部の材料だけを百日分抱えるのと、どちらのリスクが高いですか?・・材料なら使い回しができるし、単価も安い(p130)
市場連動生産と在庫の適正化
工場では在庫が7日分を切った商品だけ生産がはじまります。つまり、販売店で売れた分だけ生産し、従業員たちは帰宅していくようになりました。
それまでは、上から言われた計画通りに製品を作っていた工場が、市場の動きを見ながら売れ行きに合わせて製造する工場へと変貌したのです。
販売も売れる商品も売れない商品もセットで売り込んでいたのをやめて、売れる商品を売れただけ届けるという販売方法に変わりました。つまり、値引きもリベートもなく、売れる商品だけを作って納入するようになったのです。
そうすると次の段階は、一番売れる商品が7日の在庫ではいくら生産しても在庫が増えないという状況になります。つまり、生産が間に合わないのです。そこで、常に出荷される人気商品は在庫を増やすという需要連動生産(ダイナミックバッファー)という仕組みが導入されるのです。
工場が実現した短い供給納期を武器に変えることにした。つまり商品ではなくこの在庫回転率というサービスを売ればいい・・押し込みはやめよう(p150)
仕事の目的・成果物・成功基準
こうした改善プロジェクトの「目標の擦り合わせ」も素晴らしいと思いました。つまり、プロジェクトの実施前に目的、成果物、成功基準を明確化するのです。
そして、プロジェクト関係者全員でプロジェクトの目的、成果物、成功基準を共有して工程も全員で作っていくのです。みんなで議論して作った工程だから、目標の工期が危うくなってくると、自然に全員が助け合うようになるのです。
ソニーの事例かなと思いましたが、なんだ「知らないからできる 既成概念を覆す「0(ゼロ)ベース思考」」と同じ内容じゃないですか!尾関さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・広ければ広いほど本当は効率が悪くなるんだ。ずっと置きっぱなしなるものが増えてくる。つまりものの滞留が増えてくる・・返品されたものからどんどん修理していく(p39)
・実際に工程表を作ってみましょう・・・「その前にやることは何ですか?」・・「本当にそれだけですか?」・・「〇〇したら、××できるんですね?」・・ベテランの豊かな経験に基づく巧みな段取りが工程表の中で明らかになっていく(p205)
・「問題が上ってきたときにはどうすればいいんですか?」・・・「何か助けられることはない?」って聞くんです(p218)
▼続きを読む
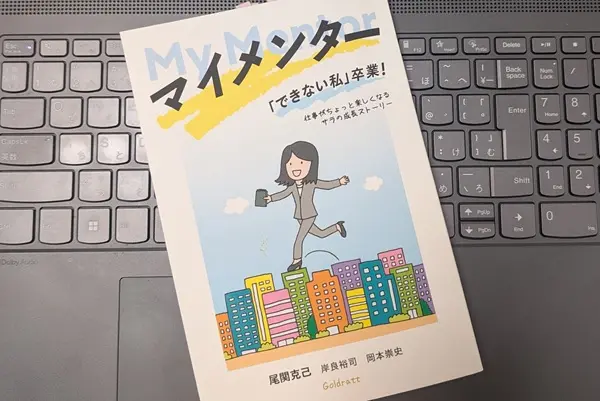
Amazon.co.jpで詳細を見る
尾関 克己, 岸良 裕司, 岡本 崇史 (著)、自費出版
【私の評価】★★★★☆(86点)
目次
第1章 逆境はチャンス
第2章 流れの改善が業務のキモ
第3章 既成概念からの解放
第4章 マネジメントが変われば現場も変わる
著者経歴
尾関 克己(おぜき かつみ)・・・(株)ゴールドラット・ジャパン パートナー。元ソニー(株)生産戦略統括部長、ソニーエリクソン(現ソニーモバイル)中国総経理。倒産の危機にあった英国工場を立て直す。台湾では携帯電話事業の立て直し、北京では携帯電話工場の総経理として最悪の成績だった工場を半年で世界一にした。2009年から(株)ゴールドラット・ジャパンに転職し、オムロンヘルスケア、千寿製薬、ダイワハウス等で全体最適のマネジメントを導入して目覚ましい成果を出している。本編の主人公のモデルとして監修を担当。
岸良 裕司(きしら ゆうじ)・・・(株)ゴールドラット・ジャパンCEO。全体最適のマネジメント理論TOC(Theory Of Constraint:制約理論)を実践し、活動成果として発表された「三方良しの公共事業」はゴールドラット博士の絶賛を浴び、2007年に正式に採用される。2008年、ゴールドラット博士に請われて、イスラエル本国のゴールドラット・コンサルティング・ディレクターに就任。本編の全体構成と監修を担当。
岡本 崇史(おかもと たかし)・・・外国語大学英米語学科に入学後、作家になるために中退。本編の執筆を担当。
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!







































コメントする