【書評】「ホワイトカラーの生産性はなぜ低いのか 日本型BPR 2.0」村田 聡一郎
2025/08/18公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(84点)
要約と感想レビュー
ホワイトカラーの生産性を高めよう
タイトルのBPRとは、Business Process Re-engineering、企業の業務プロセスを見直すということ。つまりこの本では、業務プロセスを再構することによって、ホワイトカラーの生産性を高めましょうと提案しているのです。
なぜなら日本では、生産現場の少人化は改善活動によって進みましたが、なぜか管理部門については少人化どころか肥大化しているという。それが、1人あたりGDPが日本の製造業が18位、全業種で比較すると30位という数字の原因になっているというのです。
確かに、技術系は現場なので効率化してきたイメージがありますが、総務や資材や経理などで実際に人を減らしたという話は、最近まであまり聞いたことがありません。
海外ではERP(統合基幹システム)を導入することで、ホワイトカラーの生産性を高めてきた実績があるので、日本の企業も真似するべしというのが著者の主張なのです。
ただし、著者は主要なERP(統合基幹システム)の一つであるドイツのSAPジャパンの部長なので、割り引いて読む必要があります。
欧米企業の経営者は、それまでホワイトカラー社員がやっていたタスクのうち、定型的な部分から少しずつ剥がして、ソフトウェアに渡していった(p52)
典型的な日本の職場とは
著者の観察した典型的な日本の職場では、部分最適のプロセスやルールが定型化されず、そのまま残って属人化していて、その人が抜けると仕事が回らない状態。担当者は「多能工化」どころか「私はこの仕事しかできません」と恥ずかしげもなく言い放つ始末。
古いシステムを変えようとしても部門システムが相互につながって、簡単に改善もできなければ、置き換えもできない。ひどい例だと、部門でExcelデータを送付し合っていたり、紙のデータを「二重入力」したりしている職場もあるのです。
営業システムだとFAXで受注してOCR(文字認識ソフト)で取り込む会社もまだ存在しています。そもそもFAX受注をWeb受注に切り替えれば、読み取りの時間もミスもゼロになるのにです。
著者は、こうした状況が放置された原因は、管理監督者つまり経営陣や上級管理職の責任であるとしています。ホワイトカラーの人たちは、それぞれの職場で頑張ってきたのです。自分のやり方で改善してきたので、属人化し、部分最適になってしまったというわけです。
手順通りにやったところで「人並み」になるだけで、人並み以上にはならない。それなら定型化などせず、「自分のやり方」でやったほうが差別化できる(p172)
典型的な欧米の職場とは
欧米企業ではどうしていたのかというと、ホワイトカラーの職場に「デジタル自働機械」つまりERP(統合基幹システム)という枠を履かせ、オンラインで一括管理できるようにしたという。なぜなら欧米企業では、部門長は「労働生産性を毎年1割改善せよ」などとプレッシャーを受けているからです。
そのためホワイトカラーに対して、部門長は少人化圧力をかけざるを得ず、より少ない人数で、価値のある業務だけを実行させるのが当然のことなのです。当然、価値を産まないグレーゾーン業務は管理職が「やめていい」と言ってやる必要があるのです。
人の生産性を測定し、改善していくというのはキーエンスや京セラの経営管理の考え方そのものだと感じました。
ホワイトカラーから定型業務を剥がす・・ソフトウェアという機械に「人間の知恵を付けて自働化する」(p243)
顧客価値を最大化する
著者は優れた企業を、「顧客価値の最大化を軸に、優れた業務プロセスを持ち、それを高度化させていく仕組みを持つ企業」と定義しています。正論ですね。したがって、日本の得意なボトムアップの「ヒトの現場力」とトップダウンの「全体最適の追求」、両方の合わせ技が必須と主張しているのです。
そしてERP(統合基幹システム)を導入すれば、月末を待つまでもなく、毎日いつでも、最新の状況を見て、現場に指示を出すことができるというわけです。
一番の問題は、手にしたデータを仕事に活用できるのか、そうした管理職の頭になっているのかということなのでしょう。つまり本当の意味で、顧客価値の最大化を業務の中で実践できるのか、ということです。その点をERP導入前に考えたいものです。
村田さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・日本のホワイトカラー社員は「グレーゾーン業務」、つまり顧客価値にあまり影響がない社内業務や調整業務に多くの時間を費やさざるを得なくなっている(p4)
・トヨタでは・・1会議のムダ・・2根回しのムダ・・3資料のムダ・・一枚以上の資料を準備していませんか?・・4調整のムダ・・5上司のプライドのムダ・・「自分は聞いていない」と言ってませんか?・・6マンネリのムダ・・7「ごっこ」のムダ・・「しゃんしゃん」会議をしてませんか?(p200)
・設計段階での原価、製造部門における原価、営業部門が認識している原価は互いに異なっていることが多い・・すれ違うわけである(p115)
▼引用は、この本からです
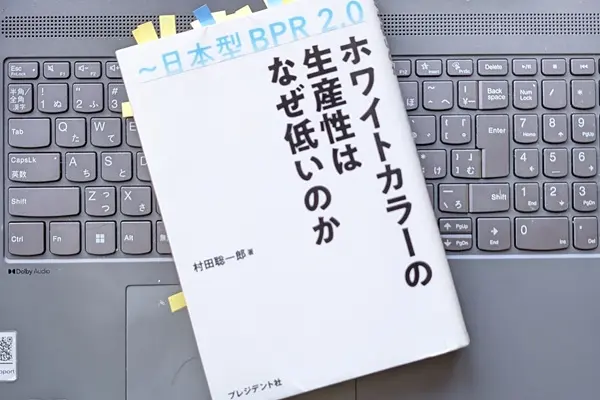
Amazon.co.jpで詳細を見る
村田 聡一郎 (著)、プレジデント社
【私の評価】★★★★☆(84点)
目次
Chapter 1 生産性のカギは「人間性の尊重」
Chapter 2 日本の置かれた現状
Chapter 3 ホワイトカラーの生産性革命とは
Chapter 4 部分最適vs全体最適
Chapter 5 ホワイトカラー業務の本質
Chapter 6 現場主導のカイゼンによる生産性アップの限界
Chapter 7 日本型BPR 2.0=変革の仕組み化
著者経歴
村田聡一郎(むらた そういちろう)・・・SAPジャパン株式会社 カスタマー・アドバイザリー統括本部 コーポレート・トランスフォーメーションディレクター。1969年神奈川県生まれ。米国Rice UniversityにてMBA取得。外資系IT企業、スタートアップを経て、2011年SAPジャパン入社。顧客の企業変革を支援する。海外事例にも精通し、講演多数。COO養成塾 事務局長。白山工業株式会社 社外取締役。「合い積みネット」共同創業者。
ホワイトカラーの生産性関連書籍
「トヨタ生産方式の逆襲」鈴村 尚久
「ホワイトカラーの生産性はなぜ低いのか 日本型BPR 2.0」村田 聡一郎
「トヨタ式ホワイトカラー革新」金田 秀治 近藤 哲夫
「吉越式 利益マックスの部下操縦術」吉越 浩一郎
「トヨタで学んだ動線思考 最短・最速で結果を出す」原マサヒコ
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!

































コメントする