【書評】「なぜパワハラは起こるのか:職場のパワハラをなくすための方法」宮本剛志
2025/10/10公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(80点)
要約と感想レビュー
パワーハラスメントの定義
2022年にパワーハラスメント防止法が全企業義務化されました。パワーハラスメント防止法では、1 優越的な関係,2 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの,3 労働者の就業環境が害されるもの、この3つの要素がすべて当てはまった場合を「パワハラ」と定義しています。
暴力や資料を投げつける、会議の時に机を叩いて脅すなどは、明らかなパワハラでしょう。
必要以上に「なぜできないの?」「なぜそうなるの?」と問い詰めて,追い込んでしまうのもパワハラだという。トヨタの「5回のなぜ」も、使い方や言い方によってはパワハラなのです。
中途採用の人に「普通,できますよね」と教えずに、「なんできないんですか?!」と自分が教えなかったことを棚に上げて,繰り返し問い詰めた事例もあるという。
この本では、こうしたいろいろなグレーなケースを教えてもらえるのです。
グレーなケース・・・皆の前で叱るのはパワハラ?(p84)
パワハラを放置するのはリスク
最近は、上司の適切な指導に対して「上司にいじめられた!」という部下からの訴えが増えているという。さらには、部下から「ハラスメントとして訴えるぞ!」と脅されて、何も言えなくなってしまったケースもあるという。
本来、上司としては,「その発言はよくないよ。相手を脅す行為になる。Dさんにはいつも感謝している。ぜひ協力してほしい」と伝えるべきなのでしょう。言うべきことを言っておかないと、部下は「教えてもらっていない」と言い訳する可能性があるのです。
また、他の人へのパワハラ行為を見て見ぬふりした結果,行動がエスカレートし,ターゲットになった人が退職してしまうこともあるでしょう。パワハラを放置するのは、大きなリスクがあるのです。
見て見ぬふりした結果,・・・行動がエスカレートし,Bさんは適応障害で退職しました・・声をかけて早めに介入するようにしましょう(P72)
パワハラ防止はコミュニケーション
パワハラ防止のためには、コミュニケーションを多く取るしかないようです。コミュニケーションによって、お互いの考え方や価値観の違いを日頃から理解するしておくのです。
逆に日頃のコミュニケーションがないと、人間関係が構築できず、困っていても相談できないため、仕事のミスが増え、上司がイライラするという悪循環となるわけです。
コミュニケーションについては、メールやチャット等よりも、できれば会って話す,少なくとも電話の方がよいでしょう。誤解が生じずに済むことが多いという。
コミュニケーション・・お互いの考え方や価値観の違いを日頃から理解する(p40)
年上部下が年下上司を攻撃
最近は、上司から部下のパワハラに加え、ベテラン社員が新任上司と対立し、後輩たちに「声をかけるな、挨拶するな」と指示するケースもあるという。年上の部下が,異動してきたばかりの経験の浅い年下の上司と主導権争いをして、周囲の部下は自分の身を守るためにも、上司を無視するというパターンです。
上司の立場としては、自分の管理能力が問われると不安になるかもしれませんが、病気になる前に、相談窓口や上役に相談して適切に対応したいものです。宮本さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・暗黙のルール,組織の文化,過度なプレッシャー・・そうした様々な要素が,知らず知らずのうちに,パワハラの温床をつくりだしてしまいます(p4)
・イライラ感情のまま攻撃的なメール送信・・・生成AIです。「この文章を穏やかな表現に変えてほしい」と指示を出せば,ほんの数秒で書き換えてくれます(p125)
・「パワハラ改善カウンセリング」とうたうと,企業に情報を共有することができなくなくなってしまいます。ですから,個別「研修」という形をとります(p236)
▼引用は、この本からです
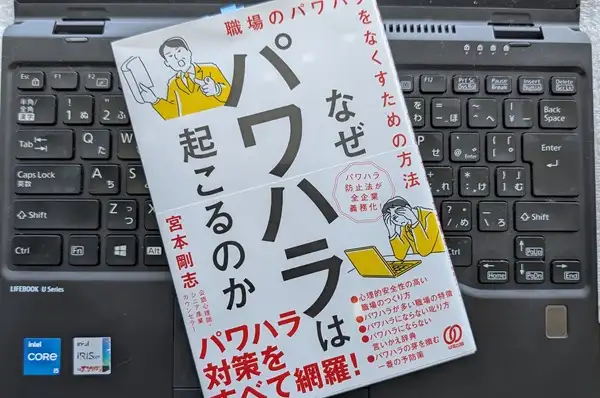
Amazon.co.jpで詳細を見る
宮本剛志 (著)、ぱる出版
【私の評価】★★★★☆(80点)
目次
第1章 パワハラってなに?
第2章 なぜパワハラは起きるのか
第3章 この場面、セーフ? アウト?
第4章 パワハラにならない上手な叱り方
第5章 その一言を変えるだけで、空気は変わる
著者経歴
宮本剛志(みやもと つよし)・・・株式会社メンタル・リンク代表取締役社長・公認心理師。管理職を経験し部下との関わり方に悩んだことをきっかけに、ハラスメントについて学ぶ。その後、ハラスメント対策を通してより良い職場づくりの支援を行うために起業。現在は、心理学に基づく研修やハラスメント被害者・加害者の面談を行う。企業のハラスメント対策委員会外部委員や顧問を務める。企業研修は年間約200回。カウンセリングは年間約400人(延べ人数)。
パワハラ関連書籍
「なぜパワハラは起こるのか:職場のパワハラをなくすための方法」宮本剛志
「一流の人は知っている ハラスメントの壁」吉田 幸弘
「パワハラ上司を科学する」津野 香奈美
「モンスター部下」石川 弘子
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!

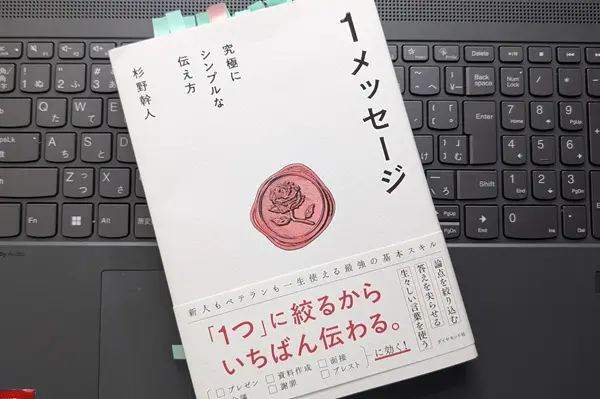
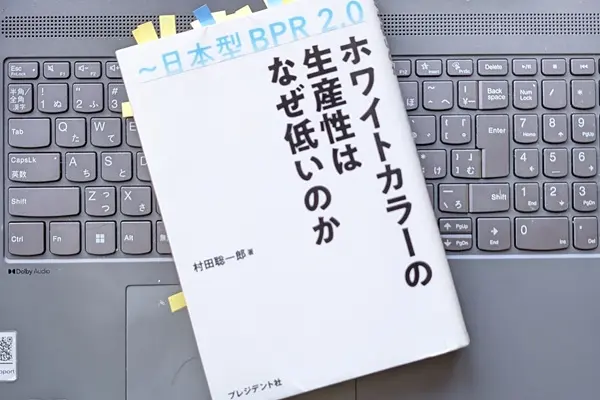
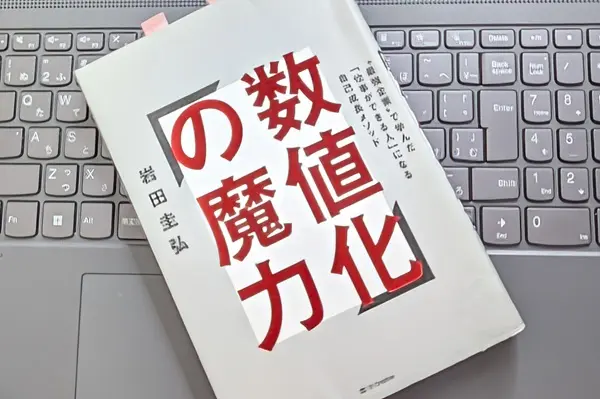
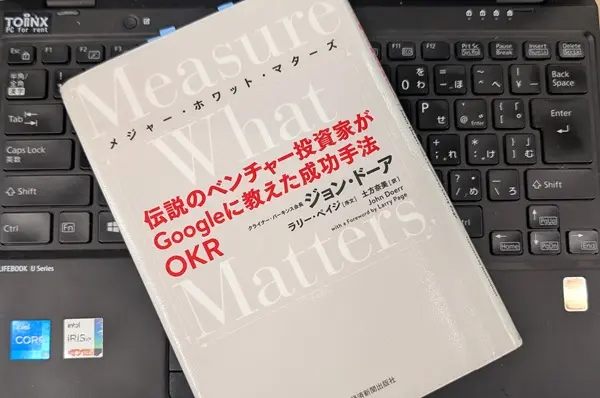
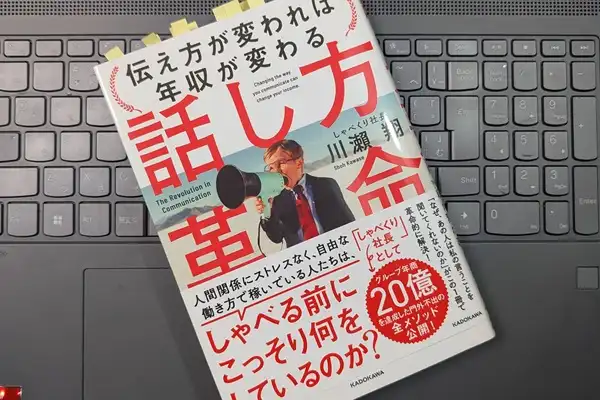
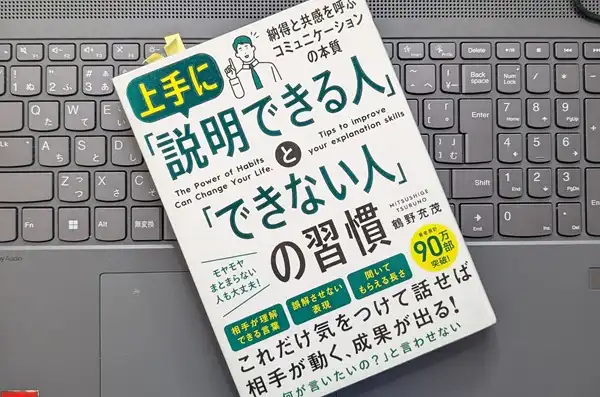
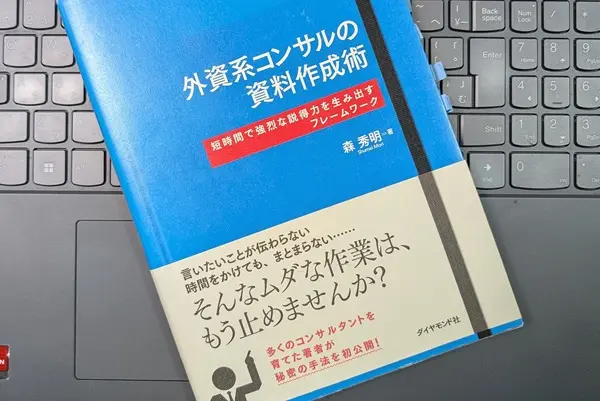























コメントする