【書評】「Measure What Matters 伝説のベンチャー投資家がGoogleに教えた成功手法 OKR (メジャー・ホワット・マターズ) 」ジョン・ドーア
2025/07/14公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(87点)
要約と感想レビュー
目標と主要な結果(OKR)とは
目標と主要な結果(OKR)とは、目標(Objectives)と主要な結果(Key Results)の頭文字を取ったものです。
企業では目標管理ということで、半期くらいで目標設定、評価、対話が行われているはずです。当時ベンチャー企業であったGoogleにも、ベンチャー・キャピタル社員であった著者が目標と主要な結果(OKR)を教えたのです。
会社での「目標」とは、経営者であれば会社が目指すべき場所であり、管理職であれば、部門の達成すべき事項です。例えば、経営者なら「市場で支配的地位を獲得」管理職であれば「メディアでの露出を増やす」といったものになります。
それに対する四半期の「主要な結果」は、測定可能なマイルストンであり、例えば、経営者なら「10件新規受注すること」、管理職であれば「交流会に記者を20人招待する」といったものになるのです。
定性的な「目標」が明確化され、それを達成しつつあるのかどうかをモニタリングするのが「主要な結果」です。
OKRの優等生だったマリサ・メイヤーは「数字が入っていなければKRとは呼べないわ」とよく言っていた(p19)
OKR運用での注意点
目標(O)は重要で、具体的で、人々を鼓舞するようなものが理想です。目標(O)は意欲を引き出すためのものであり、上司と相談しながらOKRのほぼ半分を従業員に決めさせるとよいという。仮に、すべての目標をトップダウンで設定すると、意欲は削がれてしまうのです。
また、目標による管理を厳密に給与や賞与と連動させると、リスクを取ることがマイナス評価につながることになり、従業員はリスクを取らなくなります。
さらに目標がノルマになってしまうと、従業員の非倫理的な行動を助長し、協力意識や意欲を損ない、組織的問題を引き起こす可能性が高まるのです。
目標と主要な結果(OKR)はあくまで道具であり、なぜ特定のプロジェクトに注力しなければならないのか明確にし、社員に説明しやすくするものなのです。
報酬(昇給とボーナス)とOKRを切り離す・・・勤務評定と目標管理には個別の面談が必要・・勤務評定は過去を振り返る評価で、通常は年度末に実施する(p257)
CFR(対話・フィードバック・承認)も重要
Googleの目標と主要な結果(OKR)の目標達成度は0.7だという。報酬とは切り離しつつ、高いストレッチ目標を設定しようとしていることがわかります。
またOKRを使いこなすために、継続的な対話(Conversation)、リアルタイムなフィードバック(Feedback)、そして承認(Recognition)の重要性を指摘しています。つまり、継続的にパフォーマンスを改善していくために、目標と主要な結果(OKR)について対話するのです。
優先順位が十分明確になっていないのではないか、ストレッチ目標を達成するリソースは十分か、あまりにも目標が低いのではないか、などと目標と主要な結果(OKR)を使って、リーダーと担当者の意識合わせを行います。
また目標と主要な結果(OKR)があれば、建設的な議論が可能となります。例えば、Google社内なら「なぜユーザーはユーチューブに短時間に動画を投稿できないんだ?そのほうが君たちの次の四半期目標よりも、重要なんじゃないか?」と質問できるというわけです。
(インテルの)アンディ・グローブはマネジャーが面談に90分かけると「それから2週間にわたって部下の質を高められる」と考えていた(p260)
人の意欲を引き出す方法
会社組織は人が動かすということで、ベンチャー企業でも人の意欲を引き出すために工夫しているのだと思いました。特に短期間に成果を求められるベンチャ企業では、主要な結果(KR)でどれだけ行動し、どれだけ成果を出したのか定量的にモニタリングする必要があるのでしょう。
目標と結果が数値化されることで、現場で働く従業員が、自分の仕事が会社全体の目標と連動していることがわかり、意欲が引き出されるのです。
これは個人でも同じで、目標設定とモニタリングができれば、成果が出やすいのではないでしょうか。ドーアさん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・われわれは何にエネルギーをフォーカスすべきだろうか?・・目標を絞り込むのは常に難しい。しかしその価値はある(p79)
・パフォーマンス基準と高い目標が必要だ。ただどのように業務を遂行するかは、必ずその従業員の責任と判断に委ねるべきである(ピーター・ドラッカー)(p133)
・グーグルが・・離陸するには、困難な決断を下し、チーム全体が進むべき道を踏み外さないようにする方法を身につける必要があった・・「速く失敗すること」を学ぶ必要もあった(p17)
・IT部門のすべての社員は、四半期ごとに3~5個の事業目標と、1~2個の個人目標に責任を持つ(インテュイット)(p158)
▼引用は、この本からです
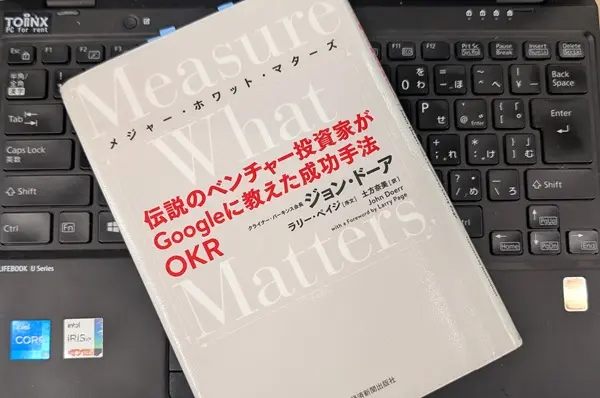
Amazon.co.jpで詳細を見る
ジョン・ドーア (著)、日本経済新聞出版
【私の評価】★★★★☆(87点)
目次
第1部 企業はOKRをどう使っているのか
第1章 グーグル、OKRと出会う
第2章 OKRの父
第3章 クラッシュ作戦――インテルのケーススタディ
第4章 OKRの威力(1) 優先事項にフォーカスし、コミットする
第5章 フォーカスする――リマインドのケーススタディ
第6章 コミットする――ヌナのケーススタディ
第7章 OKRの威力(2) アラインメントと連携がチームワークを生む
第8章 アラインメント――マイフィットネス・パルのケーススタディ
第9章 連携する――インテュイットのケーススタディ
第10章 OKRの威力(3) 進捗をトラッキングし、責任を明確にする
第11章 トラッキング――ゲイツ財団のケーススタディ
第12章 OKRの威力(4) 驚異的成果に向けてストレッチする
第13章 ストレッチ――グーグル・クロームのケーススタディ
第14章 ストレッチ――ユーチューブのケーススタディ
第2部 働き方の新時代
第15章 継続的パフォーマンス管理――OKRとCFR
第16章 年次勤務評定を廃止する――アドビのケーススタディ
第17章 明日はもっとおいしく焼こう――ズーム・ピザのケーススタディ
第18章 文化
第19章 文化の変革――ルメリスのケーススタディ
第20章 文化の変革――ボノのONEキャンペーンのケーススタディ
第21章 これからの目標
著者経歴
ジョン・ドーア(John Doerr)・・・クライナー・パーキンス会長。世界的ベンチャー・キャピタル、クライナー・パーキンスの会長。1980年にクライナー・パーキンス・コーフィールド・アンド・バイヤーズ(KPCB)に加わり、Amazon、Google、Twitterといった企業に初期段階から投資。投資先が世界的な大企業に成長するなかで、42万人以上の雇用創出にかかわってきた。
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!

































コメントする