【書評】ホワイトカラーの生産性を高める「トヨタ生産方式の逆襲」鈴村 尚久
2025/08/25公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★★(94点)
要約と感想レビュー
「トヨタ生産方式」の本質
著者は「トヨタ生産方式」の生みの親、大野耐一氏の右腕だった鈴村喜久男氏の息子です。著者は経営コンサルタントとして「トヨタ生産方式」を活用した業務改善を指導しています。ところが、「トヨタ生産方式」の本質を理解していない会社があまりにも多いので、この本を書いたのだという。
典型的な勘違いは、「鈴村さん!うちはカンバンシステムを使って在庫がほとんどありません!」という会社です。実は「トヨタ生産方式」の本質は、在庫を減らすことにあるのではなく、多品種少量生産であっても即納を可能とする「製造から販売まで適正在庫を持ち、品切れしないように補充する仕組み」なのです。
現場で必要なものを必要なだけ造るために、注文の納期はいつか、在庫量は正常なのか、異常なのか、誰が見てもわかるようにするのです。
実はそうした仕組みを構築しようとすると壁になるのが開発や営業、物流などのホワイトカラーであり、ホワイトカラーの生産性が悪い会社が多いというのです。
工場の努力を、ホワイトカラーが食いつぶしている(p149)
適正在庫量と補充を仕組化
まず、著者が指導した事例を紹介していきましょう。
最初はコンドーム製造工場です。この工場では30種類のコンドームを生産していましたが、欠品や在庫の山で困っていたという。著者が行ったのは、部品と製品を置く「ストア」を設置することです。
「ストア」とは、スーパーのように何が置いてあるか明示され、コンビニのように先入れ・先出しで、在庫量が例えば5日分になったら補充するなど決めておくのです。在庫量は、注文から入荷までの日数と1日平均販売数から計算し、統計的に考えた余裕をプラスすればよいでしょう。
それまで、コンピュータシステムで売れた分だけコンドームの製造指示をしていましたが、「ストア」のほうがリアルタイムで在庫が見えるし、補充もきめ細かくせざるをえなくなったことで、欠品や在庫がほぼなくなったという。
ところがこの話には「落ち」があって、「ストア方式」を全社展開しようとしたら上層部の抵抗に遭って断念したという。具体的な理由は書いていませんが、ホワイトカラーである上層部が壁だったのです。
工場の邪魔をするのが生産管理部門・・・新旧製品のリニューアル時になると、従来の計画生産に戻そうとする(p171)
計画生産より後補充生産
「コープさっぽろ」の案件では、自社工場で生産している豆腐や総菜、うどんなどの廃棄が、豆腐だけで年間1500万円となっていたので著者が指導しました。ここでも著者が作ったのは、「半製品ストア」「加工材料ストア」「素材ストア」です。惣菜は容器に小分けする前の段階のものを「半製品ストア」から取れるようにしたのです。
さらに、店舗への配送を、朝のみ1回から、朝・夕の1日2回に改め、こまめに補充することで、廃棄がほぼゼロになったという。導入まには物流費が高くなると抵抗されましたが、物流費以上のメリットが出たし、他のトラックに一緒に積んでもらうことで、結果して物流費は増えなかったのです。
また、自動車の交換用バッテリーでも同じように「ストア方式」で、納期3日、在庫がない場合3~4週間を即納できるようにしたという。
工業用バルブの会社でも、「特注品」の青ハンドルは自社で塗るようにして、納期3週間を即時出荷にしたというのです。
キャットフードの例では、米国からコンテナで輸入される原料の魚や肉を、コンテナ単位ではなくパレット単位で輸送することで、約8億円の運転資金が不要になったという。
店舗への配送を、朝のみ1回から、朝・夕の1日2回に改める・・物流費が高くなると抵抗・・豆腐だけで年間1500万円分廃棄していたのがほぼゼロになりました(p101)
工場よくあるロット生産の罠
工場が生産性を高めるために行っているロット生産が、壁になることもあるという。例えば、ある工場ではお客は段ボール20個くらいで注文したいのですが、工場は「段ボール4000箱を1ロット」として生産しているので、ロット単位まで注文が貯まらないと生産できず、納期遅れが多発していたという。
ガラス板工場でも、お客は2枚注文したのに、工場担当者は、「1ロット10枚単位でないと、出荷実績が計上ができなシステムになっているので出荷できません」と堂々と説明していたというのです。
また、前倒して納入が可能でも営業担当者が「2週間先に約束した車がこれから納車できますと言えば、こちらが適当なことを言っていたと思われる」とゆっくり待っていたという。
事例が生生すぎて絶句してしまいますが、2~3日あれば即納できるような製品を、「納品まで2カ月かかります」と平気で顧客を待たせている会社が多いというのです。
ゴールドラットジャパンの TOC(制約理論)の本に書いてることと、同じ内容だと感じました。短納期のほうがよいことは、当たり前のようですが、世の中、当たり前が通らないこともあるのです。鈴村さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・牛丼屋や寿司屋で注文したら、すぐ目の前に料理が出てくる・・これこそが最大の顧客満足向上(p43)
・煮豆に使うコンニャクを複数種類、使い分けていた・・・共通化すべき材料を共通化しなかったことによって、付加価値の低い仕事が増えてしまっていた(p174)
・外注する・・外注から部品を買う購買部や引き取りの検収作業の人件費・・・外注先に渡す支給部品の検査と梱包、送り状の作成に加え、受け取った方でも梱包の手間や棚入れ、完成して送り返す際の梱包など、作業は膨大に増えます(p45)
・大口注文・・ストアに置いてある通常在庫では、大量出荷に対応できないと言って、昔の計画生産に戻そうとしがちです・・ボトルネックとなるのは・・・人員確保です・・・部品・材料の手当てが何とかつけば・・・設備は2交代制(p172)
▼引用は、この本からです
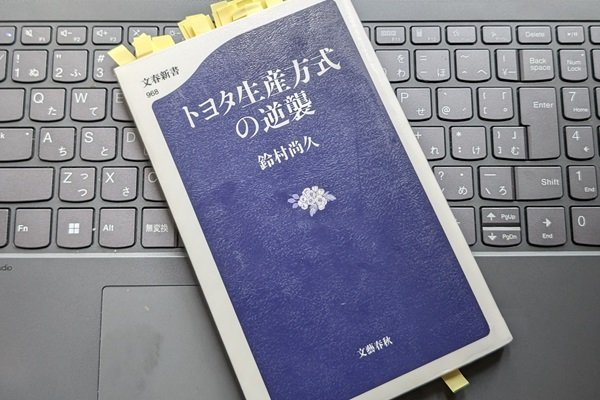
Amazon.co.jpで詳細を見る
鈴村 尚久 (著)、文藝春秋
【私の評価】★★★★★(94点)
目次
第1章 「常識」を疑い、パラダイムを変えよ
第2章 「タイミング」を売れ!
第3章 顧客ニーズと生産体制のマッチ
第4章 「サラダ理論」で需要予測とオサラバしよう!
第5章 ホワイトカラーという「魔物」
第6章 下請けを巻き込んで効率的なモノ造り
第7章 短納期こそ最大の顧客満足
著者経歴
鈴村 尚久(すずむら なおひさ)・・・1952年生まれ。1976年京都大学法学部卒業。トヨタ自動車工業(現トヨタ自動車)入社、経理部、第2購買部、産業車両部、生産調査部、販売店業務部、国内企画部に勤務。1997年退職。エフ・ピー・エム研究所を設立。父、喜久男氏は「トヨタ生産方式」の生みの親、大野耐一氏の右腕だった。
適正在庫関連書籍
「トヨタ生産方式の逆襲」鈴村 尚久
「「ザ・ゴール」シリーズ 在庫管理の魔術」エリヤフ・ゴールドラット
「世界一わかりやすい在庫削減の授業」若井 吉樹
「改訂版 データ分析できない社員はいらない」平井明夫
「ソニー中村研究所経営は「1・10・100」」中村 末広
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!
































コメントする