【書評】「電力崩壊 戦略なき国家のエネルギー敗戦」竹内純子
2024/06/04公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(77点)
要約と感想レビュー
電力会社への懲罰
2011年3月11日の東日本大震災は、東京電力福島第一原子力発電所の炉心溶融という最悪の結果となりました。その後、民主党政権下で原子力発電を安全対策実施完了まで停止させること、再エネ固定価格買取制度(FIT)導入、電力自由化の方針が固まりました。つまり、事故のリスクのある原子力は不要、自然の力を利用する再エネを増やす、競争原理の導入で電力業界を効率化する、ということです。
著者は、震災をきっかけに電力自由化が一気に加速したのは、電力会社への「懲罰」の意味を含んでいたと推測しています。大手電力会社を競争環境に置いて、その官僚以上に官僚的と言われる組織を解体することにしたというのです。本書では、こうした方針によって日本での安価で安定した電力供給が難しくなっている現状を説明しています。
現下の電力危機も、太平洋戦争も、予想される悪いシナリオを正しく向き合うことができていれば避けられたことだったと思えてならないのです(p278)
大手電力会社の電力供給責任がなくなった
2000年頃までの電力業界は、地域独占の民間大手電力会社による電力の安定供給体制という、戦前の過当競争や戦中の国家統制を反省して作られたものでした。長期の電力需給予想に基づくことで、長期契約の燃料調達を可能とし、計画的な発電所の建設計画を立案し、総括原価を国がチェックして電気料金を認可するという絶対に停電しない体制だったのです。
一方、現在の電気事業は、市場原理で価格が決まり、誰もが電気事業に参入可能で、どこからでも電力を購入できます。逆の視点で見れば、現在の電気事業は市場で価格が決まることから、発電事業者は収入が予想できないため発電所の建設を計画しにくくなりました。
また、電力の販売者が増え、前日の電力市場で調達する企業も多く、実際の需要が予想しにくくなり、燃料の購入計画が難しくなりました。燃料の長期契約はできなくなりつつあるのです。
さらに再エネの大量導入により、火力発電所が停止することが増えました。停止している発電所は収入がありませんので、火力発電所は休廃止することになります。万が一のために維持されていた火力発電所が、休廃止されているのです。大手電力会社の電力の供給責任がなくなったのも、背景にあるのでしょう。
現在は4年後の供給力確保のために容量市場が作られ、発電所が運転していようが停まっていようが固定費相当分を入札で決定し、支払われる仕組みが導入されているのです。
発電事業と小売事業には競争が導入され、それまで発電から送配電、そして小売りまでを一体的に運営していた地域の大手電力会社が負っていた「供給義務」は廃止されました(p104)
日本のLNG備蓄は2週間分しかない
電力自由化には、メリットもあります。それは多くの新規参入者が参入し、効率的でない事業者は市場から退出することです。実際、電力卸市場から電気を調達できるので、余った電気を格安で調達して、安く売るのが新電力が林立しました。大手電力会社でも、販売に不要な各地域の支店・営業所は廃止・縮小され、コールセンターに統一されつつあります。
問題は需給によって価格が変動する電力卸市場で電気を調達して、固定価格で電気を販売している新電力会社が多いことです。電力市場高騰すれば、すぐに赤字になってしまいます。海外では電気料金は市場連動が基本で、固定価格はヘッジするため割高になるのが常識なのです。2021年2月に米国のテキサス州では、寒波により1kWhの電気が9ドル(200倍)まで暴騰した事例があり、これが市場経済なのです。
日本での高騰例としては、2021年1月に寒波が来て電力需要が増加し、太陽光発電が低調な中で、大型石炭火力が故障すると、LNGが不足する事態となりました。1kWhの電気が250円(25倍)まで暴騰したのです。日本のLNG備蓄は、たった約2週間分しかないことが明らかとなったのです。
販売する電気のほとんどすべて(81~100%)を、スポット市場と呼ばれる前日の取引市場で調達して販売する小売事業者が全体の15%もいた(2020年実績)(p88)
再エネ賦課金は年2.7兆円
再エネ固定価格買取制度では、買取価格が欧米諸国の2倍以上で設定され、確実に儲かる商売として、不安定電源である太陽光や風力発電が大量導入され、日本国民が負担する賦課金は年約2.7兆円と消費税1%(2兆円)以上の負担となっています。
そもそも、2030年に温室効果ガスを2013年比で46%削減するという目標は、データを積み上げた数字ではなく、2050年のカーボン・ニュートラルを実現するために、「エイヤ」と勢いで決めた数字であると警告しています。
太平洋戦争前に、山本五十六は「半年や1年の間は随分暴れてご覧に入れる。然しながら、2年3年となれば全く確信は持てぬ」と言ったと伝えられています。「電力自由化も5年10年はなんとかなる。しかしながら、20年、30年となると全く確信は持てぬ」というのが著者の言いたいことなのでしょう。竹内さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・クルーグマン教授は「自由化してはいけないものが3つある。医療、教育、そして電気」とも述べています(p117)
・ロシアからパイプラインで天然ガスを輸入・・政府の高官だった方から・・電力会社が協力的でなかった」と恨み節を聞いた(p71)
・電動車は、単に駆動源としてバッテリーを利用したクルマですが、エネルギー産業側から見れば、電気の「時間のシフト」を可能にする蓄電池(p268)
▼引用は、この本からです
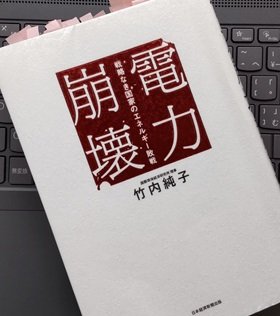
竹内純子、日経BP 日本経済新聞出版
【私の評価】★★★☆☆(77点)
目次
プロローグ 揺らぎ始めた"当たり前"
第1章 停電前夜
第2章 第三次オイルショックの衝撃
第3章 電力自由化は誰を幸せにしたのか
第4章 再生可能エネルギーは主役になれるのか
第5章 原子力事業のしんどさは誰がどう担うのか
第6章 起死回生―エネルギー敗戦を回避するには
エピローグ 敗戦を繰り返さないために
著者経歴
竹内純子(たけうち すみこ)・・・国際環境経済研究所 理事/U3イノベーションズLLC共同/東北大学特任教授(客員)。東京大学大学院工学系研究科にて博士(工学)。慶応義塾大学法学部法律学科卒業後、東京電力入社。主に環境部門を経験後、2012年より独立の研究者として地球温暖化対策とエネルギー政策の研究・提言に携わる。国連気候変動枠組み条約交渉にも長年参加し、内閣府規制改革推進会議ほか政府委員も多数務める。2018年にはU3イノベーションズLLCを創業し、新事業の創造による環境・エネルギー問題解決を目指す。
エネルギー安全保障関連書籍
「電力セキュリティ: エネルギー安全保障がゼロからわかる本」市村 健
「電力崩壊 戦略なき国家のエネルギー敗戦」竹内純子
「再生可能エネルギーの地政学」十市 勉
「世界の中の日本 これからを生き抜くエネルギー戦略」金子祥三,前田正史
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!




































コメントする