【書評】「論語と算盤(下) (人生活学篇)」渋沢栄一
2017/04/06公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(78点)
要約と感想レビュー
教育の重要性
90年前に出版された渋沢栄一「論語と算盤」のノーカット現代語訳(下巻)です。
富国強兵を押しすすめる日本は、士農工商を廃止し、誰でも教育を受けることができるようにしました。現代と同じように若者の道徳心や、先生を敬う気持ちが失われつつあることを渋沢栄一が憂いているのは面白いと感じました。
また、女性も社会の一員として、女子も男子と同様に才能や知識を高め、そして共に助け合って働くことを推奨しています。そのために女性教育に力を入れるとしています。現代社会の考え方と、ほとんど変わりません。
現代の教育は知識を重んじます・・多くの知識を詰め込む。けれども、精神の修養はほったらかしです。心を磨くことに力を注がないので、青年の人格形成は大いに危ういものがあります(p157)
人事を尽くして天命を待つ
渋沢栄一の考える公的成功とは、単なる富や名声ではありませんでした。どれだけ世の中に貢献したのかが、もっとも大切だというのです。
そして私的成功も、単なる富や名声ではありませんでした。いかに本気で取り組んだのか。全身全霊の努力を尽くして自分が納得すれば、成功しても失敗しても良いではないかというのです。仮に事業で「失敗」したとしても、決して「失敗」ではないというのです。前向きですね。
つまり、渋沢栄一は現代の成功哲学と同じように、真面目に努力し、自分で運命を切り開くことが大切と主張しています。だから失敗したとしても、「自分の力が足りなかった」とあきらめればいい。結果は天命に任せるのがいいというわけです。
本当に人を評価しようとするなら・・「その人の精神がどれだけ世の中に尽くしたか」「どんな影響を世の中に与えたか」によってするべきなのです(p24)
人事を尽くして天命を待つ
渋沢栄一は軍事力で富が支配され、領土さえ支配しようとする時代に、商工業の力で勢力が移り変わることを指摘しています。軍事力が注目されるなかで、実は国家にとって経済力が重要だとしているのです。
経済を発展させるためにも、金儲けだけ考えるよりも、国家レベルで考え、道徳心がないと国家は発展しない、ということでしょうか。道徳と金儲けの両立を目指す渋沢栄一に会うことができました。渋沢さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・どんな些細なことだろうと、どんな細かい話だろうと、ほったらかしにしておいてはならない。また、自分の意思に反することなら、それが小さい問題だろうが大きい問題だろうが、キッパリとはねつけねばならない(p44)
・中国では・・見識や人格において抜きん出た人が少ないというわけではないけれど、国民全体としてみた場合、個人主義と利己主義が強すぎることです。中国人は国家の一員という意識が乏しく、国を思う気持ちに欠けています(p115)
・政府当局にひとこと言っておきたいのは、「奨励は大いにやってほしいが、不自然で不相応な奨励となると結局は失敗する」ということです。親切なやり方もかえって結果として不親切となり、保護したつもりが干渉や束縛になったり・・(p123)
▼引用は下記の書籍からです。
致知出版社 (2016-07-29)
売り上げランキング: 81,990
【私の評価】★★★☆☆(78点)
目次
・人格と修養
・ソロバンと権利
・実業と士道
・教育と情誼
・成敗と運命
著者経歴
渋沢栄一(しぶさわ えいいち)・・・1840(天保11)~1931(昭和6)年。実業家。約470社もの企業の創立・発展に貢献。また経済団体を組織し、商業学校を創設するなど実業界の社会的向上に努めた
読んでいただきありがとうございました!
この記事が参考になったと思った方は、
クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
人気ブログランキングへ
いつも応援ありがとうございます





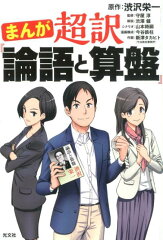



































コメントする