【書評】「貧乏国ニッポン ますます転落する国でどう生きるか」加谷 珪一
2024/06/25公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(75点)
要約と感想レビュー
海外は物価も賃金も上昇
2020年、コロナ禍の中で日本経済の凋落を指摘する一冊です。2020年当時の日本円の為替レートは、1ドル110円くらいでした。当時でも日本の世帯所得の平均値が約560万円であるのに対し、一般的な米国企業の大卒新入社員で年収500~600万円が相場で、グーグルやアップルの新入社員の年収は1500万円以上だったのです。
米住宅都市開発省が行った調査で、サンフランシスコでは年収1400万円は「低所得」に分類されていることが報道されていました。現在は1ドル160円ですので、さらに日米の差は大きくなっています。もちろんアメリカは賃金が高いぶんだけ物価も上昇しているのです。
海外は物価以上に賃金も上昇・・日本はまさに下請けにピッタリの国(p76)
円安で日本経済は復活するのか
日本は2013年からマネーの量的緩和策を取り、為替レートが円安に振れました。株価や不動産価格を上昇させ、消費を増やそうとしたのです。また、円安にすることで輸出企業の業績を上げさせ、経済を活性化させることを狙ったものと考えられます。ただでも日本の物価は安いのに、量的緩和で円安さらに日本は相対的に安い国になり、外国人観光客が押し寄せてきているのです。
ただし、外国人観光客は、日本の物価や為替レートが上昇すれば、来日しなくなるので、インバウンドは持続性のある戦略ではないとしています。著者は、まず経済を回復させることが重要であって、物価上昇はその結果として得られるものとしています。量的緩和で円安となり、経済復活となるのかどうか日本が試されているわけです。
量的緩和策というのは、あえて大量のマネーを供給・・・株価や不動産価格が上昇し、資産効果から消費が増える可能性が高まります(p104)
日本は仕事があっても貧困に陥る
著者は、日本において仕事があって貧困に陥る「ワーキングプア」が多いことを問題視しています。日本の貧困率は15.7%と高い水準であり、チリやメキシコと同じレベルであるというのです。特にシングルマザーのデータを見ると、仕事がある人とない人の貧困率に大差がないという。つまり、生活保護を受けている人と必死に働いている人の収入があまり変わらないのです。
安すぎる日本は一時的とはいえ、著者は日本人が海外に出稼ぎに行く日がやってくる可能性も高いとしています。私には海外が物価も賃金も上昇するなかで、日本だけが物価も賃金も変わらないことが問題のように見えます。
できれば、日本国内でお金を持っている人が、お金を使って、日本の景気をよくして適正な為替レートにしていく必要があるのでしょう。加谷さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・日本のGDPに占める輸出の割合は18.3%ですが、輸出大国の典型であるドイツ(46.1%)と比較するとかなり低い・・フランス・・31%・・米国の水準(12%)(p181)
・日本は国内市場をもっと大事にし、消費を活性化・・輸出やインバウンドに頼らなくても、十分に経済を成長させることができます(p183)
・サラリーマン社長を一掃すべき・・今後1年間における自社の成長について非常に自信があると回答したCEOは、日本はわずか11%(p189)
・1外国に投資する(外国で稼ぐ企業に投資する)、2外国で稼いで日本で暮らす、3外国にモノを売ることを考える(p203)
【私の評価】★★★☆☆(75点)
目次
第1章 日本はこんなに「安い国」になっている
第2章 安さだけではない、日本の転落
第3章 なぜここまで安くなってしまったのか
第4章 モノの値段はどう決まるのか
第5章 そもそも経済大国ではなかった―為替レートのマジック
第6章 日本の強みをどう生かすべきか?
著者経歴
加谷珪一(かや けいいち)・・・経済評論家。仙台市生まれ。1993年東北大学工学部卒、日経BP社に記者として入社。野村證券グループの投資ファンド運用会社に転じ、企業評価や投資業務を担当。独立後は、中央省庁や政府系金融機関などに対するコンサルティング業務に従事。現在は、メディアで連載を持つほか、解説者やコメンテーターなどを務める
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!
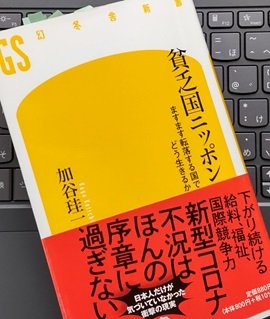






































コメントする