【書評】アウトプットがすべて「記憶脳」樺沢紫苑
2024/05/30公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★★(91点)
要約と感想レビュー
映画の内容を記憶する方法
樺沢さんの記憶術の基本は、徹底したアウトプット(復習)です。映画好きの樺沢さんは、アメリカ留学中にメルマガ「シカゴ発 映画の精神医学」を発行し始めました。樺沢さんは映画を見終わったら、すぐにその内容や感想をノートにメモするのです。(復習1回目)そしてそのメモから、メルマガを書いていたという。(復習2回目)
このようにアウトプットを繰り返すと、それが復習となり、樺沢さんは1年前、10年前に見た映画でも覚えているのです。映画に限らず、本にしてもメルマガでアウトプットしたり、人に話すと記憶に残ります。私も本を自分に読ませるためにメルマガを書き、ブログに記録していますので、20年前の本でも内容を説明することができるのです。
メモは、復習1回分に相当する・・メモは、「記憶の索引」になる(p68)
試験は記憶力の競争
樺沢さんの試験勉強法は、過去に出題された問題をノートにまとめることです。ノートにまとめるということは、「理解」と「整理」をしているということになります。この「理解」と「整理」で、記憶しやすくなるのです。そのノートを見た瞬間に、視覚でイメージとして情報が頭に流れ込んでくるという。
過去問をまとめれば、出題されることだけを覚えられるし、ノートに書けば、それが復習となって、イメージが頭の中に固定されるわけです。確かに私もノートを買いて、あのページの右上にこれが書いてあったと思い浮かぶことがありました。
試験は、過去問命!(p123)
樺沢式記憶術
その他にも、講演やセミナーの前には、樺沢さんは話す内容を小さい声を出して読む「シャドー読み」リハーサルをするという。2時間、3時間の講演でも、1度「シャドー読み」をしておくと、本番で自然と声が口から出てくるのです。
さらに樺沢さんは「締切」や「納期」を必ず守ることにしています。守ると決めれば、「火事場の馬鹿力」が自然に発揮されて、仕事力、記憶力が高まるというのです。確かに私がメルマガを毎朝書けるのも、4時半起床してから、7時半には出社しなくてはならないという締め切りがあるからだと思います。
映画にしても本にしても、感想を話せないならば、それは読んでいないも同じです。樺沢さんのようにアウトプットして記憶していきましょう。樺沢さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・人に教えると物凄く記憶に残る・・他の人に「言葉でわかりやすく説明できる」ということは、頭の中で十分にストーリー化されている(p96)
・名前は忘れやすい「意味記憶」で、患者さんがどんなことを話したのかは忘れにくい「エピソード記憶」です(p72)
・鉄砲伝来、以後予算(1543年)増える・・「語呂合わせ」は・・「意味記憶」の「エピソード記憶」への置き換え(p91)
・「1日」「3日」「7日」後に復習する(p146)
【私の評価】★★★★★(91点)
目次
第1章 「記憶脳」を鍛えることで得られる3つのこと
第2章 無理に詰め込まなくてもいい―精神科医の「アウトプット記憶術」
第3章 記憶力に頼らずに成果を最大化する―精神科医の「記憶力外記憶術」
第4章 感情が動くと記憶も強化される―精神科医の「感情操作記憶術」
第5章 無限の記憶を獲得する―精神科医の「ソーシャル記憶術」
第6章 脳の作業領域を増やして仕事を効率化する―精神科医の「脳メモリ解放仕事術」
著者経歴
樺沢紫苑(かばさわ しおん)・・・精神科医、作家。1965年札幌生まれ。札幌医科大学医学部卒。2004年から米国シカゴのイリノイ大学精神科に3年間留学。帰国後、樺沢心理学研究所を設立。「情報発信によるメンタル疾患の予防」をビジョンとし、YouTube(48万人)、メールマガジン(12万人)など累計100万フォロワーに情報発信をしている。
記憶術無料レポート
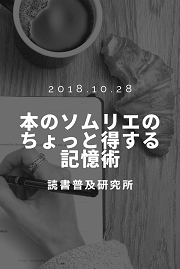
本のソムリエの「ちょっと得する記憶術」
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!
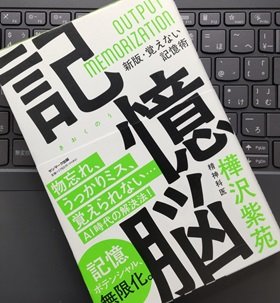





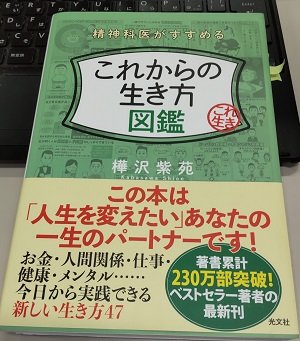

































コメントする