【書評】「定年をどう生きるか」岸見一郎
2021/04/06公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(75点)
要約と感想レビュー
副業や趣味を見つけておく
アドラー哲学を紹介した『嫌われる勇気』の著者が考える定年後の生き方です。本のソムリエも55歳になったので、この本を手にしました。著者は精神科の病院に勤めていたとき、本の翻訳の仕事をしていたという。また、哲学の先生でも休みの日に小説を書いている人もいたといいます。こうした興味のあること、儲からなくても楽しいことなどを今からやってみるのも定年後に役立つようです。つまり、仕事だけに生きがいを感じていた人は、定年を迎えると生きがいを失ってしまうことになるからです。
ただ、著者は定年後のために何かを準備しておくという意味だけではなく、自分のやりたいことを今やるということを強調しています。それは仕事がある時でも定年後でも同じことなのです。つまり、充実した人生のためには何かを成し遂げなければなりませんが、今ここに、生きていることがそのまま幸福であるとするために、やりたいことを今からやっていくのです。
早くからこのような副業や趣味を見つけておくことが、定年後の人生にとって大切だと思いますが、・・・働いている時に副業や趣味があり、それを楽しみに生きられるのがいいように思います(p65)
仕事という居場所は、定年でなくなる
仕事によって自尊心を維持していた人が定年になって仕事がなくなると不安になり、家の中で昔の状態を維持しようとしてトラブルになることがあるようです。定年で会社を辞めれば、もう会社は何もしてくれません。さらに、会社という組織に属さなくなると、誰からも注目されなくなります。
会社では威張っていても職位があれば何も言われませんが、家で威張っていては反発されることになります。特に感情的になってしまう人は、心の底では自信がないのでそうしないと自分自身を維持できない人である可能性があります。仕事が生きがいであっても問題はないと思いますが、いずれ仕事という居場所は、定年でなくなるということも考えておく必要があるのでしょう。
感情的になって大きな声を出したり、まわりの人を叱りつけたりする人は、自信がないので、普通にしていれば自分が認められないと思っているから、感情的になることで上に立とうとするのです(p77)
新しい生き方をはじめる
定年の本ではありますが、定年について考えるということは、結局、どう生きるのかということに収斂(しゅうれん)していくようです。人は死ぬまで生きるのですから、組織の中で生きられなくなれば新しい生き方をはじめるしかないのです。
その場所、その場所で楽しく生きていくことが大切であるように感じました。哲学として考えると固いのですが、成功法則と何も変わるところはないのです。岸見さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・企業研修・・・私は、人は働くために生きているのではなく、生きるため働いているのだという話をしたのです(p122)
・心の病気・・・仕事に生きたくなくなった時にどうすればいいかといえば、病気になる前に休む決断をすることです・・・逃げるところがあると思っていることは大切です(p36)
・私は精神科の医院に勤めていた時に翻訳の仕事をしていました・・・翻訳をしていたのは、日々のカウンセリングをする中で、翻訳を通じて多くのことを学べ、それが仕事にも有用だと考えたからです・・・上司はよくは思わず、そのことでぶつかったことがありました(p64)
【私の評価】★★★☆☆(75点)
目次
第1章 なぜ「定年」が不安なのか
第2章 定年に準備は必要か
第3章 あらためて働くことの意味を問う
第4章 家族、社会との関係をどう考えるか
第5章 幸福で「ある」ために
第6章 これからどう生きるのか
著者経歴
岸見一郎(きしみ いちろう)・・・哲学者。日本アドラー心理学会認定カウンセラー。日本アドラー心理学会顧問。1956年京都府生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学(西洋哲学史専攻)。前田医院精神科勤務後、専門の哲学と並行して、1989年からアドラー心理学を研究。精力的に執筆・講演活動を行っている。多くの大学の非常勤講師を務める。
この記事が参考になったと思った方は、
クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
人気ブログランキングへ
| メルマガ[1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』] 3万人が読んでいる定番書評メルマガです。 >>バックナンバー |
| |
この記事が気に入ったらいいね!
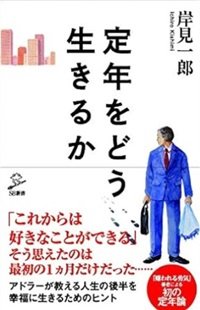








































コメントする