【書評】「石油の「埋蔵量」は誰が決めるのか? エネルギー情報学入門」岩瀬 昇
2016/02/15公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★★(90点)
要約と感想レビュー
エネルギーの安定確保が重要
三井物産でエネルギー関連事業に取り組んできた岩瀬さんが、ご経験をまとめた一冊です。大手商社だけあって、原油、天然ガス、石炭などエネルギーの見方はしっかりしている印象でした。エネルギー自給率4%の日本は、エネルギーの安定確保こそが重要ということです。石油・天然ガスの開発は、手がけてから生産に至るまで、数年から10年ほどかかるのですから、供給不足になってから手配してもすぐに供給できないのです。
現在の日本は、低廉で安定したエネルギー供給ではなく、原子力を停止して化石燃料を大量に輸入し、高価格の太陽光、風力を強制的に購入させて電力価格を上昇させているのですから、まったく逆の方向に進んでいるのが残念です。また電力の完全自由化により、燃料調達も目先の安さを優先して、スポット調達を増やしています。それまでの総括原価の時代には、長期的で安定した調達を優先していたころに比べれば、日本のエネルギー価格安定と調達の確実性は明らかに低下しているのです。
我々がエネルギー問題を考える場合、もっとも大事なのは一次エネルギーと呼ばれる石油、天然ガス、石炭、原子力、そして水力を含む再生エネルギーをどこから、どの程度の割合で長期的に確保するか、ということではなかろうか(p15)
日本はエネルギーを持っていない
興味深かったのは、なぜ、日本のLNGは原油リンクなのか?石油はコモデティなのか、戦略物資なのか?エネルギー政策をどう考えるのか?という本質的な疑問をテーマとして掲げているということです。日本はどういう国になりたいのか。そのために、長期的地球規模の視点に立ってどういう選択肢があるのか、考える必要があるのでしょう。
私は日本はエネルギーを持たない貿易立国であるとすれば、その地位を利用して安価で安定したエネルギーを手に入れるため、石炭、石油、LNG、原子力、水力といった多様なエネルギー源からバランス良く開発するしかないと考えます。仮にA国が中東シーレーンを封鎖したらどうするのか、原油やLNGの価格が倍になったらどうするのか、想定しておく必要があるのです。
ちなみに三井物産と三菱商事が関係したサハリン1では、日本向けパイプライン構想がありましたが、電力業界の反対により実現しなかったという。エクソンモービルは、日本に新たなパイプライン網を作れば、物流に便利度、自由度が増すと提案していましたが、ロシアのウクライナ侵攻を考えれば、電力業界のエネルギー源に対する保守的な姿勢が正しかったということなのでしょう。
シェルのシナリオ・プランニング・・・1973年の第一次オイルショックの到来を見通したと言われる伝説の手法だ・・ほぼ5年ごとに全世界の動向とエネルギー事情を対象として新しいシナリオ・プランニングを作成し、社内外に発表している(p227)
再生可能エネは不安定電源
最後に一つ。何度読んでも、原油の先渡取引による節税の仕組みは理解できませんでした。先渡取引は保険として使えますが、それを引き受けてくれる人がいるのか、いないのか、そこがポイントのはずです。もう少し勉強してみます。
不安定な再生可能エネルギーの大量導入についても、停電をおこさないために同容量の発電所を調整電源として用意しておく必要があることを指摘しており、電力供給の本質を理解していることがわかります。岩瀬さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・ガス価格を原油価格と比較するためには、ガス価格に「6」をかければ、熱量等価でほぼ正しい比較ができる。すなわち4~5ドル/100万Btuのガスは24~30ドル/バレルの原油に相当する(p33)
・一般的には90%以上の回収可能性がある場合を「確認埋蔵量」といい、50%以上の場合を「推定埋蔵量」、10%以上の場合を「予想埋蔵量」と呼ぶ(p89)
・埋蔵量に統一の定義はない・・・アメリカでは、既述のSEC基準と、世界石油工学技術者協会の定義が代表的だ。日本には日本工業規格というものがあり、・・・BP統計集に記載されている埋蔵量も、厳密に考えると疑問がない訳ではない(p96)
【私の評価】★★★★★(90点)
目次
第1章 日本の輸入ガスはなぜ高いか?
第2章 進化するシェール革命
第3章 「埋蔵量」のナゾ
第4章 戦略物資から商品へ
第5章 もう一度エネルギー問題を考える
第6章 日本のエネルギー政策
著者経歴
岩瀬昇(いわせ のぼる)・・・1948年生まれ。エネルギーアナリスト。浦和高校、東京大学法学部卒業。1971年三井物産入社、2002年三井石油開発に出向、2010年常務執行役員、2012年顧問、2014年6月退職。三井物産入社以来、香港、台北、二度のロンドン、ニューヨーク、テヘラン、バンコクでの延べ21年間にわかる海外勤務を含め、一貫してエネルギー関連業務に従事。現在は新興国・エネルギー関連の勉強会「金曜懇話会」世話人として、後進の育成、講演・執筆活動を続けている。
エネルギー資源関係書籍
「エネルギー(上・下)」黒木 亮
「石油の「埋蔵量」は誰が決めるのか? エネルギー情報学入門」岩瀬 昇
「エネルギー政策は国家なり」福島伸享
「資源論―メタル・石油埋蔵量の成長と枯渇」西山 孝
読んでいただきありがとうございました!
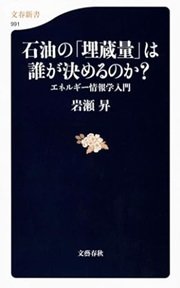




































コメントする