【書評】「国民は知らない「食料危機」と「財務省」の不適切な関係」鈴木 宣弘, 森永 卓郎
2025/08/08公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(74点)
要約と感想レビュー
食料輸入が止まると都会が飢える
1年前に、現在のコメ不足を予言していた一冊です。コメ不足となる理由は2つ。一つ目は、日本の農家の平均年齢が2022年の時点で68歳であること。二つ目はコメの需給調整、つまり減反政策が続いていることです。
著者の鈴木宣弘さんの不安は、外国の安い食料を輸入することで食料自給率が低いままの日本で、食料生産を減らす政策が実行し続けられていることなのです。もし、食料の輸入が止まったらどうするのだろうか。すぐに食料を増産しようとしても、簡単に増産できないのに、と不安は止まりません。
太平洋戦争のときには、都会の人は食うものがなくなって、田舎の農家に食料をわけてもらいに行っていました。そうしたことが起こりかねないという状況の中で、財務省と農林水産省は、減反政策を変えようとしないのです。
(今年、やっと転換するようです)
田んぼを潰せと言っているのは財務省だ・・・短絡的な発想しかない。米が余っているなら田んぼはやめろ、金がもったいないと、そういう意見しか言わない(鈴木宣弘)(p149)
食料の輸出は簡単に止まる
もちろん国も、食料の安定供給がやばいことはわかています。例えば、2022年5月、インドはウクライナ戦争の影響で小麦価格が上昇したことを理由に小麦の輸出を禁止しました。2023年インドはコメの輸出も禁止しているのです。
そこで国は、2025年4月に食料危機の恐れがある場合に、政府が農家に生産拡大を要請できる「食料供給困難事態対策法」を施行しました。しかし、そんなに簡単に作物の転換や増産などできるわけない!と著者の鈴木宣弘さんは訴えるのです。
インドは世界二位の小麦生産国ですが、ウクライナ戦争の影響で、小麦価格が上昇したことで、国内の安定供給のため小麦の輸出を禁止しました(鈴木宣弘)(p22)
ロシアの農園別荘が理想
森永卓郎さんの提案は、農産物を国内で生産・消費し自給率100%を目指すことです。さらに、「一億総農民」が理想としています。例えば、約1アール、30坪程度あれば家族で食べる分は充分作れるというのです。
実際、ロシアでは農園付きの別荘「ダーチャ」を持っている人が多く、経済危機の中でも、ロシア人は飢えることがないのです。
日本人が食料を自分で生産し、それを食べるようになれば、その分だけ、外国から小麦やトウモロコシの輸入を減らすことができるというわけです。
日本をなんとかするための第一歩として、「とりあえず、コメ食おうぜ!」と私は言いたい(森永卓郎)(p89)
他国と同じ農業保護が必要
日本ではニワトリのヒナはほぼ全量を輸入だし、エサとなるトウモロコシもほぼ100%が輸入です。日本はもともと、飼料穀物の輸入が多く、化学肥料もほぼ100%が輸入で日本の食料生産は構造的に弱いのです。
著者の鈴木宣弘さんの提案は、他国で農業保護として当たり前のコスト高による赤字の補填、政府が在庫を持ち、国内外の援助に活用するなどの政策です。グローバル化の中では、良い悪いは別にして、他国と同じ保護政策を行わないと同じ環境で競争できないことが問題なのでしょう。
農業や食料の話は重要だと思いますが、根拠なく再エネ関係の主張が出てきたり、マルクスの話が出てくるのが不快でした。農業の課題と対策を説明するのであれば、最後までその根拠を提示しながら、主張の正当性を訴えてほしいものです。
鈴木さん, 森永さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・私は「一億総農民・一億総戦闘員・一億総アーティスト」になるべきだと思います・・一部の人に戦闘を任せるより、全員が戦うほうが強い。だから全員がそのための訓練を受けるほうが本当はいい(森永卓郎)(p117)
・化学肥料と農薬の大量投入で、土壌の微生物が死んでしまっているから、畑の保水力が落ちているんです。だから渇水時にはどんどん水を撒かないと間に合わない(鈴木宣弘)(p47)
・大量の乳製品輸入・・・国内在庫が過剰であるにもかかわらず、海外からの莫大な輸入は続けている。「低関税で輸入すべき枠」を「最低輸入義務」と政府が意図的に解釈しており、異常事態が継続している(p142)
・私は2000年から2004年までテレビ朝日の「ニュースステーション」のコメンテーターを務めていました。そのときの総合プロデューサーは「自民党政権を倒すぞー!そのための番組を作るぞ!」と毎日言っていた(森永卓郎)(p112)
▼引用は、この本からです
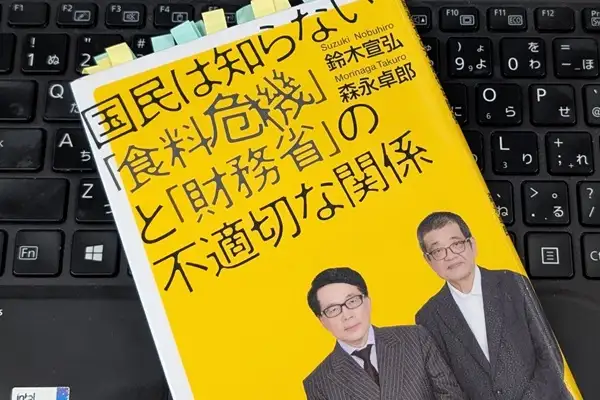
Amazon.co.jpで詳細を見る
鈴木 宣弘, 森永 卓郎 (著)、講談社
【私の評価】★★★☆☆(74点)
目次
第一章 世界経済はあと数年で崩壊する
第二章 絶対に知ってはいけない「農政の闇」
第三章 アメリカの「日本搾取」に加担する財務省
第四章 最後に生き残るためにすべきこと 鈴木宣弘
著者経歴
鈴木 宣弘(すずき のぶひろ)・・・東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授。「食料安全保障推進財団」理事長。1958年生まれ。三重県志摩市出身。東京大学農学部卒。農林水産省に15年ほど勤務した後、学界へ転じる。九州大学農学部助教授、九州大学農学研究員教授などを経て、2006年9月から東京大学大学院農学生命科学研究科教授、2024年4月から同特任教授。
森永 卓郎(もりなが たくろう)・・・経済アナリスト。獨協大学経済学部教授。1957年、東京都生まれ。1980年、東京大学経済学部卒。日本専売公社(現在のJT)に入社し「管理調整本部主計課」に配属
農業関連書籍
「日本一の農業県はどこか:農業の通信簿」山口亮子
「国民は知らない「食料危機」と「財務省」の不適切な関係」鈴木 宣弘, 森永 卓郎
「バターが買えない不都合な真実」山下 一仁
「農家はもっと減っていい 農業の「常識」はウソだらけ」久松 達央
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!

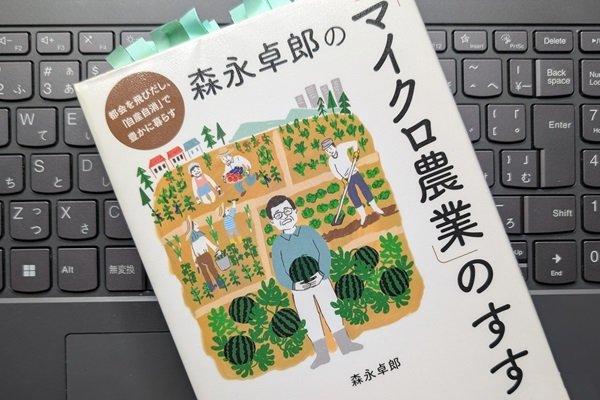
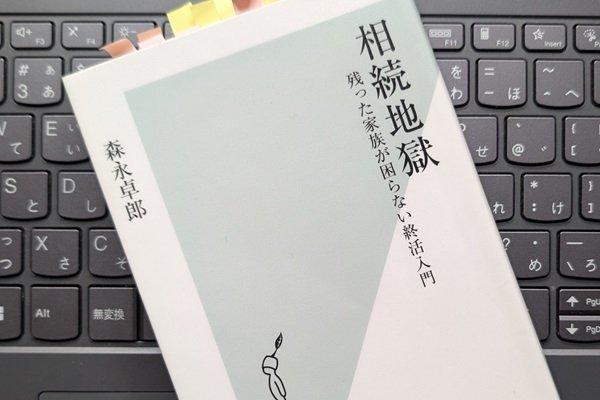
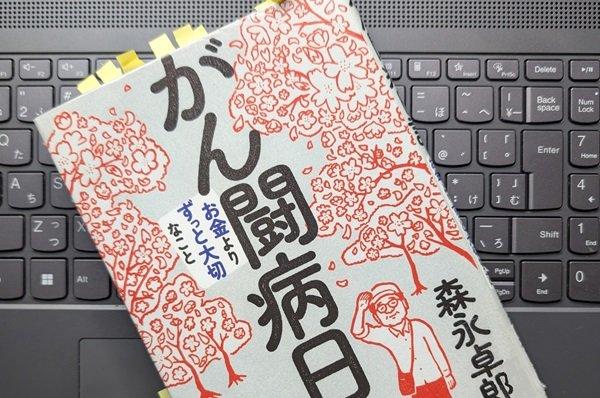
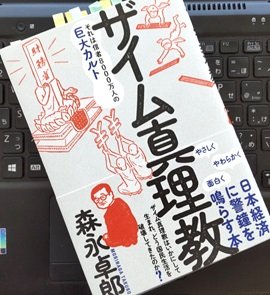
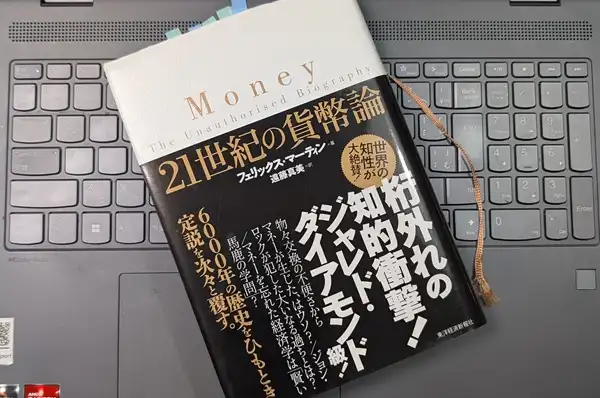
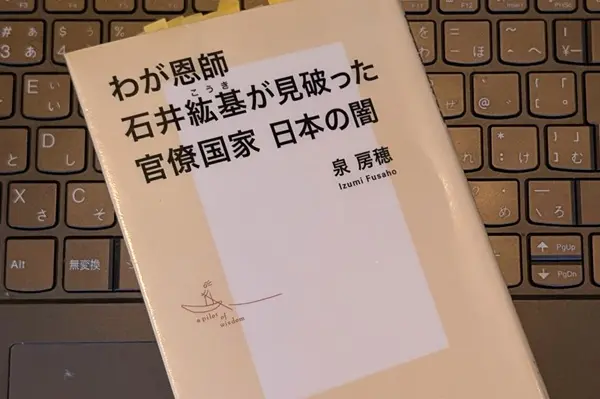
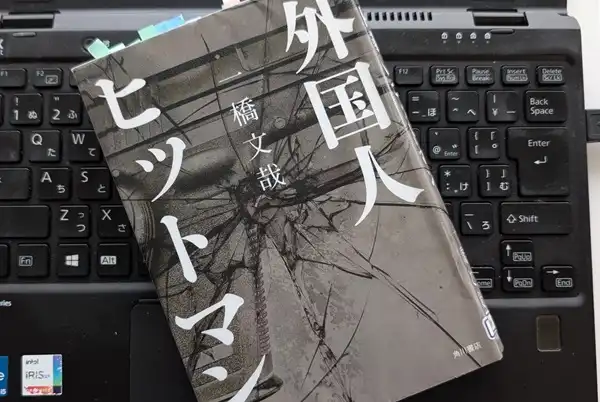
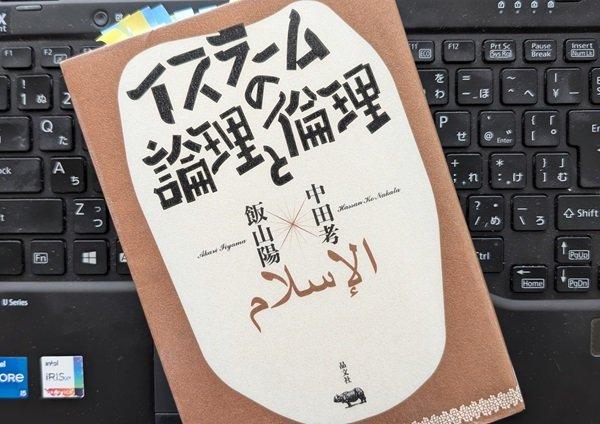
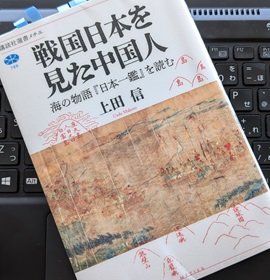
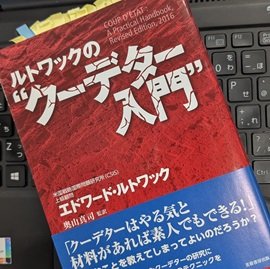
























コメントする