【書評】「バターが買えない不都合な真実」山下 一仁
2018/11/08公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(85点)
要約と感想レビュー
バターが不足する理由
元農林水産省の官僚による日本農政の不都合な真実の解説書です。この本では農業について、いくつかの質問が出てきます。
なぜ、バターが不足するのか。なぜ、農協は高い米価を望んだのか?なぜ、配合飼料は輸入とうもろこしの3倍なのか?実は、とうもろこしの輸入価格(CIF)に対し、とうもろこし小売価格は2倍、配合飼料価格は3倍だというのです。
まず、バターが不足する理由は、生乳からバターと脱脂粉乳が1対1の比率で生産される特性に原因があります。バターの需要が変わらないなかで、脱脂粉乳の需要が減ってきたため、脱脂粉乳の需要減に合わせてバターの生産量を減らしているのです。
仮に、バターの需要に合わせると、脱脂粉乳だけが余ることとなり、脱脂粉乳から安い還元乳が作られ、牛乳の価格が暴落する恐れがあるので、それは避けたい。
では、バターを輸入すれば良いのではないかと考えてみると、バターは高関税で輸入が事実上禁止されており、輸入するにしても国の畜産産業振興機構alicが独占的に輸入しており、高価格維持のために最小限の量しか輸入しないのです。
日本農政の特徴は高い価格で農業を保護してきたことである・・高い価格での保護は消費者を苦しめるだけではなく、農業自体の国際競争力を奪ってきた(p235)
農協が高い米価を望む理由
次に、農協が高い米価を望む理由は、価格に比例して販売手数料収入があること、そして農薬、肥料、飼料などを高い値段で農家に売ることができるからです。農協の圧力によって高価格が維持されるので、農家は農協から高い農薬、肥料、飼料を文句も言わずに買ってくれるのです。
農協にとっても農家にとっても短期的には素晴らしい仕組みでしたが、高価格により米の消費量は減少し、政府は減反政策を推進することになるとともに、農家の創意工夫する必要も感じないままに日本の米農業は衰退することになったのです。
つまり、農水省は短期的視点の農協の圧力に負けて、生産者米価を上げて消費者米価も上げたのです。長期的な視点で言えば、政府介入により市場の価格を高く設定したことによって、消費を減少させ、辻褄合わせの減反政策が、日本農業を縮小・弱体化させてしまったというわけです。
米価は高いままなので、コストの高い零細な兼業農家も農業を継続しています。農家の7割が米農家ですが、農業生産額の2割しか生産しておらす、こうした零細な兼業農家を主に相手にするJA農協の農業部門は赤字となっています。零細農家1軒、1軒に肥料一袋を届けるのは効率が悪いのです。
なぜ、わざわざ米農業を衰退させるような愚かな政策を、日本の農業界はとってしまったのだろうか?・・・なぜ、JA農協は高い価格を望んだのか?農協の販売手数料は、価格に応じて、または比例して、決まる・・肥料などの農業資材を農家に高く販売する(p148)
飼料が輸入とうもろこしの3倍である理由
配合飼料が輸入とうもろこしの3倍である理由についての記載はありませんが、だいたい推察できます。小麦の場合には、輸入小麦はキログラム当たり35円ですが、これに農林水産省が関税のような輸入課徴金22円を課して、57円として製粉会社に売り渡しているからです。
著者としては、アメリカ・EUのように関税をなくして農家に一定の収入を保証し、国際市場価格での取引とする政策を推奨しています。アメリカやEUのような直接支払いに転換すれば、輸入食料を含めて、消費者の負担は大幅に軽減されるのです。
さらに、最も市場への介入度合いが小さいのは、生産しようがしまいが、農家に一定額の所得補償を支払うというやり方があるという。これは生産や価格と切り離されているという意味で、"デカップリング"と呼ばれ、アメリカは1996年に不足払いも生産調整もやめてデカップリングに移行し、EUの直接支払いも2003年にデカップリングに移行しているという。
そしてなぜ、日本が諸外国のようにそうした政策変更できないのか、その理由もだいたい推察できます。若干文章が分かりにくかったので、星4つとしました。山下さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・酪農だけではない。牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵など、他の畜産では、ほとんど100%エサをアメリカに依存している。畜産物はエサの加工品と言ってよい(p52)
・農業政策の関与が少ない、野菜、果樹、花、鶏卵、鶏肉については、自立している農家が多い。ところが、米を筆頭に、麦やサトウキビなどの畑作物、酪農、牛肉、養豚など、これまで保護されてきた農家については・・なかなな自立できない(p111)
・稲作などでは、中規模の専業農家よりも、小さい兼業農家の方がサラリーマン収入があるので、豊かなのである。小農はもはや貧農ではない(p112)
・農家出身者でない若者が、親兄弟、友人に出資してもらい、ベンチャー株式会社を作って、農地を取得しようとしても、農地法が認めない(p216)
・貿易を自由化すると、農業に影響が出るので生産性向上を図る必要があるとして、予算処置を講じて、農林水産省OBのいる団体へ、国からお金を出す。しかし、生産性は向上しない・・というより、生産性が上がらない方が予算を毎年確保できて都合が良いのだ(p117)
・会計検査院は、事業費に対する事務費の割合を調査している。事務費の中で特に大きいものは、人件費、つまり職員の給料である。60の基金のうち、12の基金で事業費の半分以上に相当する額を事務費に当てていた。さらに、10の基金が、事業費がゼロで事務費だけを支出していたという・・私が課長補佐として畜産局の予算を担当していた頃、農林水産省OBの元畜産局長から、もっと基金を作ってくれという要請を受けたことを思い出す(p228)
幻冬舎 (2016-03-30)
売り上げランキング: 338,020
【私の評価】★★★★☆(85点)
目次
第1章 消えたバターについての酪農村の主張
第2章 日本の酪農とアメリカの切れない関係
第3章 牛乳・乳製品は不思議な食品
第4章 複雑な酪農事情と政策の歴史
第5章 乳製品の輸入制度はこうしてできあがった
第6章 さあ、謎解きです―バターが消えた本当の理由
第7章 日本の酪農に明日はあるか?
著者経歴
山下 一仁(やました かずひと)・・・キヤノングローバル戦略研究所研究主幹。経済産業研究所上席研究員。1955年岡山県生まれ。東京大学法学部卒業。同博士(農学)。1977年農水省入省。同省ガット室長、農村振興局次長などを経て、2008年より経済産業研究所上席研究員。2010年よりキヤノングローバル戦略研究所研究主幹。
農業関連書籍
「バターが買えない不都合な真実」山下 一仁
「農家はもっと減っていい 農業の「常識」はウソだらけ」久松 達央
「誰が農業を殺すのか」窪田新之助, 山口亮子
この記事が参考になったと思った方は、
クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓ ![]()
![]()



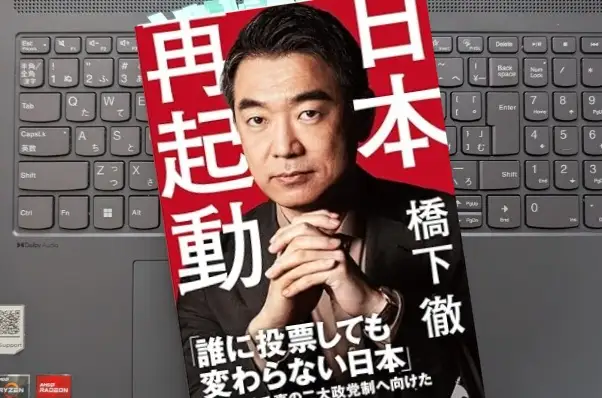































コメントする