【書評】「ざっくばらん」本田宗一郎
2002/09/29公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(86点)
要約と感想レビュー
職人と技術屋の違い
では、職人と技術屋の違いはどこにあるのだろうか。それは、学校を出た出ないじゃなくて、一つのものがあると、過去を大事にして、そればっかりにつかまっている人が職人だ。同じ過去でも、それに新しい理論を積み重ねて、日々前進するのが技術屋だ
お役所仕事のズサンなこと
ホンダも昔は小さな工場、いや本田宗一郎という人がいるだけでした。その本田宗一郎の持つ考え方、ビジョンが世界の本田を作ったのです。そのことがよく分かる一冊です。昭和35年の本ですが、今でも全く古さを感じさせません。
1960年にスピード制限についてお役所仕事の例としてあげているのは、さすがだと思います。60年経ってやっと高速道路の最高速が120キロに上がろうとしているのですから、お役所仕事は素晴らしい。
お役所仕事のズサンなことをあげると、スピード制限のことである。信州の田んぼの真ん中の一本道も40キロで、箱根のカーブまたカーブといった道も同じ40キロ・・・スピードアップできるいい道は、それにふさわしく制限を緩和すべきである(p226)
工作機械を4億円買って潰れかける
また、ホンダの資本金は600万円の中小企業だったとき、借金をして欧米の工作機械を4億円も買ったという逸話があります。
当時のことを振り返って、宗一郎は、「機械を買えばつぶれるかも知れないが、買わなくてもジリ貧でやがてはつぶれる。しかし機械を買っておけば、つぶれるかも知れないが、伸びるときには伸びるだろうという希望がある。それならばやはり買うべきだ」と考えたという。
今後、本田宗一郎という人間をもっと研究していきます。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・本を読むんだったら、そのヒマに人に聞くことにしている。500ページの本を読んでも、必要なのは1ページくらいだ。それを探し出すような非能率なことはしない(p9)
・人間は80%ぐらいは遊びたいという欲望があって、それがあるために一生懸命働いているのではないだろうか。それを働け働けといってヤミクモに尻を叩いても能率が上がるわけはない(p141)
【私の評価】★★★★☆(86点)
目次
技術とは
汗と創意
個と全体
小僧時代
日に新た
細心なれ
国民性論
新デザイン学
美と個性
島国根性
政治と技術
ネオ能率論
真理に徹す
浅間雑感
カミナリ論
欧州断想
軽四輪考
文化人論
性能と価格
看板と中味
逆立ちと役人
保護と自立
著者経歴
本田宗一郎[ホンダソウイチロウ]・・・1906年(明治39年)、静岡県に生まれる。小学校卒業後、アート商会(東京・自動車修理工場)に入社。28年、のれん分けして浜松アート商会を設立。自動車修理工として成功するが飽きたらず、東海精機重工業(株)を設立しピストンリングの製造を行なう。46年、本田技術研究所、48年、本田技研工業(株)を設立。オートバイ『ドリーム』『スーパーカブ』などを次々に開発。59年、英国マン島TTレースに初参加。61年、マン島TTレースで1~5位を独占して完全優勝する。62年、四輪車に進出。64年、F1GPに挑戦。65年、F1メキシコGPで初優勝。72年、低公害のCVCCエンジン発表。アメリカの排ガス規制法であるマスキー法規制に、世界で初めて合格する。73年、社長を退任、取締役最高顧問となる。89年、日本人として初めてアメリカの自動車殿堂(AHF)入り。91年、84歳で逝去
読んでいただきありがとうございました!
この記事が参考になった方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
人気ブログランキングに投票する

![]()
| メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」 44,000名が読んでいる定番書評メルマガです。購読して読書好きになった人が続出中。 >>バックナンバー |
| 配信には『まぐまぐ』を使用しております。 |
お気に入りに追加|本のソムリエ公式サイト|発行者の日記
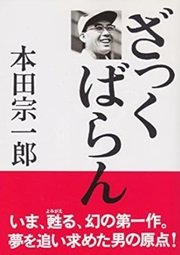









































コメントする