【書評】「死ぬ瞬間 死とその過程について」エリザベス・キューブラー・ロス
2025/04/03公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(85点)
要約と感想レビュー
末期患者インタビューの目的
著者はシカゴ大学ビリングズ病院で、末期患者へのインタビューを行い、その内容について学生と討論するといセミナーをはじめました。このインタビューの目的は、患者を一人の人間として見直し、患者との会話を通じて病院の患者管理の長所と欠点を患者から学ぶことでした。
1965年当時、病院の医師やスタッフはセミナーに強い拒否反応を示し、末期患者へのインタビューを担当医にお願いしたとしても許可してもらえることは少なかったという。それでもインタビューの実績を増やしていく中で、末期患者がどう思い、何に怒り、どう変化していくのか見えてきたのです。
本書を書くまでに200人以上にインタビューを行い、その結果、末期患者が、否認と孤立→怒り→取り引き→抑鬱→受容と変化していくことが観察されました。そして学生との討論によって、死を自分にも起こりうるものと考えるようになること、死に対するアレルギーが軽減するという効果が学生にあったという。
死期の近い患者には、この世との永遠の別れのために心の準備をしなくてはならないという深い苦悩がある(p147)
末期患者インタビューの方法
インタビューの方法は、インタビュー室に患者と聴き取りを行う著者たちが入ります。そのインタビュー室にはマジックミラーが設置されており、学生がインタビューの様子を見て聞くことができるようになっているのです。
患者は事前に、このインタビューの目的を再説明され、そしてインタビューでは、やめたくなったらいつでも止めてもよいこと、マジックミラーの裏に学生がいることを再度説明されるという。そしてインタビューが終わると、患者を病室へ送り届けた後で全員で討論を行うという流れで進むのです。
患者200人以上にインタビューしたが、ほとんどの人は不治の病であることを知ったとき、はじめは「いや、私のことじゃない。そんなことがあるはずがない」と思ったという(p68)
どのように告知するべきなのか
インタビューの目的にあるとおり、当時の米国では末期患者への対応は、統一したものがなかったようです。患者が休息と安らぎがほしいとしても、延命のために、点滴や輸血を受け、必要があれば、人工心臓や気管切開まで延命処置が行われてしまうのです。
また、末期患者に告知するかどうかは担当医の判断に任されており、告知する医師、告知しない医師がいたという。
インタビューでわかったことは、患者は休息と安らぎを求めているということ。そして、告知されなくても、いずれは死期が近いことに気づくのです。そして、自分に嘘をついた医師を信頼しなくなるという。したがって、著者は患者の望む死の迎え方を尊重すること。そして、そのためにも告知するべきか告知しないべきかではなく、どのように告知するのか明確にすべきと提言しています。
今では日本でも告知が当たり前になっていますが、米国でも1960年代は告知に悩んでいたことがわかります。
どれだけ生きられるかはだれにもわからないと率直に言うべきだ。あと何か月とか何年とか具体的な数字を示すのは・・そうした数字はいずれにせよ正確ではなく、長すぎるか短すぎるのが常である(p55)
ホスピスや緩和ケアは私たちの問題
インタビューでは、眠れない患者が、医師の処方を厳密に守ろうとする看護師を批判しています。患者を麻薬中毒にしたくないのは当然ですが、そもそも末期患者はそんなに生きられないということです。麻薬を使えば痛みがやわらいで、何かを楽しんだり、人間らしい時間がもてるというわけです。
日本でも緩和ケアが普及していると思いますが、患者ファーストの対応が必要なのでしょう。
米国でも強い医師の抵抗の中で、こうした患者を一人の人間として扱おうという取り組みにより、ホスピスや緩和ケアの取り組みが強化されてきたことがわかりました。人間はいずれは死にますので、死期が近づいたときにどうあるべきなのかは、私たちの問題として考えるべきなのです。
キューブラー・ロスさん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・対処療法がおこなわれることにより、患者の多くは「延命」するかもしれない。だが死を先延ばしにしても、患者からは感謝の言葉より恨み言を聞くことが多い(p288)
・もし患者が、慣れ親しんだ最愛の家で最期を迎えられるならば・・家族は彼のことをよく知っているから、鎮痛剤の代わりに好きなワインを一杯与えるだろう。自家製スープの香りが食欲をそそり、・・点滴よりずっとうれしいのではないだろうか(p21)
・否認と孤立・・彼女が自殺することも精神病になることもなく自分の死を受け入れるまでには、何週間いや何か月も、静かな触れ合いを続ける必要があった(p83)
・受容・・患者はある程度の期待をもって、最期の時が近づくのを静観するようになる・・患者は疲れきり、たいてはい衰弱がひどくなっている。まどろんだり、頻繁に短い眠りを取りたくなる(p192)
▼引用は、この本からです
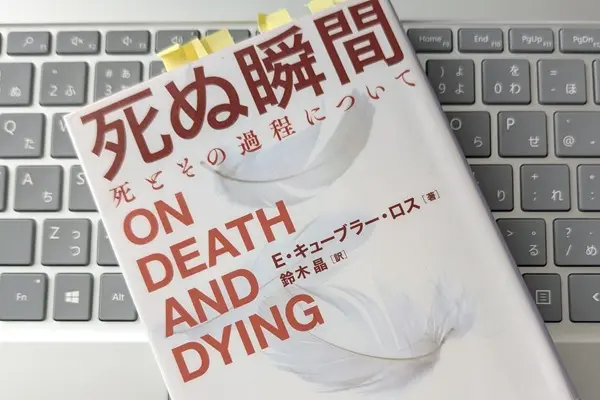
Amazon.co.jpで詳細を見る
エリザベス・キューブラー・ロス、中央公論新社
【私の評価】★★★★☆(85点)
目次
死の恐怖について
死とその過程に対するさまざまな姿勢
第一段階/否認と孤立
第二段階/怒り
第三段階/取り引き
第四段階/抑鬱
第五段階/受容
希望
患者の家族
末期患者へのインタビュー
死とその過程に関するセミナーへの反応
末期患者の精神療法
著者経歴
エリザベス・キューブラー・ロス(Elisabeth Kübler-Ross)・・・精神科医。1926年、スイスのチューリヒに生まれる。チューリヒ大学に学び、1957年学位取得。その後渡米し、ニューヨークのマンハッタン州立病院、コロラド大学病院などをへて、1965年シカゴ大学ビリングズ病院で「死とその過程」に関するセミナーをはじめる。1969年、『死ぬ瞬間』を出版して国際的に有名になる。著書多数。2004年、死去。
死ぬ瞬間関連書籍
「死ぬ瞬間 死とその過程について」エリザベス・キューブラー・ロス
「もしも一年後、この世にいないとしたら。」清水研
「もしあと1年で人生が終わるとしたら」小澤竹俊
「死ぬ瞬間の5つの後悔」ブロニー ウェア
「人生で学んだ一番大切なこと」ウェンディ・ラストベーダー
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!

































コメントする