【書評】「言語の本質-ことばはどう生まれ、進化したか」今井 むつみ、秋田 喜美
2025/04/02公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(75点)
要約と感想レビュー
オノマトペが言語学習の第一歩
「新書大賞2024」第1位とのことで、手にした一冊です。この本では、ヒトはどうやって言語を習得するのか、検証しています。まず、最初に注目するのは、オノマトペです。オノマトペとは、「カクカク」「ギザギザ」「ニャー」「ザラザラ」「ウネウネ」「ドキドキ」といった擬音語や擬態語です。
赤ちゃんがオノマトペをよく使うので、オノマトペが言語学習の第一歩と考えているのです。実際、オノマトペを使ったときの脳の活動を測定すると、左右半球どちらも活動するが、相対的に右半球の活動が顕著だという。言語の処理は左半球側、環境音の処理は右半球側で処理するので、オノマトペは言語でも環境音でもあるということなのです。
つまり、当たり前のことに感じますが、オノマトペは非言語の音を言語とむすびつけるものなのです。
オノマトペはきわめて言語的である(p52)
言語はアナログからデジタルへ
言語の発達の例として、ニカラグア手話を紹介しています。もともとニカラグアには手話がなく、家庭内でしか通用しないホームサインが使われていたという。しかし1980年代に特別支援教育センターが開設され、耳が聞こえない子どもたちが学校に集められ、「学校手話」が生まれたのです。この「学校手話」を使う人の人口が増え、今では「ニカラグア手話」として、国際的に公式の手話言語として認定されているのです。
ニカラグア手話は、最初は動作をジェスチャーで示すアナログ的なものであったという。そして大きな塊の意味単位から、だんだんと細かい要素の意味単位に分割し、再結合されていったのです。例えば、最初は「転がりながら坂を落ちる」という表現は、転がる動作と、下へ落ちる動作に分けて、組み合わせで表現するようになりました。
動作をアナログ的に表現していたものが、だんだんと細分化され、細かい意味単位から構成されるデジタル的な表現に変わって、言語として体系が作られていったのです。
ニカラグア手話の始まりから数世代の変化・・第一世代はアナログ的に表現していた・・アナログ的な連続性から離れてデジタル性を深め、普遍的な「言語」に成長していく(p140)
ヒトは感覚に接地しながら言語を学ぶ
ニカラグア手話のように、言語はオノマトペのようなアナログ的なものから、細分化されデジタル的な表現に発展していったのは明らかでしょう。
専門的には、母語の言語は「感覚に接地」しており、接地した言語が習得できていれば、まったく意味のわからない言語は「感覚に接地」していないと表現するらしい。ヒトは感覚に接地しながら、言語を学んでいくのです。当たり前のような結論に、「新書大賞2024」第1位の理由がよくわからなくなりました。
今井さん、秋田さん良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・原住民が野原を跳びはねていくウサギのほうを指差して、「ガヴァガーイ」と叫んだ。「ガヴァガーイ」の意味は何か?・・・ことばを学習する子どもたちがつねに直面する問題である(p110)
・(英語やロシア語のような)衛星枠づけ言語では・・・動詞本体にはplod(トボトボと歩く)、scurry(大慌てで走る)、limp(片足を引きずって歩く)のように動きの様態情報が含まれる傾向にある(p160)
・「とがる」「かくばる」「カクカク」「ギザギザ」なども「硬い言葉」と言える。「なめらか」「なだらか」「ゆるやか」などは「柔らかいことば」である(p30)
▼引用は、この本からです
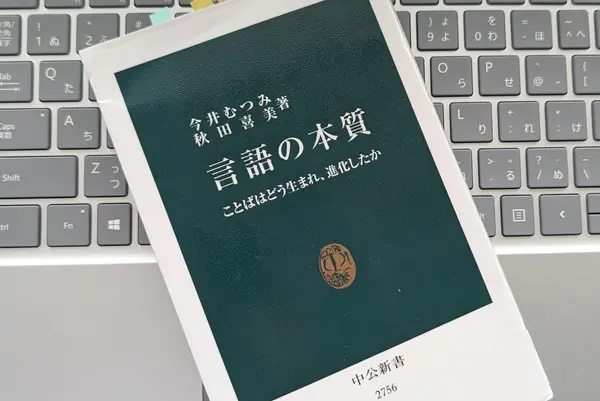
Amazon.co.jpで詳細を見る
今井 むつみ (著), 秋田 喜美 (著)、中央公論新社
【私の評価】★★★☆☆(75点)
目次
第1章 オノマトペとは何か
第2章 アイコン性―形式と意味の類似性
第3章 オノマトペは言語か
第4章 子どもの言語習得1―オノマトペ篇
第5章 言語の進化
第6章 子どもの言語習得2―アブダクション推論篇
第7章 ヒトと動物を分かつもの―推論と思考バイアス
終 章 言語の本質
著者経歴
今井むつみ(いまい むつみ)・・・1989年慶應義塾大学大学院博士課程単位取得退学.1994 年ノースウェスタン大学心理学部Ph.D.取得.専門,認知科学,言語心理学,発達心理学
秋田喜美(あきた きみ)・・・2009年神戸大学大学院文化学研究科修了.博士(学術)取得.大阪大学大学院言語文化研究科講師を経て,名古屋大学大学院人文学研究科准教授.専門は認知・心理言語学
新書大賞関連書籍
2025年「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」三宅 香帆
2024年「言語の本質-ことばはどう生まれ、進化したか」今井 むつみ
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!


































≪…動作をアナログ的に表現していたものが、だんだんと細分化され、細かい意味単位から構成されるデジタル的な表現に変わって、言語として体系が作られていった…≫で、数の言葉ヒフミヨ(1234)の自然数の眺めは『コンコン物語』になるようだ。