【書評】「再生可能エネルギーの真実」山家公雄
2020/01/12公開 更新
Tweet
【私の評価】★★☆☆☆(62点)
要約と感想レビュー
著者は再エネ推進論者
著者は日本開発銀行、日本政策投資銀行を歴任し、再エネ推進論者です。再エネ固定化価格買取制度により不安定電源である太陽光、風力がどんどん増設されていますです。家庭用電気料金が28円、事業用が10円強なのに、再エネは40円、30円などという高額で購入し、消費者が負担するという仕組みなのです。
ヨーロッパでは不安定電源のために系統が不安定になり、送電線も不足。さらには電気料金が2倍にもなっているという。例えばドイツでは太陽光の大量導入は、財政負担や電気料金上昇負担が重すぎると問題になっています。再エネ助成の6割は太陽光が占めるが、電力に占める割合は5%に過ぎないのです。
このように太陽光発電はコストが高く社会負担が重いため、買い取り制度を止める国が増えています。ただ、常に世界のどこかで再エネ買い取り制度ができると大きな需要が生じて、全体としてはまだ伸びているだけなのです。そうした事実にもかかわらず、著者はそうした批判は目先の現象だけを見ているからだと現実を直視することを避けています。私にはあまり論理的には思えませんでした。
再エネ普及初期段階において、バッシングともいえるような太陽光批判は、分からないではないが、再エネ全体を俯瞰することなく目先の現象のみを追って議論しているように見える(p361)
水力発電は投資回収の期間が長すぎるのか
自分こそが再エネの本質に目を向け、CO2を発生しない再エネが素晴らしいと、手をたたくだけなのです。あと10年もすれば電気料金がヨーロッパのように1.5倍、2倍となり筆者は「こんなはずではなかった」などというのでしょうか。
一方で著者は水力発電について、初期投資が高く、投資回収の期間が長すぎるとしています。水利権や環境アセスの調整などに地元調整を要し、土木工事にも時間がかかると事実を述べるのみでした。私は20年後に大量の廃棄物を生む太陽光発電よりも、100年後も安定した電気を発電し続ける水力発電こそ、再生可能エネルギーのエースだと思っています。しかし、著者は水力発電の投資回収期間の長さという問題点を指摘するのみなのです。
表面的な一冊でした。良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・固定価格買い取り制度(FIT)の買い取り条件については、風力業界は、大規模・陸上施設で、期間は20年、価格は22~25円程度を要望し、22円で決着した(p38)
・温度差発電は・・・発電コストは、設備利用率90%を前提に1MWでkWh当たり50円、10MWで20円、100MWで10円と試算されている(p108)
・昔は、山持ちは資産家であったが、次第に山はお荷物になってきている。スギ人工林の造成・育成費用は、50年間でヘクタール当たり231万円かかるが、2009年時点の価格で販売した場合91万円にしかならない(p257)
【私の評価】★★☆☆☆(62点)
目次
第1章 風力発電
第2章 海洋エネルギー
第3章 太陽光発電
第4章 地熱発電とバイナリー
第5章 中小水力
第6章 バイオマスと1次産業1―木質バイオマスと林業
第7章 バイオマスと1次産業2―バイオマスの主役、輸送用バイオ燃料
第8章 再エネ政策を考えるヒント
著者経歴
山家公雄(やまか・きみお)・・・1956年生まれ。東京大学経済学部卒業後、日本開発銀行(現日本政策投資銀行)入行。2009年からエネルギー戦略研究所株式会社 取締役研究所長。
再生可能エネルギー関係書籍
「フクシマのあとさき―複眼的エネルギー論」山地 憲治
「再生可能エネルギーの真実」山家公雄子
「「エネルギー・シフト」再生可能エネルギー主力電源化への道」橘川 武郎
この記事が参考になったと思った方は、
クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓ ![]()
| メルマガ[1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』] 3万人が読んでいる定番書評メルマガです。 >>バックナンバー |
| |
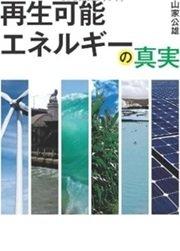


































コメントする