【書評】「外務省は 「伏魔殿」か: 反骨の外交官人生と憂国覚書」飯村 豊
2025/09/05公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(71点)
要約と感想レビュー
田中眞紀子外務大臣と飯村豊氏の対立
NHKスペシャル「シミュレーション~昭和16年夏の敗戦~」で祖父の人格を毀損されたと元駐仏大使の飯村豊氏が抗議したということで、手にした一冊です。
著者の飯村豊氏は、第1次小泉純一郎内閣のとき、外務省官房長として田中眞紀子外務大臣と対立。降格されることになります。この本の前半は、田中眞紀子外務大臣に外務省がどう対応したかの記録となっています。
当時は、外務省の松尾克俊が官房機密費をプールして、うち7億円を流用して私的な競走馬やゴルフ会員権を購入していたことが発覚。外務省で機密費をプールしていたことが、表に出てしまったのです。そこに田中眞紀子氏が、外務大臣に任命されたのですから、混乱は必至です。
田中眞紀子外務大臣は、外務省の人事を凍結します。その中に、小寺ロシア課長の更迭人事も含まれていました。著者の説明によれば、北方領土二島先行で交渉していた東郷欧亜局長と鈴木宗男衆議院議員に小寺ロシア課長が抵抗して、実質的に更迭されたのです。田中眞紀子外務大臣は、それを良しとしなかったのです。
外務省の幹部が松尾克俊氏にたかっていた・・・のちに外務省のトップに上り詰めた人のなかに松尾氏の麻雀仲間がおり,この人に松尾氏が甘やかされていたことは有名でした(p39)
田中眞紀子外務大臣の問題点
著者が田中眞紀子外務大臣を批判しているのは、アーミテージ国務副長官との面談をドタキャンしたこと。これは、アメリカとの良好な関係に悪影響があるということでしょう。
また、田中眞紀子外務大臣が中国の外交部長との電話会談で、歴史教科書や台湾に関する問題発言を行ったこと。これは、田中眞紀子外務大臣が中国寄りであり、日本のスタンスの一貫性が崩れることを危惧しているのでしょう。
北朝鮮の金正日総書記の長男・金正男氏が入国したとき、事務方の意見を無視して田中眞紀子外務大臣が帰国させたこと。これも、田中眞紀子外務大臣が中国寄りと考えればあり得ることです。
そして最も著者が批判しているのは、人事や会計などに田中大臣が手を突っ込んできたことです。これは、事務次官,官房長,総務課長,人事課長,会計課長の「官房ライン」が重大な危機感を持っていたという。
このように、世論とメディアに支持された田中眞紀子氏が外務大臣となり、やりたい放題するのは、過去の敗戦の原因となった満州事変を支持したメディアと世論の暴走と同じポピュリズム・人気取りだと、著者は批判するのです。
そして、冷静で長期的な判断に基づく外交を、外交官は信念を持って貫くべきと主張しています。つまり、外務大臣の主張を信念を持って否定するということであり、著者はすごい信念を持っているのです。
冷静に読むと、国益というよりは外務省の人事に口出しする田中眞紀子外務大臣を外務省官房ラインとしては信念を持って退任させなくてはならなかったと主張しているように見えました。
マスメディアが本来世論を啓発すべき立場にありながら,時流に流され,日本の国自体を悲劇に導いた一因となった・・・大半の主要紙が満州事変を支持し,また満州事変に関する国際連盟のリットン報告書を批判しました(p69)
外務省の田中眞紀子外務大臣対策
田中眞紀子外務大臣に対して外務省幹部は,田中大臣と融和するグループ,抵抗を試みるグループ,そして傍観する多数派の3派に分裂したという。
外務省の官房ラインとしての田中眞紀子外務大臣の暴走対策は、外務大臣自身に直言できる人物を次の外務省事務次官にすることです。結果、野上義二氏が外務省事務次官となりました。
同時に官房長であった著者は、抵抗勢力として官房付きに降格となりました。著者は抗議の意味で辞令交付式を欠席したという。
外部への田中眞紀子外務大臣暴走対策は、鈴木宗男議員に田中大臣の問題行動を報告して、攻撃してもらうこと。実際、鈴木宗男議員が衆議院外務委員会で田中大臣を厳しく問い詰めています。
また、自民党の元外務大臣である高村正彦氏、河野太郎氏に随時、田中外務大臣の問題を報告しています。二人はいつも励ましてくれたという。
田中大臣が外交会談で問題発言したことを記録した公電を、プレスにリークすること。これは「機密を漏洩した」として国会で問題になりました。
結果してNGO参加拒否問題が持ち上がったタイミングで、小泉純一郎首相は田中真紀子外相と野上義二外務事務次官を更迭することになるのです。
8月10日,新旧次官の交代と官房長更迭の辞令が出され,私は官房付きになりました・・・私はこのような屈辱的な行為をやることはできず,辞令交付式には出ませんでした(p61)
外務省は「伏魔殿」
その後、ロシアとの交渉を進めていた鈴木宗男議員も外務省から排除され、結果して、欧米派が生き残ったということになるのです。安倍晋三氏があまり出てこないのは、意図的なのか偶然なのか、少し残念でした。
ただ、「自由で開かれたインド太平洋戦略」については、ASEAN諸国が中国に敵対的な動きとして神経質になっているとして前向きではないようです。また、「自由で開かれた」という民主主義と市場経済の価値観では、一部の発展途上国が賛同しないので、国際法を守る,軍事力により国際社会の現状を一方的に変更させないことを基本的な目的とするべきと主張しています。
つまり、著者は安倍晋三氏の「自由で開かれたインド太平洋戦略」に前向きではないようです。
全体的に、外務省関係者に向けて自分は省益を守るためにこれだけやった!とPRしているように感じました。外務省の内部で、権力闘争があることは明らかで、そういう意味で外務省は「伏魔殿」なのでしょう。
この事件で、官僚の人事や会計などに手を突っ込むとどうなるか、多くの人が学びました。官僚の思考と力を再確認できました。飯村さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・田中大臣の外遊中の会談での発言記録のうち不都合な部分が修正されて公電となり,本省に送られる事例もありました(p56)
・外交は長期的な国益を図る戦略と冷静な判断に基づいて行うべきです・・最近政治家が世論に乗っかるために外交を人気取りに使っているようなところも見られますので,そういう点が心配です(p63)
・不安定な国際環境において独立国家としての地位を維持しつつ小国として生きていくには厳しいリアリズムが要求されます。幻想に取り憑かれやすい日本人にできるでしょうか(p259)
・軍事力に負荷をかけ過ぎた安全保障政策は国の安全を守ることにならないということです。軍事力,経済力,科学技術力,ソフトパワーなど国の総合的な力を動員し,志を同じくする国々と共に連携して,国際社会の平和を脅かす現状変更勢力の野心を抑止しうる「力の均衡」を作り上げること(p274)
▼引用は、この本からです
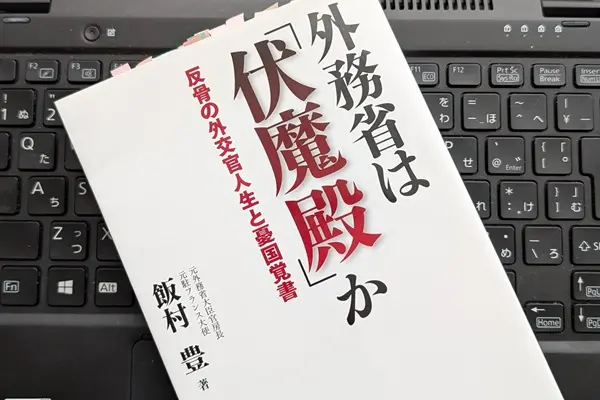
Amazon.co.jpで詳細を見る
飯村 豊 (著)、 芙蓉書房出版
【私の評価】★★★☆☆(71点)
目次
プロローグ 「国賊」と呼ばれた家庭から外交官へ
第1章 「外交と世論の関係」は永遠の課題
第2章 相互批判と協力が交錯する日米欧関係
第3章 体験して初めてわかった途上国外交
著者経歴
飯村 豊(いいむら ゆたか)・・・1946年東京都生まれ。東京教育大学附属駒場中・高等学校、東京大学教養学部教養学科を経て、1969年外務省入省。外務省研修生として仏ディジョン大学、ストラスブール大学に留学。海外では在ソ連(当時)大使館、在フランス大使館、在フィリピン大使館及び在米大使館、国内においてはアジア局南東アジア一課、調査部企画課、官房人事課首席事務官、経済協力局技術協力課長、官房報道課長、欧亜局(現欧州局)審議官、経済協力局長及び官房長を務めた。2001年官房長更迭後官房審議官(監察・査察担当)を経て、駐インドネシア特命全権大使、駐フランス特命全権大使、政府代表(中東地域及び欧州地域関連)を歴任。外務省以外では、ハーバード大学国際関係研究所フェロー、国際博覧会(BIE)協会執行委員会(BIE)委員長、MSH(米国NGO)理事、東京大学公共政策大学院客員教授、フランス国立高等社会科学研究院シニア・フェロー、政策研究大学院大学(GRIPS)客員教授、東京大学経営評議会学外委員・総長選考会議議長を務める。現在、GRIPS・政策研究院シニア・フェロー、日仏会館評議員(議長)
外務省関連書籍
「外務省は 「伏魔殿」か: 反骨の外交官人生と憂国覚書」飯村 豊
「日本外交の挑戦」田中 均
「中国「戦狼外交」と戦う」山上 信吾
「反省 私たちはなぜ失敗したのか?」鈴木 宗男/佐藤 優
「日本がウクライナになる日」河東 哲夫
「中国・アジア外交秘話」谷野 作太郎
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!
































コメントする