【書評】「世界の本当の仕組み: エネルギー、食料、材料、 グローバル化 、リスク、環境、そして未来」バーツラフ・シュミル
2025/10/13公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(75点)
要約と感想レビュー
エネルギーの未来
カナダの大学教授が世界のグローバル化、エネルギーや食料の未来とリスクについて語る一冊です。著者は、私たちに今後も十分なエネルギーと水と食料が手に入るだろうか?と問いかけています。
1950年代頃から、資源の不足で世界は終わると予言する人がいました。それから世界の人口は3倍になりましたが、穀物の全世界の収量は約2.2倍に増え、原油も約1.7倍に増え、世界は終わりませんでした。
ただ現在、石炭の埋蔵量は約120年、原油と天然ガスの埋蔵量は約50年と言われていますが、これからも資源が枯渇しないのかどうかは、よくわからないのです。
エネルギー源としては木炭→石炭→石油・ガスが使われるようになり、電力も水力、火力、原子力、風力、太陽光などと技術か開発されてきました。
不安定な風力、太陽光が大量導入されていますが、火力で調整できなくなれば、何ギガワット時という単位の大きな蓄電施設が電力の安定供給のために必要となります。
実用化されているのは揚水式水力しかありません。その揚水式水力でも効率は0.7と3割は損失となります。他の貯蔵方法の容量は何桁も小さく、コストも高いのです。
原油は石炭とは違って・・・簡単に生産できる。原油はエネルギー密度が高く・・タンカーや・・パイプラインで大陸間を輸送できる(p49)
食料の未来
食料については、トウモロコシは、1920年には1haあたり2トンしか取れませんでしたが、2020年には11トン採れるようになりました。1800年には、アメリカの人口の83%が農民で、日本では90%が農民でしたが、今では小麦1kgあたりの労働は2秒未満であり、1haあたり3.5トンの収穫があるのです。
農業機械と無機肥料の導入で、食料生産は効率化されてきたのです。ただ、食糧の安定供給には、多くのエネルギーを必要としていることを知る必要があります。
例えば、スペインの野菜や果物の栽培者は、ビニールハウスで生産し、80%をEU諸国に輸出していますが、店舗への配送するまでに、1kgあたり130ミリリットルのディーゼル燃料を必要としてます。
近海のイワシやはサバは漁獲量1kgあたり100ミリリットルのディーゼル燃料を必要としますが、沖合や遠海漁業では、魚1kgあたり平均700ミリリットルのディーゼル燃料が必要となるのです。
さらに養殖になると、スズキの場合は、1kgあたり2~2.5リットルのディーゼル燃料が必要となるという。
食べられる肉の重さが今ではほぼ1kgきっかりになるアメリカのニワトリ1羽を生産するには、トウモロコシが3kg必要とされる(p97)
グローバル化の未来
1950年以降、世界はグローバル化しました。それは効率的なディーゼル機関が普及し、ジェットエンジンの航空機が導入され、鉄鉱石、石炭、穀物などを運ぶばら積み貨物船が作られ、貨物のコンテナ化によって輸送の標準化され、コンピュータにより事務手続きが簡単になったためだと分析しています。
グローバル化によって、2000年以降欧米諸国、日本などが中国に投資し、生産を中国に移転することで、アメリカ人製造業の700万人の職が失われました。
特にグローバル化が進んだのは、以前孤立していたロシアや中国、インド、アフリカの一部の国々、ブラジルなどです。特に中国は製造業で日本と同等となり、ロシアも石油・ガス輸出でスウェーデン並みとなり、インドもプログラマーを供給するなどしてシンガポールと同じレベルになったという。
ただ、コロナ禍で、世界のゴム手袋の70%がたった1つの工場で生産されていたり、抗生物質や医薬品が中国とインドの一部の供給業者に依存している状況が顕在化しました。アメリカでは、大型変圧器を中国製に依存していることから送電網の安全が心配されるなど、今後、グローバル化から逆に進んでいく可能性を著者は指摘するのです。
アメリカでは2000年以降、以前は高賃金だった製造業の働き口がおよそ700万も失われた・・大半は中国に移った(p216)
リスクを数字で考える
著者が憂うのは、人の感じるリスクと数字のリスクに差があることです。
例えば、自動車は毎年全世界で120万人を超える死者を生み出していますが、もし、橋や建物などが原因で同じ死者が出たら、許容されないでしょう。自働車は飛行機による移動よりも危険が1桁大きく、自動車の移動で死亡する確率は、自宅にとどまっているときと比べて、1.5倍になるのです。
ちなみにスカイダイビングでは、死亡事故は25万回に1回で、自宅にとどまっているときと比べて、50倍になります。
また、ワクチンで子供が自閉症になるという噂を信じて、子供に予防接種を受けさせない親がいます。その結果、子供が病気かかるリスクを自発的に大きくしているのです。
1995年から気候変動会議が毎年開催されていますが、中国による採炭は1995~2019年に3倍以上に増え、2050年までにCO2排出量は50%増加すると予想されています。
地球温暖化による自然災害の増加をテレビで指摘していますが、そのリスクは実は低いという。例えば、アメリカのハリケーンのリスクは、せいぜい落雷程度の死亡リスクでしかないというのです。
また、地球温暖化による海面上昇のリスクが指摘されていますが、太平洋の珊瑚礁島国家ツバルでは40年間に陸地面積が3%増えたという不都合な真実もあるという。
このように、学識者や大学の先生が、データや統計の数字に基づいていろいろな主張をしていますが、実は当たらないことが多く、未来はよくわからないということなのです。
それでもリスクに対し、適切に対処しておく必要があるのも事実でしょう。未来はわからないにしても、予測の誤差も含めて、リスクに対しどれだけ保険をかけるのかバランス感覚が大切なのだと思いました。
シュミルさん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・全世界で生産されるアンモニアの約80%は、作物の肥料のために使われ、残りは硝酸や爆薬、ロケットの推進剤、染料、繊維、窓や床の洗浄剤に使われる(p139)
・約450kgの重さがある自動車用の典型的なリチウム電池には、約181kgの鋼鉄と・・約11kgのリチウム、14kg近いコバルト、27kgのニッケル、40kg以上の銅、50kgの黒鉛が使われている(p168)
・地震のリスク・・・日本では、1945~2020年に、約3万3000人が地震で亡くなった・・全死亡率よりも4桁小さい(p254)
▼引用は、この本からです
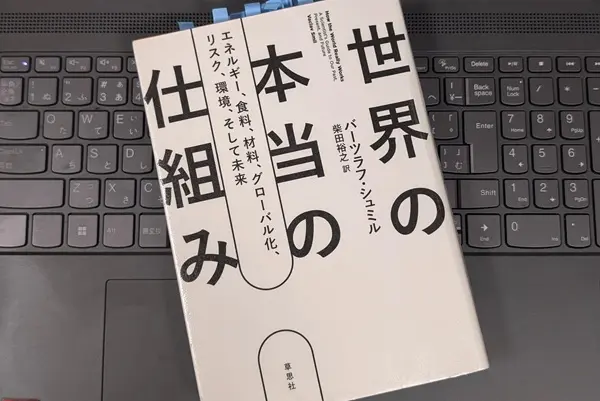
Amazon.co.jpで詳細を見る
バーツラフ・シュミル (著)、草思社
【私の評価】★★★☆☆(75点)
目次
第1章 エネルギーを理解する―燃料と電気
第2章 食料生産を理解する―化石燃料を食べる
第3章 素材の世界を理解する―現代文明の四本柱
第4章 グローバル化を理解する―エンジン、マイクロチップ、そしてその先にあるもの
第5章 リスクを理解する―ウイルスから食生活、さらには太陽フレアまで
第6章 環境を理解する―かけがえのない生物圏
第7章 未来を理解する―この世の終わりと特異点のはざまで
付録 数字を理解する―10n
著者経歴
バーツラフ・シュミル(Vaclav Smil)・・・カナダのマニトバ大学特別栄誉教授。カナダ王立協会(科学・芸術アカデミー)フェロー。エネルギー、環境変化、人口変動、食料生産などの分野で学際的研究に従事。2013年、カナダ勲章を受勲。
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!

































コメントする