【書評】「断片的なものの社会学」岸政彦
2025/10/12公開 更新
Tweet
【私の評価】★★☆☆☆(63点)
要約と感想レビュー
京都大学の社会学では何を教えているのか
鉄塔文庫読書会の課題本。京都大学の社会学の教授は何を教えているんだろうと考えながら読んでみました。
著者の専門の社会学では人の話を聞いてまとめるらしいのですが、不思議なのは、沖縄の人とか、在日とか、夫が刑務所に入った人とか、元風俗嬢とか、変な人の話ばかりであること。
例えば沖縄について著者は「私は沖縄ではよそものである。しかも私は、基地や貧困を沖縄に押し付けている当事者である」と書いています。いやいや、押し付けてないって。沖縄に日本政府は毎年3000億円の公共事業を投資しているのです。
社会学をやっている著者の周辺には、「在日コリアン」「沖縄人」「ゲイ」など差別をなくす活動をしている人が多いというのです。どういう業界なのでしょうか。
沖縄で、基地問題や沖縄戦の研究で非常に著名な方・・自分の家族と親戚が一度だけ、わざわざ沖縄から会いに来たことがあって、東京の繁華街の真ん中で待ち合わせたときに「向うのほうから真っ黒い顔の集団がやってきて、どこの土人かと思ったら、僕の家族だったよ」と言って大笑いをしていた(p95)
人びとは不安と恐怖を感じているのか
話の最後に、変な一言で終わるのにも違和感を持ちました。
例えば、ある貧しい女性の夫が、刑務所に入ったという。そして、女性はいくつかの職業を転々としたあと、今では公園で暮らしているというのです。この話の後で、著者は「これが私たちの暮らしなのである」で話を終わるのです。
いやいや、「私たち」じゃないって。世の中の何%の女性が夫が刑務所に行って、公園で暮らしている確率を調べれば、宝くじレベルで特異な事例だと思います。
また、別の男性は貧困家庭に生まれ、暴力団の一員となり、覚醒剤の取引で香港の捜査機関に捕まり、刑務所に10年間収監されていたという。現在は生活保護を受給しているという話なのですが、日本は犯罪を犯しても老後は安心して暮らせる国だとわかりますが、これも珍しい事例でしょう。
そして著者のまとめは、私たちは、なにか目に見えないものにいつも怯えて、不安と恐怖を感じている。そして、差別や暴力は、そういう不安や恐怖から生まれてい来るのだと思う(部落や在日に対する差別は大阪でも強い)と結論づけるのです。
いやいや、犯罪を犯しても老後が安泰な日本で、不安や恐怖がどこから来るのかわからないし、差別と暴力を結びつけるロジックがまったく説明になっていないのです。
自分の研究や教育、社会活動の関係で、いわゆるマイノリティとか差別とか人種とかそういう活動をしている人たちと友だちになることが多い(p95)
外国人が生活保護を受給しているのは損なのか
京都大学の教授なのに、こじつけのような自分の意見を正当化する説明が多いことも気になりました。
例えば、著者は「私たちにはいつも、どこに行っても居場所がない。だから、いつも今いるここを出てどこかへ行きたい」と書いていますが、居場所のある日本人のほうが多いのが私の感覚です。「私たち」ではなく「私」なのではないでしょうか。
また、著者は幸せのイメージは、それが得られない人びとへの暴力になると言っています。例えば、不妊の夫婦に、子どもを作らなくてはならないという常識が暴力になるというのです。
もちろん不妊の夫婦にとっては不運なことですが、一定の確率で不妊の夫婦はいるものなのです。その不運を暴力という表現を使ったり、夫婦を排除される人と表現するなど誤解を生むように誘導しているように感じるのです。
さらに、ギャンブルや薬物依存症はマルチ商法やカルト宗教のことには、多くの学生が何も言わないことを紹介したうえで、外国人が生活保護を受給していると聞くと、なんとなく損した気持ちになることが、同じように考えるように誘導するのです。
外国人が生活保護を受けているのは、違法ですが、運用で認めているだけで、日本人がお人良しなだけなのです。こうしたことを京都大学で教えてよいのでしょうか。
幸せというものは、はじめに書いたとおり、そこから排除される人びとを生み出す、という意味で、それは同時に暴力でもある(p114)
社会は排他的で狭量で息苦しいものなのか
著者は最後に、「いま、世界から、どんどん寛容さや多様性が失われています」と根拠なく断定し、「私たちの社会も、ますます排他的に、狭量に、息苦しいものになっています。この社会は、失敗や、不幸や、ひとと違うことを許さない社会です」と書いています。
いやいや、社会はどんどん進歩して幸せな人が増えているというのが私の認識です。排他的で狭量で、息苦しいのは著者の周辺だけであり、「私たち」ではなく「私」と表現するべきではないでしょうか。
このスタイルで学生を指導していると思うと、不安に感じました。
ただ、そうした批判を避けるためなのか、著者は、「動物の肉を食べながら、どうして子猫を拾ってしまうのかわからない」とし、自分がイルカや鯨の漁に反対なのは理屈が通らないとしています。
しかし理屈がなくても、外国人は出ていけとか、生活保護を廃止しろとか、そういう意見を表明することはできるのだから、自分も同じように理屈がなくても自分の意見を表明できるとまったく違うことを同じレベルで比較して論理がめちゃくちゃなのです。
ますます不安になりました。
岸さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・ホストにはまる風俗嬢、というものがたくさんいて、せっかく稼いだカネをすべてそこに注ぎ込んでしまう、ということが、この世の中には珍しくないのだ、ということを学ぶことはできる(p37)
・私の大切な友人に、朝鮮学校の美術の先生がいる。彼女は自分でも作品を作っている。それは、巨大な乳房がついた、小さな土偶である(p44)
・マイノリティは、「在日コリアン」「沖縄人」「障害者」「ゲイ」であると、いつも指差され、ラベルを貼られ、名指しをされる。しかしマジョリティは、同じように「日本人」「ナイチャー」「健常者」「ヘテロ」であると指差され、ラベルを貼られ、名指しをされることはない(p170)
・自分が思う正しさを述べる「権利」がある。それはどこか、「祈り」にも似ている・・・祈りが届くかどうかは「社会」が決める(p211)
▼引用は、この本からです
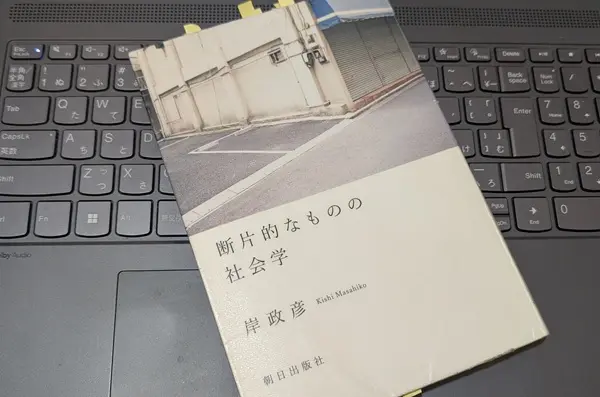
Amazon.co.jpで詳細を見る
岸政彦 (著)、朝日出版社
【私の評価】★★☆☆☆(63点)
目次
人生は、断片的なものが集まってできている
誰にも隠されていないが、誰の目にも触れない
土偶と植木鉢
物語の外から
路上のカーネギーホール
出ていくことと帰ること
笑いと自由
手のひらのスイッチ
他人の手
ユッカに流れる時間
夜行バスの電話
普通であることへの意志
祝祭とためらい
自分を差し出す
海の向こうから
時計を捨て、犬と約束する:物語の欠片
著者経歴
岸政彦(きし まさひこ)・・・京都大学大学院文学研究科教授。社会学研究室所属。1967 年生まれ。大阪市立大学大学院文学研究科単位取得退学。博士(文学)。専門は、社会調査方法論、生活史。沖縄における質的調査。研究テーマは沖縄、被差別部落、生活史。
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!
































コメントする