【書評】直木賞受賞作「利休にたずねよ」山本 兼一
2022/09/17公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(87点)
要約と感想レビュー
利休とは何者だったのか
信長、秀吉に仕えた利休とは何者だったのか。秀吉から相談されるくらい信頼されていた利休が、秀吉から切腹を命じられたのはなぜなのか。今となってはわからない歴史のナゾを、歴史小説の形で謎解きした一冊です。
表向きの理由としては、大徳寺の門の上に自分の木像を置いて、人を上から見下ろしていることが不敬であること。茶道具を高額で売り、暴利をむさぼったことです。一般的には娘を秀吉の側室に差し出さなかったこと、朝鮮出兵に反対したことなどと言われていますが、著者はそれは本筋ではないとしています。
著者の筋書きは、利休が表向きは頭を下げつつも秀吉が所望する香合(香を収納する容器)を差し出さず、あくまで茶を追求する利休の姿勢に秀吉が傲慢を感じたからです。そしてその香合には、利休の若き日の秘密の思い出とつながっていたという映画「タイタニック」ばりの物語となっているのです。
茶が人を殺す・・・茶の湯には、人を殺してもなお手にしたいほどの美しさ、麗しさがあります(利休)(p272)
口は災いの元
興味深いのは登場人物を使って言わせる、著者の人生観でしょう。利休とは、利は、鋭いという意味であり、鋭すぎる男は、人に嫌われる。だから鋭利なこころを休めたほうがよいというのが利休の由来なのです。
それにもかかわらず、利休は茶の湯について天下一の自負があったがゆえに、それを秀吉に見せてしまい切腹することになりました。著者は、利休に「自負を剥き出しに見せているようでは、まだ人として底が浅いといわねばなるまい」と言わせているのです。
同じように茶席で豊臣秀吉を怒らせた山上宋二にも、「ほんとうのことは、口にしてはならぬものだ。真実を告げたら、嫌われる。まことを話したら殺されかねない」と言わせています。「口は災いの元」ということなのでしょう。
人の世には、三毒の焔が燃えさかっている。三毒は、仏法が説く害毒で、貪欲、瞋恚(しんに)、愚痴、すなわち、むさぼり、いかり、おろかさの三つである(p243)
利休が茶の湯を文化にする
利休切腹の表向きの理由に、茶道具を高額で売っていたことがあります。利休が認めた道具は、高値で取引されたのです。ワインでいえば、ロバート・パーカーが評価すれば高値で取引されるのと似ています。
金や宝石ではなく、純粋に「美」に対して大金を支払うというのは、単なるお茶飲みを利休が芸術のレベルにまで高めた証拠だと思いました。利休が茶の湯、茶道という後世まで伝え続けられる日本文化を作り上げたのです。
そうした利休の自負こそが、利休の自死につながったというのも、人の世の難しさなのだと思いました。山本さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・茶入などは、ただの土器(かわらけ)ではございませぬか。ただの土くれに、なにゆえ銭三千貫もの高値がつくのか、さっぱり合点がゆきませぬ」(景勝)(p37)
・唐物名物をむやみとありがたるのが、足利将軍時代の書院の茶の悪弊である。あたらしい侘び茶は、書院の茶の派手な道具自慢に辟易したところから出発している(p86)
・同じむさぼりの焔にしても、信長と秀吉ではずいぶん色彩が違う、と宗陳は思った。信長のむさぼりは、いたって求道的な色合いが強い気がした(p249)
・秀吉は思った。世の中、存外おもしろいことは少ない。なにか、痛快なことはあるまいか(p208)
・肝要なのは、毒をいかに、志にまで高めるかではありますまいか。高きをめざして貪り、凡庸であることに怒り、愚かなまでに励めばいかがでございましょう(p259)
【私の評価】★★★★☆(87点)
目次
死を賜る ──利休
おごりをきわめ ──秀吉
知るも知らぬも ──細川忠興
大徳寺破却 ──古渓宗陳
ひょうげもの也 ──古田織部
木守 ──家康
狂言の袴 ──石田三成
鳥籠の水入れ ──ヴァリニャーノ
うたかた ──利休
ことしかぎりの ──宗恩
こうらいの関白 ──利休
野菊 ──秀吉
西ヲ東ト ──山上宗二
三毒の焔 ──古渓宗陳
北野大茶会 ──利休
ふすべ茶の湯 ──秀吉
黄金の茶室 ──利休
白い手 ──あめや長次郎
待つ ──千宗易
名物狩り ──織田信長
もうひとりの女 ──たえ
紹?の招き ──武野紹?
恋 ──千与四郎
夢のあとさき ──宗恩
著者経歴
山本 兼一(やまもと けんいち)・・・1956年(昭和31年)、京都市生まれ。 同志社大学卒業後、出版社勤務、フリーランスのライターを経て作家になる。 2002年、『戦国秘録白鷹伝』(祥伝社)で長編デビュー。2004年、『火天の城』(文藝春秋)で第11回松本清張賞を受賞。2009年、『利休にたずねよ』(PHP研究所)で第140回直木賞を受賞。 その他の作品に『いっしん虎徹』(文藝春秋)『命もいらず名もいらず』(NHK出版)『おれは清麿』(祥伝社)『信長死すべ』(角川書店)、また、「とびきり屋見立て帖」(文藝春秋)「刀剣商ちょうじ屋光三郎」(講談社)のシリーズがある。
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」 3万人が読んでいる定番書評メルマガです。 >>バックナンバー |
| |
この記事が気に入ったらいいね!
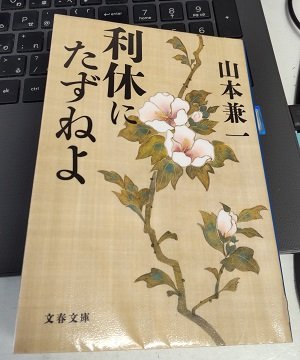



































コメントする