【書評】「文明崩壊(上)」ジャレド・ダイアモンド
2020/06/17公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(84点)
要約と感想レビュー
記録のあるグリーンランドの歴史
本書上巻では、中米のマヤ文明、イースター島、グリーンランドへのヴァイキング(ノルウェー人)の入植などが紹介されています。日本の本ならそれぞれが一冊の本になるくらいのボリュームで、いっぱいいっぱいでした。
マヤ文明やイースター島については記録が少なく推測の部分が多いので、ある程度記録のあるグリーンランドの歴史が楽しめました。
マヤ文明については、1549年から1578年の間、スペインのフランシスコ会の司祭ディエゴ・デ・ランダは、異教信仰粉砕のために、マヤ文字で書かれた書物をすべて燃やしてしまったという。その結果、マヤ文字の書物はわずか4点しか現存していないというのです。
干物の輸出は、1300年以降、アイスランド経済再建の鍵となったが、ヨーロッパからもっと遠距離にあるグリーンランドでは、ヨーロッパへの航路が海氷によって阻まれることが多く、干物を輸出することができなかった(p408)
1300年ごろから小氷河期
グリーンランドにノルウェー人が到達したのは西暦980年ごろとされています。当時は中世温暖期と呼ばれ、現在のグリーンランドと同程度かあるいはわずかに暖かかったという。
1300年ごろから小氷河期と呼ばれる寒冷期に入り、15世紀頭にはグリーンランドは歴史から消えるのです。著者は、グリーンランドのノルウェー人絶滅の理由は、寒冷化という変化に対し、ヨーロッパ文化に固執し、家畜を飼いつづけ、教会を維持し、イヌイットの知恵を活用しなかったためではないか、と推測しています。なぜなら、イヌイットは小氷河期を生き抜いているからです。
ノルウェー人たちが気候の比較的穏やかな時期にグリーンランドに入植したのは、幸運であり、不運でもあった。寒冷期に入ると家畜の数を維持するのがむずかしくなることなど予測しようがなかった。20世紀に入ってから、デンマーク人がヒツジとウシをグリーンランドに再導入したが、やはり失敗を免れず、ヒツジの頭数が多すぎて土壌侵食を引き起こし、ウシについては早々に飼育をあきらめた。現代グリーンランドは経済的に自立しておらず、デンマークからの対外援助と欧州連合からの漁業権料に大きく依存している(p548)
人間は必然的に自然を破壊する
本書を読んでわかるのは、人間が増えていくなかで必然的に自然を破壊するということです。自然破壊のスピードと自然の回復力が問題であり、破壊が早ければそこは砂漠になってしまうのです。
例えば、アイスランドでは人間が居住を始めてから、もともとこの島にあった樹木と植生は破壊され、土壌の約半分が浸食によって海中に流入し、今ではほとんどが茶色い荒地となっているという。
人間が死滅しないためには、自然の再生力の範囲で自然を活用していくことなのでしょう。ダイアモンドさん、良い本をありがとうございました。
| メルマガ[1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』] 3万人が読んでいる定番書評メルマガです。 >>バックナンバー |
| 配信は『まぐまぐ』を使用。 |
この本で私が共感した名言
・人間が入植するたび、大型動物の絶滅という波が起こった。・・・環境資源の濫用という罠からは、どんな人間も逃れられない(p31)
・例えば、イースター島の住民たちは、島に残った最後の一本の木を切り倒すとき、どういう言葉を吐いたのだろう?(p55)
・過去の社会の多くは、食料不足が発生した際、気候の違う地域の余剰食糧を取り寄せるという"有事救済"の仕組みを持っていなかった・・・過去の社会では気候変動のリスクが大きかったと言うことができるだろう(p37)
・"黒人狩り"が1805年頃から始まり、1862年から1863年に最盛期を迎えた。イースター島史上最も苦難に満ちたこの時代には、20隻余りのペルー船がおよそ1500人(生存者の半数)の島民を連れ去り、競売にかけて、ペルーの鉱山における鳥糞石の採掘を始め、さまざまな雑役を強制した(p226)
・農民たちは、どのような階層社会でも、自分たちの必要ぶんだけでなく、ほかの消費者たちの必要も満たすだけの食料を供給しなければならない・・・効率性の高い農業が行われている現在のアメリカ合衆国では、農民は全人口のわずか2%を占めるのみで、農民ひとりが平均して125人のほかの人間に食糧を供給している(p328)
・メソアメリカ社会には金属器がなく、また、滑車などの装置も、車輪もなく、帆船もなく、荷役や耕耘(こううん)に使える大型の家畜もいなかった。あの壮大なマヤの神殿は、すべて石器と人力だけで建てられたのだ(p332)
・1500年以降、ようやくヨーロッパ人の入植者たちが北米大陸にふたたび到達した・・・銃や鉄器を装備した補給船団を毎年送り出して後押しした・・・イギリスやフランスがマサチューセッツ州、ヴァージニア州、カナダに築いた植民地では、最初の一年が経たないうちに、入植者の約半数が飢えと病気で命を落としている(p421)
【私の評価】★★★★☆(84点)
目次
第1部 現代のモンタナ
第1章 モンタナの大空の下
第2部 過去の社会
第2章 イースターに黄昏が訪れるとき
第3章 最後に生き残った人々(ピトケアン島とヘンダーソン島)
第4章 古の人々(アナサジ族とその隣人たち)
第5章 マヤの崩壊
第6章 ヴァイキングの序曲と遁走曲
第7章 ノルウェー領グリーンランドの開花
第8章 ノルウェー領グリーンランドの終焉
著者経歴
ジャレド・ダイアモンド(Jared Diamond)・・・1937年生まれ。アメリカの生物学者、ノンフィクション作家。ハーバード大学で生物学、ケンブリッジ大学で生理学を修め、カルフォルニア大学ロサンゼルス校医学部生理学教授を経て、現在は同校地理学教授。
この記事が参考になったと思った方は、
クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓ ![]()
人気ブログランキングへ
| メルマガ[1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』] 3万人が読んでいる定番書評メルマガです。 >>バックナンバー |
| |
この記事が気に入ったらいいね!
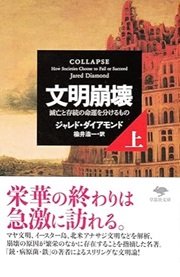



































コメントする