【書評】「すぐ実践! 利益がぐんぐん伸びる 稼げるFTA大全」羽生田慶介
2025/05/28公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(80点)
要約と感想レビュー
関税3%は法人税30%に相当する
トランプ関税の意味を考えるため、再読してみました。2018年に米トランプ政権が中国と関税合戦をはじめた頃の書籍です。関税がなぜ経営者にとって重要なのかといえば、関税は輸入価格(CIF価格)に課税されるからです。
仮に輸入価格が100円で売値が110円、粗利が10円だったとすれば、関税が10%が課税されるだけで利益はゼロ(△100%)になります。逆に、関税10円、売値が120円で粗利が10円だったとすれば、関税10%がゼロになれば、利益は20円(+100%)になるのです。
日本の企業の粗利は10%程度なので、「関税3%は法人税30%に相当する」のはおおよそ事実なのです。
また、関税支払いの多い企業では、仮に税関当局から不正の指摘を受ければ、追徴課税されるリスクがあります。過去には数百億円にも及ぶ追徴課税を命じられた日本企業もあるという。
輸出に10%かかっていた関税が、FTAの活用によってゼロになる・・・最終利益を倍増させるほどの影響力があった(p7)
FTAが活用されていない実態
著者は、経済産業省通商政策局でFTA交渉に従事していましたので、あれだけ苦労して交渉したFTAが、十分に活用されていないことを知って、少しショックを受けたという。
FTAを活用しきれていない理由は、いろいろあるります。例えば、商社に輸出手続きを任せていた場合、商社を輸出のプロとして信頼し、FTAを含めて最適な手法を取っているはずだと思っているとしたら、そうでもないのです。
なぜなら、通関でかかったコストは、関税分を含めて顧客に請求すればいいので、「FTAを駆使してなるべく安い関税率に抑えよう」という意識があまり高くないのが実情だというのです。
また別の例では、商社を省いて自社で輸入してコスト削減しようとしたら、経験不足からFTAを駆使できず、高い関税を払うことになり、逆にコストアップしてしまったという事例も多いという。
2016年時点で、日本企業の発効済みFTAを利用している企業の割合は調査対象1234社のうちの約45%に留まっている(p40)
関税の引下げで儲かるのは輸入側だけ
では、これから社内のFTAの「使い漏れ」をなくそうとしたとき、どのようなことが起こるのでしょうか。
まず、サプライヤーに「原産地規則」を満たすことを証明する必要な書類を準備してもらうことになります。しかし、輸入関税の引き下げで儲かるのは輸入側だけなので、サプライヤーは「ウチの手間が増える分のメリットは支払ってもらえるのか」という話になるのです。
したがって、まずは調整しやすい自社グループ内の取引先から始めるのが普通であるというのです。
そして自社グループとはいっても、FTAの「使い漏れ」をなくした場合、どれだけメリットがあるのか概算する必要があります。そのために、社内でFTAの「使い漏れ」がありそうな取引をピックアップして、取引明細を取り寄せ、書かれてある課税額を足し合わせる作業が必要になるのです。財務システムで関税支払額や関税番号が整理されていれば簡単ですが、整理されていない場合が多く、作業量が大きいのが現実だという。
また、仮に多額のFTAの「使い漏れ」が判明したとしても、現場の担当者が、自分の責任回避のために、その場で応急対応して、「問題なし」と本社に報告し、マニュアル作成や業務プロセスの改善などの抜本的な改善策が行われないまま、うやむやになったこともあったという。
経営陣は決して現場の担当者の責任を問わず、FTA対応の業務を整備していなかった自身の責任を明確に社内に示すべきだ(p124)
外部のリソースを活用する
FTAは諸刃の剣で、良いときは最高ですが、悪いときには最悪の事態も想定する必要があります。特にトラップ大統領のように突然の関税を変更されてしまうと、海外工場の仕事が、ある日突然、なくなってしまうリスクもあるのです。
国際情勢の見通しが立たないときに著者がお勧めするのは、正社員を雇用するのではなく、外部のリソースを活用することです。また、設備投資せずに、外部の生産委託サービスを活用することです。仮に海外ビジネスが縮小しても、それに応じて外部に委託する内容を減らせばいいだけだからです。
トランプ関税の影響力の大きさのイメージが浮かびました。これでは投資は難しいですね。羽生田さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・シンガポールや香港など、第三国を経由した取引での「使い漏れ」・・シンガポールの倉庫で製品に特段の加工がされず、当局が認める在庫管理ができていれば、シンガポール関税から「Back-to-Back CO(連続する原産地証明書)」を受け取ることができる・・直接日本から製品を輸出した場合と同じように、FTAの特恵関税が適用される(p111)
・新興国が税収確保のために、輸入手続きの「あら探し」をしてくる・・・原産地証明書の不備を突いたり、輸出品目の関税番号の再確認を求めたり、その手段は様々だ(p149)
・FTAのような国際約束がある場合、特別な許可などを得ずに出資できることにはなっている。ただ、新興国の当局担当者がすべての国際約束を把握しているとは考えにくい・・自社がFTAのサービス貿易の規制緩和の対象企業の定義に当てはまるかどうかも、確認しなくてはならない(p175)
・企業の役員が、よかれと思って政府に提言すると、その内容に関する議論をせずにひと言、「それは業界の総意ですか、御社の意見ですか」と言い放つ官僚が、今なお存在することも事実だ(p250)
▼引用は、この本からです
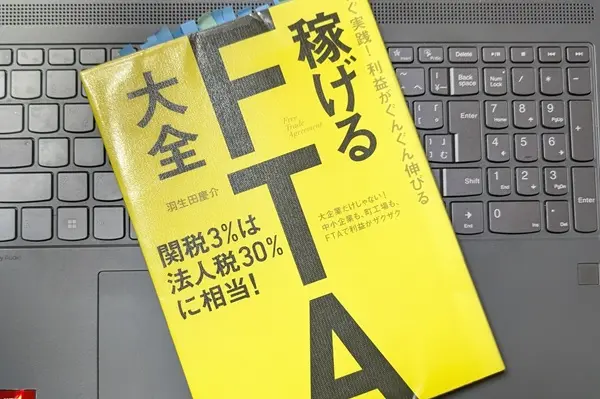
Amazon.co.jpで詳細を見る
羽生田慶介(著)、日経BP
【私の評価】★★★★☆(80点)
目次
はじめに 本当は怖いFTA残酷おとぎ話
第1章 導入編―まず理解すべき通商の基本
第2章 実践編―すぐ始める通商対応
第3章 戦略編―激動の通商環境を生き抜く
著者経歴
羽生田慶介(はにゅうだ けいすけ)・・・デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員/パートナー レギュラトリストラテジーリーダー 多摩大学大学院 ルール形成戦略研究所 副所長/客員教授。国際基督教大学(ICU)教養学部卒業。経済産業省 通商政策局にてアジア諸国とのFTA交渉に従事(ASEAN地域担当)。キヤノン、A.T. カーニーを経て、2013年にデロイト トーマツコンサルティングで現職。
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!


































コメントする