【書評】コメの価格が上がる原因「誰が農業を殺すのか」窪田新之助, 山口亮子
2025/05/14公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★★(90点)
要約と感想レビュー
まだまだ騙せる日本人
日本が開発したフルーツの品種が、中国・韓国などで大量栽培され、国際協力に成功しています。邱永漢は「まだまだ騙せる日本人」と表現していましたが、お人好し国家、日本を理解できる一冊です。
中国では、愛媛ミカンの品種「愛媛38号」「紅まどんな」「甘平」「媛小春」、また「シャインマスカット」や、それだけでなく静岡県が育成したイチゴ「紅ほっぺ」の種苗(しゅびょう)が販売されているという。
中国・四川省・丹ろう県では、愛媛ミカンの「愛媛38号」栽培が広がり栽培面積は1800ヘクタールと報道されています。「シャインマスカット」は、中国での栽培面積は日本の約29倍にも達するというのです。
そもそも愛媛ミカン「愛媛38号」は日本国内では栽培されておらず、県の研究所内で管理されている品種です。中国人農家が愛媛県の研究所から無断で持ち帰り、栽培したのです。2017年には中国農業科学院の「柑橘研究所」が「愛媛38号」を福建省で導入し、成功したと報道されています。中国の国家組織が、日本の開発した品種を窃盗し、中国国内に普及させたのです。
中国・上海にある公的研究機関を訪ねた際、日本で育成された名の知られたイチゴの品種がほぼすべてそろっていたという(p31)
海外で品種登録しない農研機構
背景には、過去に国際協力の名のもとに日本の公的機関の研究者や農家が、国内の種苗を海外に持ち出したり、栽培技術を指導したことにあります。行政職員のOBが海外から営農指導のコンサルタントとして雇われ、自県の種苗を持ち出したという噂が、よく聞かれるという。
愛媛県でも10年前まで、「果樹研究センター」や「みかん研究所」で中国・韓国からの視察団を受け入れてきました。対応する職員は通常1人ですから、見学中に枝を折り、その枝を自分の産地で接ぎ木をすれば、簡単に増殖できるのです。さすがに愛媛県は、10年ほど前から海外の農家や農業団体の視察を受け入れていないという。
中国で「あきたこまち」が生産され、リンゴの「ふじ」が6割強のシェアを誇っているのは必然なのです。
しかし、中国・韓国から許諾料を取ることはできません。海外で品種登録できる期間は、自国内で譲渡を始めてから6年以内で、農研機構が海外での品種登録をしてこなかったからです。
農研機構に種苗で儲ける発想があれば、流出は防げたはずだ(p55)
種苗法改正反対派の論理
こうした海外への種苗の無断流出を阻止するために、2022年に種苗(しゅびょう)法が改正されました。ところが、これに農業学者や元農相、JAの組合長らが反対し、一部の県では許諾の手続きや許諾料が必要ですが、多くの都道府県では、手続きも許諾料も求めず、骨抜きになったという。
その反対派の意見は、著者の分析では改正案を曲解した感情的なものが多かったと著者は説明します。具体的には、旧民主党の菅直人政権で農相を務めた山田正彦氏は、「種子は人類の遺産であり、企業の金儲けの対象とするのはおかしい!」と種子の海外への無断流出は問題ないと主張しました。日本がお人好し国家となった背景に、民主党の政治家の存在があったのです。
また、東京大学大学院農学生命科学研究所の鈴木宣弘教授は、「農家が購入する種子代が高額になる」と批判しています。著者によれば、民間の品種が高額であるのは事実ですが、実は民間の品種は収穫量が2倍近くあり、トータルで収支を判断すればいい話なのです。意図的なのか、単純な誤解なのかわかりませんが、著者は鈴木教授の主張の合理性に疑問を呈しています。
このように、国や地方自治体が税金を投じて開発した種子を、海外に無断流出するのを放置することによって、海外の農業を振興し、日本農業の足を引っ張ってきたのです。
農政は輸出の芽をつぶす・・種苗が海外に無断で流出する事態を黙認している(p8)
日本の農産物の輸出
ところが面白いことに、農水省は日本の農産物の輸出を振興しています。農水省は輸出拡大の重点品目コメの広報活動として、2017年に上海の高級料理店で、パックご飯を使ったメニューを提供するキャンペーンを行いました。こうした輸出拡大のための予算は、2017年度7億5000万円で、輸出額35億円4分の1も投じています。
しかし、輸出額は増えていません。輸出が伸びない原因を、著者は次のように分析しています。仮に高付加価値でイチゴを売ろうとした場合、新鮮なイチゴが手に入らない、かつ高所得層がいる地域の近くにイチゴ工場を建てるとよい。ところが輸出では、輸送費がかかり、鮮度も落ちる。鮮度が落ちれば、高付加価値で売れないというジレンマに陥るのです。
したがって著者の提案は、筋の悪い「農林水産物や食品の輸出」ではなく、「日本独自の種苗とその栽培システムを輸出」することです。つまり、知的財産として権利を確保し、許諾料で稼ぐのです。実際、長野県のリンゴ「シナノゴールド」は、商標登録によってイタリアの生産者から許諾料を取っています。
商標を登録すれば、同じ、あるいは似たような商標の使用を禁じ、模倣品を排除できる(p58)
コメの価格が上がる原因
一般的に、先進国では豊富な資本と技術を農業に投じることによって生産性が高まっていきます。しかし、日本の場合、農業は守るべきであるという認識を変えられない農政関係者が圧倒的多数を占めており、零細な農家を保護してきた結果、生産性は上がりませんでした。
また、種苗の海外への無断流出が数十年にわたって続いたにもかからわず、現地調査や法改正といった対策を講じ始めたのは最近のことです。農水省が無断流出を放置したのは、そこに潜む権力者と利権が関係しており、日本の農政は関係者にとって触らないのが安全と感じる世界だからなのでしょう。
現在、コメの価格が上がっていますが、価格が下がらないように減反してきたのだし、零細な農家が高齢化で退出して、思ったより減反がいきすぎただけに見えます。
コメの先物市場もJAの意向を受けた農水族の大物政治家による農水省への圧力によって潰され、日本にはコメの市場も価格の指標もありません。日本の農業を殺したのは、日本の農政関係自身である、というのが本書の結論なのです。
日本の農政について、総括的かつ提案もあり、レベルの高い内容でした。窪田(くぼた)さん、 山口さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・多くの都道府県は原則的に自分たち、あるいは農水省系の研究機関である農研機構が開発した品種以外を奨励品種として認めない・・民間企業にとっては実質的な参入障壁となっている(p194)
・有機農業・・みどり戦略は、有機農業の関係者すら蚊帳の外に置いて推し進められてきた。その理由は、日本政府が海外向けに、環境保護やSDGsへの貢献を強調するパフォーマンスをしたかったからだ(p126)
・1961~2021年に造成された農地は、113万ヘクタールにのぼる。これは、耕作放棄地の面積の3倍に近い・・・早晩耕作されなくなる農地を作り続け、「耕作放棄地問題」を膨らませたのは、農水省自身にほかならない(p113)
・農地転用・・・可否を決める各自治体に置かれた農業委員会のさじ加減次第である。そのため、本来転用を認めるべきではない広くて立地の良い農地にショッピングモールが建ったり、太陽光発電のパネルが敷き詰められたりする(p116)
▼続きを読む
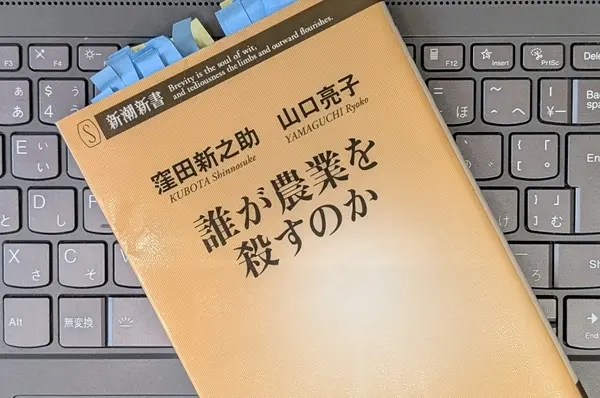
Amazon.co.jpで詳細を見る
窪田新之助, 山口亮子 (著)、新潮社
【私の評価】★★★★★(90点)
目次
第1章 中韓に略奪されっぱなしの知的財産
第2章 「農産物輸出5兆円」の幻想
第3章 農家と農地はこれ以上いらない
第4章 「過剰な安心」が農業をダメにする
第5章 日本のコメの値段が中国で決まる日
第6章 弄ばれる種子
第7章 農業政策のブーム「園芸振興」の落とし穴
第8章 「スマート農業」はスマートに進まない
著者経歴
窪田新之助(くぼた しんのすけ)・・・農業ジャーナリスト。日本農業新聞記者を経て、2012年よりフリー。著書に『農協の闇』『データ農業が日本を救うなど。
山口亮子(やまぐち りょうこ)・・・ジャーナリスト。京都大学文学部卒。中国・北京大学修士課程(歴史学)修了。時事通信記者を経てフリー。執筆テーマは農業や中国。
農業関連書籍
「バターが買えない不都合な真実」山下 一仁
「農家はもっと減っていい 農業の「常識」はウソだらけ」久松 達央
「誰が農業を殺すのか」窪田新之助, 山口亮子
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!



































コメントする