【書評】「18歳からの自炊塾 九州大学 生き方が変わる3か月」比良松 道一
2021/10/28公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(77点)
要約と感想レビュー
学生の食生活の実態を調査してみると、朝は抜くかお菓子、ご飯よりパンや麺類を好み、手作りの食事はほとんどないという結果に、著者は驚きました。本のソムリエも自炊したことがないので、学生と同じようなものです。
そこで九州大学の教員だった著者は、自炊の大切さを伝える「自炊塾」という授業を立ち上げました。「自炊塾」の授業では、フランス料理のオーナーシェフによる課外授業もあり、楽しみながら料理の面白さを学ぶことができるようになっています。
・授業のあと、シェフから鮮魚を渡された学生たちは競うようにさまざまな魚料理に挑戦しては、セミナーの情報交換の場、フェイスブックにその写真を載せます(p16)
驚いたのは、授業で行う清涼飲料水ビジネスの体感実験です。アイスコーヒーのシロップ6個を500mlの水に溶かします。これを飲むと全員が「甘っ!!」と叫び、飲み続けられません。実はこのシロップ6個は、市販の炭酸飲料に含まれる糖分と同じ量なのです。
とても甘くて飲めない砂糖水を炭酸やレモン果汁、ビタミンCなどで感覚を麻痺させているのです。こうして炭酸飲料に含まれる過剰な糖分は、インスリンを作っている膵臓の負担となり、中毒性により糖尿病を大量生産しているわけです。
・糖尿病患者の急激な増加と若年化・・・強い甘さは病みつきになる・・・その中毒性は麻薬の一種であるコカインの中毒性に勝る(p57)
ご飯と味噌汁と手作りのおかず。誰もが手作りの日本食の大切さ、素晴らしさは知っていると思います。自炊の大切さは読書と一緒で、やってみないとわからないし、一定の強制性が必要だと感じました。
自炊による食事は、体調に直結し、本人の心にも影響を与えるのです。海外に行くと、日本の味噌汁が飲みたくなるのも、日本食の大切さを証明するものなのでしょう。素晴らしい授業だと思いました。食糧自給率向上にも資するものですので、義務教育に取り入れてもらいたいものです。
比良松さん、良い授業をありがとうございました。
この記事が参考になったと思った方は、
クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
人気ブログランキングへ
この本で私が共感した名言
・自炊しなくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。かんじんなことは、目に見えないんだよ(p20)
・自分史から学んだんことは、好きなことはただちに仕事にはできない。けれども、好きなことを追い求めて研鑽を積むうちに、自分に向いていることやできることが明確になり、やがてそれが人様に喜んでもらえる仕事になる(p26)
・「生」の反対は何でしょうか?・・・生の反対は、生まれないこと(p30)
・性のトラブルを抱える子は、食のトラブルも抱えています(p32)
・医は食に、食は農に、農は自然に学べ(竹熊宜孝)(p150)
【私の評価】★★★☆☆(77点)
目次
第1章 自炊することで、人は変わる
第2章 今、なぜ自炊なのか?
第3章 見てまねて、自炊力を身につける
第4章 食材・食文化の価値を再発見
第5章 自炊の先に広がるもの
第6章 これからの自炊塾
著者経歴
比良松 道一(ひらまつ みちかず)・・・ 1965年、福岡生まれ。九州大学大学院農学研究科修士課程修了後、福岡農業試験場、同大農学部などで、作物の品種改良や来歴を解き明かす研究に従事。2006年、子どもがつくる「弁当の日」に感化され、以降、食育に力を注ぐ。2013年4月より九州大学で「自炊塾」を開講。2014年から社会問題の解決に貢献するリーダーを育てる「九州大学持続可能な社会のための決断科学センター」准教授。
| メルマガ[1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』] 3万人が読んでいる定番書評メルマガです。 >>バックナンバー |
| |
この記事が気に入ったらいいね!





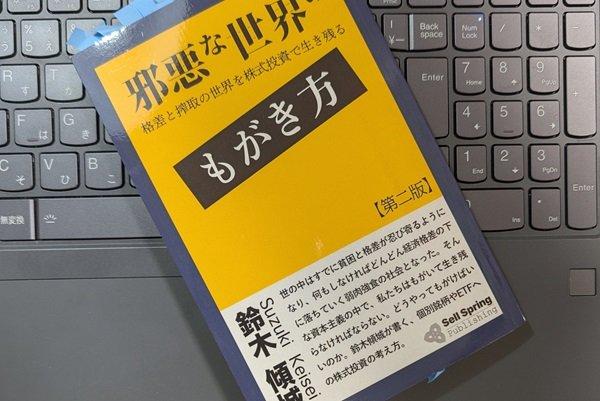




























大学進学と同時に一人暮らしを始めた息子が自炊生活をスムーズにできるようになったのは運よく「自炊塾」を受講することができたからだと思います。
私も義務教育で同じような授業があるといいと思うのですが、なかなか難しいのでしょうね。