【書評】「命を守る食卓」鈴木 宣弘,印鑰 智哉,安田 節子
2025/08/14公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(76点)
要約と感想レビュー
肉に残留する成長促進剤
安全で健康的な食品の供給について、問題提起する一冊です。
まず、明らかに問題そうなのは、EUが禁止している食材が、日本に輸入されていることでしょう。例えば、EUでは牛や豚にホルモン剤を使うことは認められていません。アメリカ産牛肉のうちホルモン剤を使わない牛肉がEUに輸出され、日本には規制値以下の残留量の牛肉が輸出されているのです。
同じように、輸入豚肉には赤身を増やす薬剤ラクトパミンが使われていますが、EUでは豚には薬剤投与が全面禁止です。日本でもラクトパミンは禁止ですが、輸入品は残留量が規制されているだけなのです。
こうした成長促進剤については、濃度によって危険性を下げることができると思われますが、国によって基準が違うというのは問題ではないでしょうか。
EUでは1989年からの輸入を禁止・・理由はホルモン剤・・・EUは2019年から禁輸を解き・・・ホルモン剤を使った牛肉は輸入禁止のままです(p13)
国産は収穫後に農薬をかけない
同じようにこの本が指摘するのは、マーガリンやショートニングを製造するときに、加熱と水素添加で生成されるトランス脂肪酸です。トランス脂肪酸を摂取すると、血管疾患やアレルギー、発がんのリスクが高まると考えられており、他国では摂取量の制限、含有量の表示などの規制がありますが、日本にはないのです。
また、輸入果物や野菜のほどんとに使われている収穫後にかける農薬(ポストハーベスト)も問題です。そもそも、国産の場合は収穫後に農薬をかけることは認められていません。アメリカ産のオレンジやレモンが半年たってもおいしそうなのは防カビ剤などの農薬のためなのです。この本では、輸入フルーツはなるべく避けるように推奨しています。
また、農薬のグリホサート(商品名ラウンドアップ)は、他国では規制され、血液のがんになったとする訴訟が米国などで多数起こされ、モンサント社(現バイエル社)が多額の和解金を支払うなど安全性が議論されているのです。
モンサント(バイエル)が自分たちに有利な規制緩和をさせたいとき・・自分の会社の幹部を規制当局の局長や長官として送り込む・・規制緩和させて、それが実現すると、会社に戻ってくる(安田 節子)(p14)
プラスとマイナスで許容範囲を考える
農薬で言えば、キャベツ、白菜、小松菜などは外葉に農薬が残留しやすいので、外葉を捨て、洗うことが普通になっています。
食品添加物では、アレルギーなどの問題で日本では認可されてこなかったコチニールがアメリカからの要望で認可されています。
気にしすぎなところもあると思いますが、実用面ではどこまでを許容範囲として認めるかということなのでしょう。
例えば、妊娠中の女性は水銀濃度の高い大型回遊魚(マグロ、カジキ、サメ、クジラ、シイラなど)を控えることをすすめられていいます。これは微量の水銀のデメリットと、魚介類を食べることのメリットのバランスで制限を決めているのです。
日本のイチゴを外国に輸出する時に農薬残留度が高すぎて、外国から受け入れ拒否されるケースがありますが、これも規制値の違いによるものなのです。
たくあんが黄色いのは伝統的な製法でも起こることですが、市販品の鮮やかさは・・石炭のコールタールからつくられるタール色素が使われています・・梅干しでさえ、同じくタール色素の赤が使用されることがあります(p54)
保険として安心できる食品を食べよう
お金に余裕があるのであれば、安心できる野菜や果物を私たちは保険として買うべきなのでしょう。例えば、アメリカで一番売れている商品は「USDAオーガニック」と遺伝子組み換えでないことを証明する「Non-GMOプロジェクト」であるという。
私たちにできることは、安心できる野菜を高くても買うことと、見た目のきれいさを気にせず、形や大きさはバラバラな野菜を許容するべきなのです。そうでないから、農家は野菜を売るために、農薬を使って見た目のよい野菜を作るしかないと思い込んでいるのです。
なお、本書の中で安田 節子さんが、「医療費は50年前の100倍にもなっています。食の劣化が健康問題を抱える人たちをたくさん生み出している」と主張していますが、医療費と食の劣化の因果関係は明確ではないと思います。
こうした感情的な主張を一つでもしてしまうとこの本の信ぴょう性が疑われるので、根拠のあいまいな主張はやめたほうがよいのではないかと感じました。
鈴木さん、印鑰さん、安田さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・「コロナ禍」「異常気象」「ウクライナ紛争」「中国人の買い占め」の理由から、食料が思うように手に入らない状況を「クワトロ(4つの)ショック」と呼びます(p83)
・作物は飼料や肥料、種苗などがなければ収穫できません。それらの必要な物資はほとんどが輸入頼り(p83)
・「カメムシ斑点米」・・味は変わらず有害性もありません・・ただ、一等米として許されるのは千粒中ひと粒まで・・・斑点米は機械ではじかれて流通するので農薬は必要なく、斑点米の等級は農薬を使用させる元凶(安田 節子)(p31)
・安全な食・・信頼できるお店・・・産地直送を利用する・・・自分でつくるといった方法があります(鈴木 宣弘)(p9)
▼引用は、この本からです

Amazon.co.jpで詳細を見る
鈴木 宣弘,印鑰 智哉,安田 節子(監修)、宝島社
【私の評価】★★★☆☆(76点)
目次
毎日の食がこんな危機的状況だった
加工品との上手な付き合い方
命を伸ばす食べ物
著者経歴
鈴木 宣弘(すずき のぶひろ)・・・東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授。「食料安全保障推進財団」理事長。1958年生まれ。三重県志摩市出身。東京大学農学部卒。農林水産省に15年ほど勤務した後、学界へ転じる。九州大学農学部助教授、九州大学農学研究員教授などを経て、2006年9月から東京大学大学院農学生命科学研究科教授、2024年4月から同特任教授。
印鑰 智哉(いんやく ともや)・・・日本の種子を守る会アドバイザー。1961年生まれ。東京大学文学部卒業。アジア太平洋資料センターに入社。ブラジル社会経済分析研究所、グリーンピース・ジャパン、オルター・トレード・ジャパン政策室室長等を経て、現在フリーの立場で世界の食の問題を追う。
安田 節子(やすだ せつこ)・・・1990年~2000年。日本消費者連盟で、反原発運動、食の安全と食糧農業問題を担当。1996年~2000年市民団体「遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン」事務局長。表示や規制を求める全国運動を展開。2000年「食政策センター ビジョン21」設立。環境政党「みどりの会議」副代表委員。NPO法人「日本有機農業研究会」理事
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!





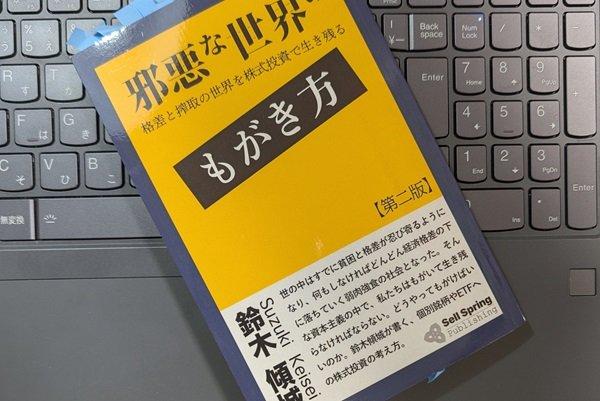




























コメントする