【書評】「職場の「やりづらい人」を動かす技術」秋山 進
2020/08/03公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(84点)
要約と感想レビュー
人にはタイプがある
著者はリクルートに入社し、新規事業を企画する職場にいましたが、先輩とは全く話が噛み合わなかったという。なぜなら、先輩は現場でどうするか(ミクロ)を重視し、著者は世界での成功事例は何かといった(マクロ)を重視していたからです。
また、先輩は自分の経験を重視し、著者は事実やデータを重視する。これでは噛み合わないのです。著者がそうした職場で踏ん張れたのは、リクルートが全社員を対象に性格検査を受けさせ、開示していたからだという。「先輩はS(現実重視タイプ)か。現実できなのはしゃーねーな」と納得できたのです。
私自身はもともと・・・マクロ×事実理論×WHATの「正しさを求めるコンサルタント」タイプだ。ところが、1980年代後半当時のリクルート社の現場は、圧倒的にミクロ×直感重視×HOWの「創意工夫の技能者」的なコミュニケーションが主流。つまり、私とはすべての点で根本的に真逆、早い話が「合わない」人だらけだったのである(p256)
人の性格を3つの点で分類
この本では、人の性格を3つの点で分類し、2×2×2=8通りに分類しています。
具体的には
【視点】(ミクロ、マクロ)×
【思考】(直感意味、事実論理)×
【行動】(WHAT、HOW)=8通り。
例えば、当時のリクルートでは、ミクロ×直感意味×HOW="創意工夫の技能者"が多かったのだという。本来は人のタイプは特徴であって良い悪いはないのですが、実際の職場では、タイプが違うと理解しえない、話が噛み合わないということになるのでしょう。
例えば、実務家から見た評論家はいい加減な人に見えるし、評論家から見た実務家は現場業務しかできない人に見えるのです。
ミクロを語りたい人とマクロを語りたい人は、いつもはっきり分かれている・・・マクロはミクロの人を「視野が狭い」とバカにし、ミクロはマクロの人を「机上の空論論者」とあざ笑って互いに相手にしない・・・そんなことをしているから、事業が衰退してしまう(p262)
感情的な対立を予防する
このようにビジネスパーソンのタイプを定義することで、異なるタイプの人との感情的イザコザを防げぎ、生産性高く協働できるという。組織としてメンバーの性格を把握して、それを活かそうという意識を持つことは大事だと思いました。なぜなら、ほとんどの職場では、性格の差も何もわからずに感情的な対立が起こることがあるからです。
8種類でなくとも4種類くらいにわけるだけでも、相互理解という点では大きく進歩すると思います。秋山さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・技能者から評論家を見ると、実現性の薄いことにうつつを抜かすほら吹きであり、役に立たない存在である。一方、評論家から技能者を見ると、どうでもよい小さなことに間違った方法でアプローチする厄介者である(p94)
・おっしゃるとおり、『我々がどうあるべきか』を決めることこそがもっとも重要な課題ですね。では、目先のこの問題を具体的にさっさと解決してしまった後に、本来の議論をしっかりやりませんか」・・・WHATからHOWへの切り替え・・相手のクセを把握したうえで、上記のような言葉を丁寧に投げかけてみると、相手は意外にも喜んで対応してくれるのだ(p158)
・C氏は・・・「頼りになる実務家」タイプだ・・・D氏は、・・・「時代を感じる評論家」である・・・C氏の実行力にD氏のコンセプト発想力が合わさると相乗効果を発揮・・・一時的にうまくいっても、組織の成長とともに、往々にして関係性が変わり仲違いで終わる・・・実際にはトップの成長にサブのほうが付いていけなくなることが原因で崩壊することも多い(p235)
【私の評価】★★★★☆(84点)
目次
第1章 職場の「やりづらい人」の正体
第2章 タイプ診断テスト―あなたのタイプはどれ?
第3章 「やりづらい人」を動かす技術
第4章 それぞれのタイプが輝けるフィールドはここだ!
終章 AIにも負けない人間の強みとは
著者経歴
秋山進(あきやま すすむ)・・・プリンシプル・コンサルティング・グループ株式会社代表取締役。リクルート入社後、事業企画に携わる。独立後、経営・組織コンサルタントとして、各種業界のトップ企業からベンチャー企業、外資、財団法人など様々な団体のCEO補佐、事業構造改革、経営理念の策定などの業務に従事。現在は、経営リスク診断をベースに、組織設計、BCP策定、コンプライアンス、サーベイ開発、エグゼクティブコーチング、人材育成などを提供するプリンシプル・コンサルティング・グループの代表を務める。
この記事が参考になったと思った方は、
クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓ ![]()
人気ブログランキングへ
| メルマガ[1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』] 3万人が読んでいる定番書評メルマガです。 >>バックナンバー |
| |
この記事が気に入ったらいいね!
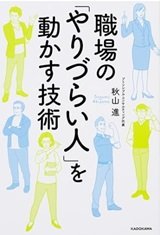


































コメントする