【書評】「信長の原理」垣根涼介
2020/07/14公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(87点)
要約と感想レビュー
なぜ信長は直属軍を作ったのか
織田信長の一生を描いた歴史小説です。歴史とは事象の流れですが、出演者の心の中を推測することで小説となるのでしょう。
なぜ、たわけ殿と言われていたのか。なぜ、信長は直属軍を作ったのか。なぜ、田楽狭間の戦いに勝てたのか。信長の心の中には、合理的な思考と自分の意思を突き通す自尊心とカッとなると手が出てしまう激情が渦巻いているようでした。
例えば、戦とは勝って、領地や利権や富を我が物にすることが目的であり、戦はそのための手段に過ぎないのです。戦は手段であるから、目的が達成できるのであれば、相手を根絶やしにしても問題はないということになるのです。
確かに僥倖(ぎょうこう)が重なって、やっとこさ義元の首を取ることが出来たのは事実だ。自分の戦略が際立って優れていたわけでもない。しかし、その幸運に向かって血の滲むような汗をかいてきた者にしか、九天神は微笑まないのだ・・・この一事が分からぬのか・・(p166)
信長は常に働かない二割を排除した
タイトルの信長の原理とは、蟻の法則です。つまり、懸命に働くのは二割の蟻。六割は手を抜きながら働き、残り二割は働かない。これは人間にも当てはまる法則であり、信長は常に働かない二割を排除して懸命に働く蟻だけにしようとしたのです。
また、指導者になる者の資質にも厳しいものがありました。愚かで軽率なものは外されたのです。愚かさや軽率さは直らないというわけです。このように優秀なものだけ残してきた織田軍ですが、最後には頭は切れるが、悪意を持った明智光秀に討たれることになるのです。
織田軍は二倍の大軍とはいえ、所詮は各地にいた部将の寄り合い所帯でしかない・・・実際の戦意はさらに心もとない。蟻の法則だ、と秀吉は改めて思う。普通なら二割しか懸命に働かない蟻(p399)
人の心を無視した人事は合理的でない
信長は合理的な考え方により、商業と軍事を強化し、金と武力でほぼ天下を統一しました。しかし、その合理性を極めた、「昇進か脱落か」という人事が光秀の裏切りをもたらしたのかもしれません。
組織は人で作られていますので、信長は合理的と思っていましたが、人の心を無視した人事は合理的ではなかったのでしょう。垣根さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・お父(でい)の言う通りだ。この世を動かしているのは商人なのだ。武士ではない・・・商人と懇意にし、この富をもたらす湊を押さえている限り、戦費はいくらでも調達できる。そして戦費が調達できる限り、どんなに苦しい戦いでも最後には勝つ(p13)
・秀吉は非常に気前が良く、常に陽気で鷹揚な人間だと織田家中では思われているが、その実は、まったくそんな人柄ではない。必死に闊達な自分を演じ続けているだけだ。出自と言える出自もろくになく、矮小で容貌も醜い。戦場に出ても槍働きひとつ満足にこなせない。そんな人間が世間で人並みに相手にされていくには、そして、組織の中で立身していくには、可能な限りの愛想の良さを自分から演出してゆくしかなかった(p400)
・五部将のうちの裏切る蟻は、家康ではなく、光秀であったか・・・しかし、何故だ。あんなに厚遇してやっていた光秀が、何故このおれを裏切る・・「余は、自ら余の死を招いたな」(p581)
【私の評価】★★★★☆(87点)
著者経歴
垣根 涼介(かきね りょうすけ)・・・1966年長崎県生まれ。筑波大学卒業。2000年『午前三時のルースター』でサントリーミステリー大賞と読者賞をダブル受賞。2004年『ワイルド・ソウル』で、大藪春彦賞、吉川英治文学新人賞、日本推理作家協会賞の史上初となる3冠受賞。その後も2005年『君たちに明日はない』で山本周五郎賞、2016年『室町無頼』で「本屋が選ぶ時代小説大賞」を受賞。
この記事が参考になったと思った方は、
クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓ ![]()
人気ブログランキングへ
| メルマガ[1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』] 3万人が読んでいる定番書評メルマガです。 >>バックナンバー |
| |
この記事が気に入ったらいいね!
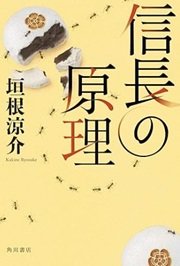



































コメントする