【書評】「ボーイング 強欲の代償―連続墜落事故の闇を追う」江渕崇
2025/05/07公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(85点)
要約と感想レビュー
ボーイング737MAX8の連続墜落事故
2018年10月にインドネシアのライオン・エア、2019年3月にエチオピア航空が運航するボーイング737MAX8が墜落し、346人が犠牲となりました。その原因は、機体の角度を測定する迎え角センサーに異常があると、水平尾翼が自動で動き強制的な機首下げが続くことでした。
これは、加速時など機首がのけぞり上を向き過ぎると、機体が失速して墜落しまうのを防ぐため、自動的に水平尾翼を下げるという操縦特性増強システム「MCAS」(エムキャス)によるもので正常動作だったのです。
問題は、「MCAS」についてパイロットが読む運航マニュアルの本文に記載せず、アメリカ連邦航空局(以下FAA)に対しても「MCAS」の動作量や作動条件を過小申告して、パイロットへの追加訓練が行われないようにしていたことです。
つまり、古い機体に大きなエンジンを取り付けたために機体の重心が変わり、機体が不安定になったため、ソフトウエアで自動で補正しようとしたが、それをマニュアルに載せず、パイロットの訓練が必要と知りながら、面倒なので訓練しないようにFAAに嘘をついていたというわけです。
MCASによって水平尾翼は最大2.5度も動くというのに、ボーイングは最大でも0.6度しか回転しないとFAAに報告していた・・MCASが起動する最低速度などの条件も、FAAに明確に知らせないまま緩められていた。MCASがパイロットの意図と関係なく何度でも起動し、機首下げを生じさせることも、FAAに伝えていなかった(p35)
ボーイング社内の葛藤
裁判で明らかになったボーイング社内の通信記録では、コスト削減とスケジュール順守を強いられる社内の様子がわかるものでした。
例えば、パイロットの訓練については「いかなるシミュレーター訓練も(FAAに)要求させはしない。ボーイングはそんなことは許さない。それを要求しようとする、どんな規制当局にも立ち向かう(2017年3月28日)」と意図的に安全のための訓練をさせないようにしていたことが明確です。
それに対し、現場の技術者からは、「君は家族をMAXのシミュレーターで訓練された航空機に乗せるか?自分なら乗せない」(2018年2月8日)という嘆きの声もありました。
同じように批判的な人は、「この飛行機を設計したのは道化で、そいつらは今度はサルたちに監督されているんだ」(2017年4月26日)と技術者を「道化」、FAAを「サル」と表現したものもありました。ちなみに日本の国土交通省航空局は、「まだ石器時代で止まっている」という評価だったという。
ボーイングにとって、737MAXを売り込むためには、パイロットの追加訓練は避けたいものだったのです。
「これらをどう解決すればいいか分からない・・経営陣はビジネスをほとんど知らないくせに、明確な目標だけは押しつけてくる」(ボーイング社内の通信記録)(p70)
アメリカ航空業界の実態
著者の取材では、規制当局のFAAと航空業界のボーイングは癒着していることを指摘しています。
まず、アメリカ運輸省監察総監であったメアリー・スキアヴォは1997年の著書「危ない飛行機が今日も飛んでいる」の中で、FAAは航空業界と癒着して、本来の任務を見失い、事故を招きかねないと警告しています。
また、ボーイングによる「セルフ認証」に関わった航空機認証専門技術者は、ボーイングの上司から、認証できない部品について「君はこれをただちに認証するか、さもなければ、職を失うかだ。席に戻って、どうすれば認証できるかを考えろ」と脅され、実際に解雇されたという。
同じように、検査官がボーイングの問題に気づき、それを指摘すると、ボーイングがFAA上層部や有力政治家に働きかけ、その検査官は審査から外され、後任は「物分かりの良い」検査官が充てられるというのです。
つまり、FAAは規制当局でありながら、ボーイングと一体であり、三菱重工の認証も遅らせて邪魔したというのが、実態らしいのです。
「厳しいがフェアな競争社会」というアメリカのイメージは、私の観察とは違う・・もっともらしい理由をつけて不合理な規制を当局に設けさせるなどし、日本企業などのライバルの邪魔する実例を、私は日本人駐在員から聞かされた(p174)
ボーイング変質の原因
こうしたボーイングの安全を無視した航空機開発の背景には、リストラを行うことで数十億円の報酬をもらう経営陣の変質にあったと著者は推定しています。
そのきっかけは、1997年にボーイングがマクドネル・ダグラスを買収したことです。マクドネル・ダグラスを潰した愚かな経営者ハリー・ストーンサイファーが、合併後のボーイング社長兼最高執行責任者(COO)になったのです。ストーンサイファーは、GEでウェルチの薫陶を受けた一人であり、その後のボーイングCEOに就いたのも、GEでウェルチの右腕だったジェームズ・マックナーニでした。
ボーイングは、マクドネル・ダグラスと同じように人を削り始め、合併時に24万人いた従業員は、8年後には15万人まで減ったのです。投資は抑え込まれ、開発や生産も下請けへ、海外へと外注されていったという。その過程で、ボーイングの安全優先の文化が消えたというわけです。
確かに経営者によって、会社は変質してしまうのだと思いました。そういえば著者は朝日新聞記者です。朝日新聞の闇も、同じように追っていただきたいものです。江渕さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・電気機器を供給するサプライヤー・・エアバスは細部にわたる膨大な説明資料を用意していた・・一方、古巣のボーイング。・・丸投げしてきた・・・ボーイングがつけてきた担当者は、たった1人だった・・以前のボーイングなら、その電子機器のためにエンジニアが20~40人はかかわっていた(p127)
・白紙から新型小型機を開発するには100億ドル規模、つまり1兆円超がかかるといわれる。ボーイングが白紙から小型機を作る計画を捨て去り、既存機種の改良でしのごうとした理由の一つは、コストの大きさだった(p79)
・ウェルチが引退して2年後の2003年、ウォールストリート・ジャーナルがGE出身の経営者たちのパフォーマンスを調べたところ、彼らは就任後、軒並み3~4割も株価を下落させていた。一方で、年に数十億円単位の報酬、さらに巨額の退職金を得ていた(p147)
▼続きを読む
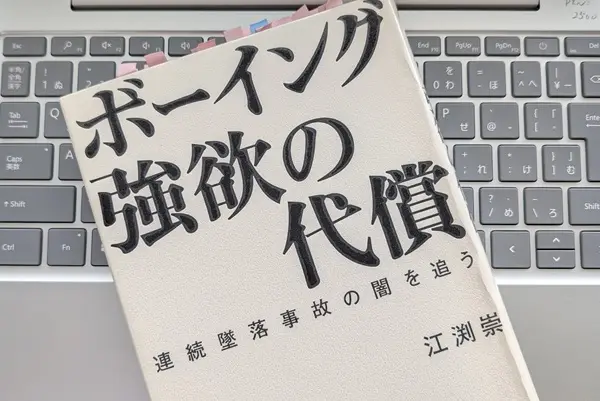
Amazon.co.jpで詳細を見る
江渕崇(著)、新潮社
【私の評価】★★★★☆(85点)
目次
第一章 慟哭のアディスアベバ
第二章 魔のショートカット
第三章 キャッシュマシン化する企業
第四章 シアトルの「文化大革命」
第五章 軽んじられた故郷、予見された「悪夢」
第六章 世紀の経営者か、資本主義の破壊者か
第七章 「とりこ」に堕したワシントン
第八章 フリードマン・ドクトリンの果てに
第九章 復活した737MAX、封印された責任
第十章 株主資本主義は死んだのか
終章 「空位の時代」をゆく日本の海図
著者経歴
江渕崇(えぶち たかし)・・・朝日新聞記者。1976年、宮城県生まれ。1998年、一橋大学社会学部を卒業し朝日新聞社入社。経済部で金融・証券や製造業、エネルギー、雇用・労働、消費者問題などを幅広く取材。国際報道部、米ハーバード大学国際問題研究所客員研究員、日曜版「GLOBE」編集部、ニューヨーク特派員(2017~2021年、アメリカ経済担当)、日銀キャップ等を経て2022年4月から経済部デスク。2024年12月現在は国際経済報道や長期連載「資本主義NEXT」を主に担当している。
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!

































コメントする