【書評】「日本の水道をどうする!?: 民営化か公共の再生か」内田 聖子
2020/07/19公開 更新
Tweet
【私の評価】★★☆☆☆(69点)
要約と感想レビュー
他国での失敗事例
日本の水道事業は公営が多いのですが、2018年の水道法改正で運営を民間企業に委ねるコンセッション方式が選択できるようになりました。
人口減少に伴い自治体は財政に余裕がなくなり、赤字の水道事業を維持できなくなっているのです。敗戦後に一気に建設された水道インフラ整備は、人口が右肩上がりに増える社会を想定して大きめに作られていました。人口減少が進むなか、かつて建設した大規模なダムや多数の浄水場の維持コストに自治体が困っているのです。
水道事業の赤字対策は、民営化しかないのですが、この本では、基本的に水道の民営化には問題があるという視点でまとめられています。前半では民営化で先行した他国での失敗事例を羅列することで、民営化の問題点を指摘しています。
ブエノスアイレス市・・・水道料金はたびたび値上げされていく。契約後7年間で45%も値上がりし、その後も年4%の値上げが続き、市民の激しい抗議運動が起きた(p18)
他国での失敗事例
そもそも公営の水道は赤字でも税金で穴埋めできましたが、少子高齢化で自治体はその負担に耐えられないというのが本質なのでしょう。確かに民営化にすれば問題は発生するでしょう。しかし、それは民営化により問題が発生したのではなく、税金で補填できないから問題が目に見えただけなのです。
著者が指摘するように、ジャカルタ市の水道水は直接飲むことができないにもかかわらず、水道料金は東南アジア諸国で最も高いのでしょう。災害による断水が起こったとき、公であれば即座に「給水車を出そう!」と判断できますが、民間企業が運営に全面的な責任を負っている場合は課題になるかもしれません。
それでも水道事業の赤字は解消されなければ、水道事業そのものの持続可能性がなくならないのです。
マニラウォーター社・・・給水人口は5年間で30%増加し、給水率は1996年の61%から2001年には80%を超えた・・・漏水パイプの修理は滞り、無収水率に大きな改善はない。また、事業者の収入不足を補填するために相次いで水道料金が引き上げられ、その負担に耐えられない貧困層が盗水をするという悪循環も発生している(p30)
赤字であれば民営化しかない
公営で資金を回せないのであれば、民営化しかないわけです。民営化の良いところは、収支が明確となり、その責任が明確になることでしょう。つまり、費用がかかるのであれば、料金が上がる。リスクのあるコスト削減を行なえば、うまくいけば自分の利益であり、失敗すれば自分の責任であるということです。
失敗しても何も問われず、税金が補填してくれる公営には限界があるように感じました。内田さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・1990年代に入り、IMFと世界銀行は途上国への新規融資や債務削減の条件として、国や自治体が担う水道事業などの民営化を構造調整プログラムの一環として押し付けてきた・・・その背後には・・・グローバル企業の意向がある(p12)
・鉛汚染との闘い・・ピッツバーグ市(米国)・・・公共水道機関は2014年4月に、鉛などの重金属を水道水から除去する化学薬品を炭酸ナトリウムから安価な苛性ソーダに変えた・・・水道水中の鉛濃度は、ヴェオリア社が水道供給を受託する前から少しずつ上昇していた・・・・安全基準は15ppbで・・・2013年には14.8ppb、2016年6月には22ppbにまで上昇(p72)
・食と水ウォッチによると、プライベート・エクイティ・ファンドは年間12~15%の投資収益を目標にしており、通常10年以内に資産を売却する(p77)
・PFIの手法は、公共サービスの民営化を率先して進めてきた英国で生み出された。1980年代のサッチャー政権下で、水道、電気、石油、ガス、鉄道、航空などが民営化されていく(p103)
・公営であっても、短期間で職員を異動させていては技術とノウハウの蓄積は期待できない。加えて、各地でこの十数年近く、若手職員の採用がほとんどない。1980年代以降の約30年間で、約30%の職員が全国で削減されている(p198)
・筆者が採用された1985年ごろは、「水道一家」という言葉があった。採用から退職まで水道部門で働く事業体が多かったのだ。しかし、一般部局との人事交流、法体系や経営、技術の違う上水道と下水道を統合した人事交流が3~5年で行われるようになり、生え抜きの職員が育たなくなった(p218)
【私の評価】★★☆☆☆(69点)
目次
第1章 世界の水道民営化の30年 内田 聖子
第2章 公共サービスの再公営化が世界のトレンド 岸本聡子
第3章 世界と逆行する日本の政策
第4章 民営化が懸念される自治体
第5章 「公共の水」をどう維持し、発展させるか
著者経歴
内田 聖子(うちだ しょうこ)・・・1970年生まれ。NPO法人アジア太平洋資料センター(PARC)共同代表。出版社勤務などを経て2001年よりPARCに勤務。TPPなどのメガFTAやWTOなどの自由貿易・投資協定のウォッチと調査、提言活動、市民キャンペーンなどを海外の市民社会団体とともに行う
この記事が参考になったと思った方は、
クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓ ![]()
人気ブログランキングへ
| メルマガ[1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』] 3万人が読んでいる定番書評メルマガです。 >>バックナンバー |
| |
この記事が気に入ったらいいね!
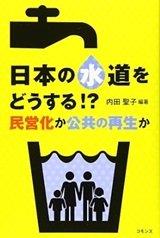

































コメントする