【書評】「ウィーン世紀末の文化」木村 直司
2020/03/28公開 更新
Tweet
【私の評価】★★☆☆☆(63点)
要約と感想レビュー
19世紀末のウィーン
日本とオーストリアの修交120周年記念(外交関係は1869年に始まった)に上智大学で開催されたシンポジウムの内容をまとめた一冊です。19世紀末のウィーンはクリムトなど官能的な芸術、アール・ヌーボーと言われる新しい様式が出てきた時代。固い内容ですが、歴史を振り返るのに良い本だと思いました。
当時のオーストリアは、ハプスブルク王室フランツ・ヨーゼフ皇帝の在位期間(1848~1916)が長く、「天下泰平」ムードが漂っていたという。その一方で、ユダヤ人排斥の空気、ブルジョワと労働者階級の対立、産業革命による貧富の格差拡大など社会の矛盾も大きかったのです。社会とはだんだんと変わり、良くなっていくものだと感じました。
1893年頃には、医学生の48%、681人いた弁護士のうち394人、ジャーナリストの42%がユダヤ人で占められるまでになっていた。また1914年までには、商業に従事する者のおよそ60%がユダヤ系であったとも指摘されている(p183)
花開くウィーン文化
ウィーンでは19世紀末のわずか数十年間に哲学(ヴィトゲンシュタイン)、社会学(シュッツ)、経済学(メンガー)、法学(ケルゼン)、心理学(アトラー、フロイト)、民族学(シュミット)、音楽(シェーンベルク、マーラー)、建築・美術(ワーグナー、ホフマン、ロース、クリムト)、文学(クラウス)、世界政治(シオニズムの理論家ヘルツル、ヨーロッパ統合論者クーデンホフ・カレルギ)等が活躍するのです。
19世紀末の芸術様式は、一般にフランス語で「アール・ヌーヴォー」(当たらしい芸術)、ドイツ語で「ユーゲントシュティール」(青春様式)、「英語で「モダン・スタイル」(近代様式)、そしてスペイン語で「アルテホベン」(若い芸術)と呼ばれています。
世紀末ウィーンの音楽状況については、マーラーがウィーン宮廷歌劇場(現在の国立歌劇場)の芸術監督に在職した期間、つまり1897年から1907年にかけての十年を中心に語られることが多い・・・新旧の音楽が交錯する過渡期の時代だった(p156)
社会の変化
都市への人口流入によって、ウィーンの住宅事情は悪化し労働者階級の生活は貧困化しました。中流以下の小市民層を基盤にしたキリスト教社会党がリベラル・ブルジョワジーを破り、1895年から1918年まで政権を握っています。
19世紀末のウィーンでは、クリムトが官能的な芸術で上流社会の婦人たちに奉仕しましたが、工場では若い女中や子供を抱えた女工たちがいたのです。貧しいウィーンの女工たちが、労働時間の12時間から10時間への短縮や、5月1日のメーデーへの参加制限の解除などを求めて、初めてストライキに立ち上がったのは1893年のことです。
木村さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・あらゆる文化価値にとって共通の試練は第一次世界大戦であった。この戦争を契機にして19世紀を支配していた主要な価値が大きく後退した。すなわち進歩の観念、理性への信頼、科学技術への信仰などである。19世紀が本当に終わったのは1918年だという見方も成り立つ(p5)
・学校では義務教育の期間中、宗教は必修科目であった。宗教の時間にはクラスが宗派別に分かれてしまう・・・ローマ・カトリック、プロテスタント、チェコスロバキア教団、ユダヤ教、無宗教・・(p57)
・進歩系の新聞では、新人の文学者たちは反ユダヤ主義傾向をもっていると批判され、保守系の新聞では、かれらのなかにはユダヤ人が多すぎる、と書かれた。いずれにせよ、自然主義の枠のなかで見られていた若きウィーンの連中にはまだ活動の場がほとんど与えられなかった(p8)
・世紀末オーストリアでのユダヤ人排斥運動の理由として、シェーネラーたちの人種差別的な憎悪の他にユダヤ人の富とその富に由来する絶大な社会的影響力が挙げられる。貧富の差の激しい社会の中で搾取されていた労働者たちはユダヤ人の中に憎い資本家の原型を見定めていた(p64)
【私の評価】★★☆☆☆(63点)
目次
世紀末文学の文化的パトス
思想の運命・都市の運命
世紀末ウィーンの宗教的・思想的状況―われらオーストリア人の生い立ち
フロイトとウィーン
世紀末「ウィーンの近代建築」の成立をめぐって
世紀末ウィーンの美術―あるいはクリムトの蛇
陽気なミューズの世紀末―世紀転換期ウィーンのオペレッタとキャバレー
世紀末ウィーンの日陰
シュニッツラーの描く女性たち
ウィーンにおけるゲーテ・ルネサンス
著者経歴
木村 直司(きむら なおじ)・・・1934年札幌生まれ。1965年ミュンヘン大学Dr.phil.現在、上智大学名誉教授。ドイツ文芸アカデミー通信会員、ウィーン文化科学研究所(INST)副会長
この記事が参考になったと思った方は、
クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓ ![]()
人気ブログランキングへ
| メルマガ[1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』] 3万人が読んでいる定番書評メルマガです。 >>バックナンバー |
| |
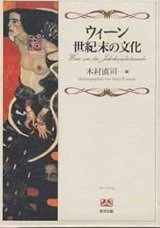

































コメントする