【書評】「額縁のなかの女たち「フェルメールの女性」はなぜ手紙を読んでいるのか」池上 英洋
2025/08/11公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(74点)
要約と感想レビュー
キリスト教は女性蔑視
女性の立場というものが、歴史の中でどのように変わってきたのか、名画とともに解説する一冊です。
まず、古代ローマでは女性に結婚を申し込むためは、経済力が必要とされていました。女性を羊と交換して妻とするような売買婚もなされていたという。
その後、西ローマ帝国がゲルマン民族の侵入によって滅ぼされ、各地に部族ごとの国家ができますが、すべてがキリスト教に改宗することでキリスト教が女性観を形作ることになるのです。旧約聖書には、女性蔑視の文言が記されており、ユダヤ教、キリスト教、ユダヤ教を母体として生まれたイスラム教では、女性蔑視の傾向が際立つことになったのです。
中世ヨーロッパでは、キリスト教の影響で性行為を悪しきものとみなしていました。例えば、11世紀のドイツで書かれた「贖罪規定書」には、性行為は祭日と水曜と金曜から日曜までしてはならず、全裸ではダメ、正常位以外はダメ、一晩に二回以上はダメ、愛撫やディープ・キスはダメ、性行為を楽しんではダメだったという。
当時の強烈な階級意識・・・ダンテ・アリギエーリにとってのベアトリーチェや、フランチェスコ・ペトラルカにとってのラウラ・・彼ら二大詩人は、いずれも若い頃に高貴な女性を見初め、他人の妻となったあとも彼女たちに精神的な愛を捧げ、詩作の際に霊感を与えてくれる「ミューズ(詩神)」として遇した(p84)
商売で女性の識字率が上がる
14世紀頃となると、東方との貿易と物流が活発化し、遠方の異民族との取引が金貨や銀貨で行われました。貨幣を流通させるために銀行業が必要となり、イタリアのフィレンツェ周辺で両替をするという名目で利子を得る「両替商」が生まれました。
家族経営である「両替商」では妻や娘も商いの貴重な担い手であり、それまでにみられなかった家庭内での女子への教育が始まったのです。もちろん普通の家では、息子が読み書きを習って、娘は母と同じ糸紡ぎをしている画が残っているように女性の地位は低いままなのですが、少しずつ文字を読める女性が増えていったのです。
その一方で、ヴェネツィアでは、宮廷の娼婦こと「コルティジャーナ」がおり、宴席を盛り上げるような技芸と教養を積んだ女性たちもいたのです。ヴェネツィアでは、女性の十人に一人がなんらかの形で売春業に携わっており、1403年にはフィレンツェで公営売春宿を管理する部署が政府内に設けられました。
「両替商」なる職業だが、お金を貸して利子を取る、実質的には銀行の初歩段階・・旧約聖書では利子をとる行為が禁じられていた・・・宗派が違う相手であればよい・・ユダヤ人だけが金貸しを営んで長年蓄財でき、ロスチャイルド家などの超富裕層が生まれた(p96)
アジアとの交易で郵便が始まる
16世紀になって、カトリックからプロテスタントが分裂すると、ローマ・カトリック教会は信徒の半数を失い、文化の中心地はイタリアからフランスへと移っていきます。そして、17世紀になるとイギリスとオランダが東インド会社を設立し、アジア貿易を独占するようになりました。
フェルメールが生まれたのはオランダの街デルフトで、フェルメールの絵の壁に世界地図が掛けられているのは必然なのです。遠方との交易のために郵便システムが始まり、オランダ市民の多くが文字を読み書きする必要性がありました。
つまり、フェルメールの「手紙を読む青衣の女」で女性が手紙を読んでいるのは、普通の女性が文字を読み書きすることができたという、当時のオランダ発展の証拠なのです。
魔女裁判を含む異端審問は、16世紀半ばから急激にその件数が増加した・・プロテスタント勢力が分裂していった時期と重なっている・・魔女狩りは20世紀初頭まで続いた・・累計で数百万人もの女性が処刑された(p149)
自由な市民社会の誕生
19世紀末になると、社会は工業化し、安定的に収入を得られる人が増え、自由な市民社会が増えていきました。スーラの「グランド・ジャット島の日曜の午後」を見ると、川辺を散歩する人や、座ってのんびりする人がいたりと、日曜の午後の自由な市民社会が描かれています。
また、伝統を重視するサロンに対し、印象派やジャポニズム、アール・ヌーヴォーなど新しい表現が提案されました。パリは芸術の中心地と言われ、パリのモンマルトルのアトリエに世界中から画学生や芸術家が集まったのです。日本からだけでも500人もいたというのですからすごいことです。
挿絵の絵画を見るだけでも楽しい一冊です。池上 さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・紀元前4世紀のアテナイで活動したプラクシテレスは、フリュネという女性を好んでモデルに使った・・フリュネは古代ギリシャの高級娼婦であるヘタイラのうち、最も成功をおさめた女性として知られる(p44)
・富裕層の母親は生まれたばかりの子どもに母乳を与えなかった。女性の体は授乳中には生理が来ないが、断乳すると産んだ子が亡くなったと自動的に判断でもするかのように生理が戻ってくる。こうして女性は一生のうちに何度も妊娠する(p66)
・1865年のサロンに入選したエドゥアール・マネの「オランピア」は、スキャンダルをまき起こした・・・2年前の1863年のサロンには5千点の応募があり、3千点もの落選作品が出た・・・「落選者展(サロン・デ・レフュゼ=拒否された者の展覧会)」が大々的に開催された(p210)
▼引用は、この本からです
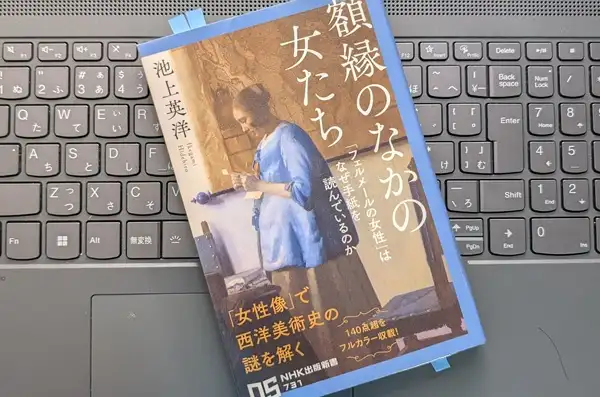
Amazon.co.jpで詳細を見る
池上 英洋 (著)、NHK出版
【私の評価】★★★☆☆(74点)
目次
第1章 古代―大地母神と女性イメージの形成
第2章 中世―聖母とキリスト教的モラル
第3章 ルネサンス―女神の復活と聖母の変容
第4章 近代―ありふれた女たち
第5章 近代以降―印象派から第二次世界大戦前まで
著者経歴
池上 英洋(いけがみ ひでひろ)・・・美術史家。東京造形大学教授。1967年広島県生まれ。東京藝術大学卒業・同大学院修士課程修了。専門はイタリアを中心とした西洋美術史・文化史。
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!
































いつも有難い情報をご提供頂き、ありがとうございます。
手紙を読む女性は識字率が高い(それまでは身分の低い扱い)という視点、日本では識字率の高さをあまり意識していない事に改めて気づきました。
古今和歌集など「詠み人知らず」の和歌でも女性や身分の低い人の句が掲載されており、また日記、源氏物語も早くから女性が文字を理解していました。
江戸時代の洒落本など大衆紙に当たるものも刊行されており、これらも日本の識字率の高さを示すもの、と考えます。
欧米諸国よりも早くから男女が「対等」であり、戦のない300年近くの平和な時代を経験している日本は素晴らしい、と再認識しました。
拙い長文、失礼しました。
今後も益々のご活躍を祈念しております。