【書評】「ヘッドハンターが教える 次世代トップリーダーの座標軸 人間力を高める経営の心得とは」古田 英明
2025/07/30公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(73点)
要約と感想レビュー
経営者の評価基準
経営幹部専門のヘッドハンティング会社縄文アソシエイツでは、上場企業の役員評価を行っているという。私も本の評価を行っていますが、失礼な話です。(笑)
役員の評価基準は、結果を出せる職務遂行能力と、人間性・人望・人間的魅力であるという。本でいえば、書籍の内容と著者の人格ということでしょうか。
経営者は誰にも正解がわからないなかで決断し、その責任を一身に引き受けなければなりません。また経営者は、人を動かす仕事であり、人の心をつかむことができるのか試されるのです。
企業活動とは、「人間によって」「人間のために」行われている活動です。そこに、合理性や効率性を超えた「人の心」や「人間性」といった要素を取り入れるべき理由があるわけです(p90)
経営幹部が学ぶべきこと
縄文アソシエイツでは、経営幹部候補を対象としたリーダーを育成する「縄文塾」を開催しています。もともとは、安岡正篤先生の子息である安岡正泰氏を講師として、安岡正篤先生の著作の輪読会を行ったのがはじまりだという。
そして、何を教えているのかといえば、「論語」などの古典や、「武士道」や「禅」といった日本の精神文化を中心に学んでいるという。この本では人が育つには、人と出会うこと、本を読むこと、旅に出ること(転職含む)と説明しています。
人と人が出会うことで人は磨かれていくものです(p29)
5%リーダーとは
この本では、理想の経営幹部を「5%リーダー」と表現しています。「5%リーダー」は他の95%を支えるだけの能力、志、覚悟を持った人物だというのです。
日ごろから、各部署・各分野の情報収集により先見性を持ちながら、実務での決断と指導によって組織の成果を生みだしていくのです。縄文アソシエイツが探している「5%リーダー」は補佐官ではなく、あくまで大将なのです。
「この人の言うことなら」と思わせるだけの人間的魅力を感じるリーダーでなければなりません(p50)
経営幹部の事前評価は難しい
会社の経営幹部の能力を事前に評価することは非常に難しいし、見極めるのは困難ではないかと感じました。どちらかといえば、縄文アソシエイツが行っている上場企業の役員評価が正しかったかどうかのほうが、その会社の業績がどうなったかで測定可能ではないでしょうか。
つまり経営幹部としての適正があるのかないのかは、やらせてみないとわからないのです。やってみた結果は測定可能なのです。古田さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・私はこれまで「30歳までは転職厳禁」と主張してきました。何か一つのことで一人前になるためには、少なくとも7~8年はかかります(p30)
・物事をどうやって解決するかは、最終的には自分で考え、自分自身で答えを出すほかありません。問われているのは、正解が何かではなく、自分はどうするのか、ということです(p67)
・「なぜこの事業を行うのか」「何のためにこの会社はあるのか」・・・企業には必ずの根本命題と向き合う瞬間がやってきます(p89)
▼引用は、この本からです
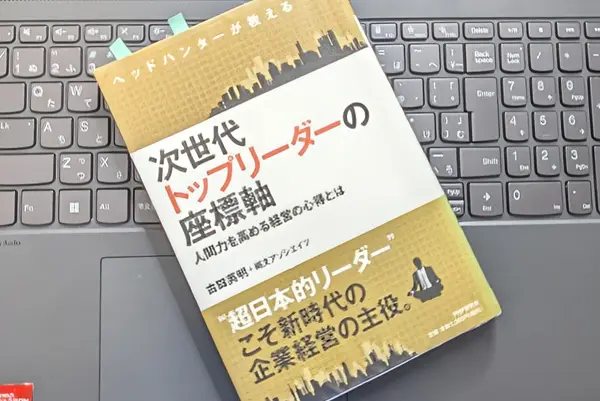
Amazon.co.jpで詳細を見る
古田 英明 (著)、PHP研究所
【私の評価】★★★☆☆(73点)
目次
序章 日本を支える真のリーダーとは
第1章 リーダーに何か必要か
第2章 人を動かす
第3章 組織を育む
第4章 経営の基本
第5章 心をつかむ
第6章 社長業の妙味
著者経歴
古田 英明(ふるた ひであき)・・・縄文アソシエイツ株式会社代表取締役。1953年生まれ。1976年に東京大学卒業。神戸製鋼所で東南アジア、中近東での企画・販売業務に携わる。野村證券では、資本市場部、営業企画部で引き受けおよび企画業務などを担当。1996年にエグゼクティブサーチ会社「縄文アソシエイツ」を設立
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!
































コメントする