【書評】「江戸の天文学 渋川春海と江戸時代の科学者たち」中村 士
2024/06/10公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(79点)
要約と感想レビュー
渋川春海が大和歴を幕府に提出
江戸時代の天文学上の事件は、1684(貞享元)年の渋川春海が作成した「大和歴」(正式には貞享(じょうきょう)歴)への改暦決定でしょう。「大和歴」は中国で1644年まで使われていた「授時歴」を基にしたもので、中国と日本の位置の違いを補正した精度の高いものだったのです。
それまで日本では、平安時代862年に採用された唐の「宣明歴」が使われていました。遣唐使の廃止(894年)により中国の新しい歴法が輸入されず、歴の改良も行われなかったため、江戸時代の初めには、実際の日時と2日程度ずれていたという。
改暦にあたって、渋川春海と対立したのは、既得権を持っていた朝廷の陰陽家である土御門(つちみかど)家です。渋川春海は元(中国)の「授時歴」に、日本と中国の「経度差」を補正した「大和歴」を幕府に提出。一方の土御門家は、「授時歴」の次の明(中国)の「大統歴」を主張したのです。
1617年、二代将軍・秀忠は朝廷から家康に「東照大権現」の神号を賜ったお礼に、京都へ上り天皇に謁見しようとした際、・・当時、幕府は三島歴、朝廷は京歴というようにそれぞれ異なる歴をつかっていたため、日にちの認識が違っていた(p40)
大統歴ではなく大和歴の採用が決定
貞享元年(1684年)の改暦では、陰陽頭であった土御門 泰福(つちみかど やすとみ)が、「大統歴」での改暦を進めようとします。
当時の将軍綱吉は、水戸藩の徳川光圀に内密に大統歴と大和歴の優劣を観測によって実証させ、大和歴の正確さを確認しようとしたという。また、土御門 泰福も渋川春海と太陽の影の長さや、月や惑星の観測を行い、大和暦の正確さを確認し、最終的には大統歴ではなく、大和歴の採用が決定したのです。
渋川春海の「大和暦」が採用されたのはその正確性だけでなく、碁の先生として徳川家の実力者に一目置かれ、信頼されていたことが大きいと言われています。
1684年に霊元天皇によって採用されかけた新しい歴は中国の明でつかわれていた「大統歴」だった。その理由は、大和歴のベースである授時歴はかつて日本を侵攻した元の歴であることから好ましくない、という土御門(つちみかど)側の非科学的な主張によるものである(p29)
ラランデ天文書を解読した高橋至時
印象的だったのは、渋川春海の弟子である高橋至時(よしとき)が、パリ天文台長のラランデが1764年に出版した「ラランデ天文書」5冊を半年で解読したということです。そして、「ラランデ歴書管見」という解読書11冊にまとめて出版します。しかし、その翌年に結核のため高橋至時は、41歳で亡くなっているのです。
最先端の科学に接し、寝食を忘れて解読した高橋至時の興奮と、若き41歳で生を終わらなくてはならい運命の無念さを感じました。また、現代社会でも既得権者の抵抗は大きいものがありますが、それは組織の必然であり、その中でも正しいことを主張して採用していく環境が大事なのだろうと感じました。中村さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・ラランデ天文書・・日食や月食、惑星について述べている以外にも、地球は単なる丸い球体ではなく「楕円体」であることが記されて・・(p113)
・麻田剛立はオランダから輸入した初めてのグレゴリー式反射望遠鏡をつかい、それまで日本人が誰ひとりとしてみたことのなかった月面クレーターを発見した(p104)
・1800年から始まった第一次測量の蝦夷地観測の旅は往復3200キロメートルの道を一定の歩幅で歩くことで距離を測る「歩測」によっておこなわれた(p136)
【私の評価】★★★☆☆(79点)
目次
第1章 江戸天文ブームの先駆け、渋川春海
第2章 江戸天文学のパトロン、天文将軍・徳川吉宗
第3章 なにわの天文学者、麻田剛立とその弟子たち
第4章 地方で活躍した技術者・研究者
第5章 幕末に活躍した天文学者たち
著者経歴
中村 士(なかむら つこう)・・・1943年生まれ。東京大学理学部天文学科卒業後、同理系大学院博士課程修了。理学博士。国立天文台に入所し、微小小惑星の探査研究を行う傍ら、江戸時代の天文学を研究。現在、帝京平成大学教授、文化庁文化財審議専門委員。著書は『江戸の天文学者星空を翔ける』ほか。
渋川春海関連書籍
「天地明察」冲方 丁
「江戸の天文学 渋川春海と江戸時代の科学者たち」中村 士
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!
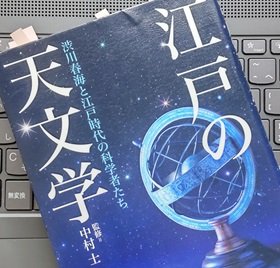

































コメントする