【書評】「日本語が亡びるとき: 英語の世紀の中で」水村 美苗
2024/06/07公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★★(90点)
要約と感想レビュー
国語とは何か
この本の前半は、アイオワ大学主催の「世界の作家たちとの国際交流」の1ヶ月の体験が綴られています。その国際交流から伝わってくるのは、「国語」というものが、いかに大切で、いかに脆いものであるのかということです。
例えば、ソビエトが崩壊したとき、ウクライナはすでにロシア語を使う人の方が多くなっていたにもかかわらず、ウクライナ語を公用語としました。今のアイルランドの第一公用語は、アイルランド語(ゲール語)で、英語は第二公用語なのですが、アイルランド語を話す人は、たったの1%しかいないというのです。
また、ノルウェーは14世紀末から1814年までデンマークの支配下にあり、デンマーク語が書き言葉として使われていました。ところが、デンマークの支配から解放されると、ノルウェー人のための書き言葉が作られ、使われているのです。
著者は12歳でアメリカに渡ったものの、アメリカ社会になじめず、「日本現代文学全集」を読んで過ごしていたという。そんな彼女が、アメリカで日本近代文学を教え、日本語で小説を書くようになったのは必然なのでしょう。
英語の台頭によって、フランス語は、気の毒なことに、日本語と同じところまで凋落してしまったのである(p71)
公文書が日本語で発布されたのは明治元年
日本の国語は明治維新後に作られた、と著者は説明します。そもそも日本の公文書は漢文で書かれており、公文書が「漢字カタカナ交じり文」という日本語で発布されたのは、明治元年の「五箇条の御誓文」が最初なのです。
明治の日本人は海外の知識を吸収するために、西洋の文献を翻訳していきました。日本の大学は、翻訳機関であり、日本語を作り上げていった場所なのです。その大学で翻訳していた人たちが、日本語で西洋の小説のようなものを書き始めます。それが日本近代文学なのです。
具体的には、東京帝国大学に在籍していた人だけでも、夏目漱石、森鴎外、坪内逍遥、正岡子規、尾崎紅葉、斎藤茂吉、志賀直哉、武者小路実篤、谷崎潤一郎、芥川龍之介、川端康成等がいます。こうした人たちの努力によって、「日本文学」は、世界の読書人のなかで、国民文学の一つとして認められているのです。
日本における<大学>とは、大きな翻訳機関=翻訳者養成所として、日本語を<国語>という、その言葉で<学問>ができる言葉に仕立て上げていった場所である(p211)
敗戦後、漢字の廃止を政府決定
衝撃だったのは、明治初期の文部省は、日本語をまったく漢字を使わない書き言葉にするのを理念として掲げていたということです。しかし実際には西洋語を翻訳するために、漢文訓読体を使った「漢字かな交じり文」が便利であり、漢字を廃止することはできなかったのです。
ところが敗戦後、漢字の廃止が政府決定され、実際に廃止されるまでのあいだ、当面使用される漢字として、1850字の「当用漢字表」が定められました。国語審議会においても、日本語をローマ字表記にする方法が議論されていたのです。最終的には、ローマ字表記派と慎重派の対立を経て、ローマ字表記派は少数派となり、現在の日本語に漢字が残っているのです。
中国でさえも、漢字を廃止しようという動きがあり、私が好きな魯迅も漢字を捨てなくては中国に未来はないと書いたことがある(p297)
優秀なバイリンガルを育てる
世界の人々に対し日本の立場や選択を説明するためにも、英語と日本語のバイリンガルの育成が必要です。そのためには、少数の選ばれた人をバイリンガルに育てるしか方法はないとし、著者はすべての国民に同じ英語教育を与えるのではなく、優秀な人に時間とお金をかけ、バイリンガルを育てることを主張しているのです。
具体的には、学校教育では、英語を読む能力の最初の きっかけを与え、大学以降は、英語は選択科目にするというものです。自分の国際交流の体験から、日本語の成立の歴史まで大学で言語学の授業を聞いているような感覚になりました。水村さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・外交がメディアにさらに左右され、いよいよ言葉の力で世界と渡り合わねばならなくなった・・日本に優れて英語ができる人材が充分に存在しなかったら、どうやって世界のなかでやっていけるのか(p271)
・学者として、日本語で書いたところで、当時の西洋の学者の誰が日本人の書いた学問=洋学の書を読むであろうか(p213)
・専門家しか読めなくなることによって、漢文という言葉は日本で死んだのである(p224)
【私の評価】★★★★★(90点)
目次
1章 アイオワの青い空の下で"自分たちの言葉"で書く人々
2章 パリでの話
3章 地球のあちこちで"外の言葉"で書いていた人々
4章 日本語という"国語"の誕生
5章 日本近代文学の奇跡
6章 インターネット時代の英語と"国語"
7章 英語教育と日本語教育
著者経歴
水村 美苗(みずむら みなえ)・・・東京に生まれる。12歳の時、父親の仕事の都合で家族と共にニューヨーク近郊に移り住む。アメリカになじめず、ハイスクール時代を通じて、昭和二年発行の改造社版の「日本現代文学全集」を読んで過ごす。ハイスクールを卒業したあとは、ボストンで美術を学ぶ。次にパリに短期滞在した後、最終的にはアメリカのイェール大学と大学院で仏文学を学ぶ。博士課程を修了したあと、日本に一度戻るが、また渡米して大学で日本近代文学を教える。東京在住。
鉄塔文庫関係書籍
「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」フィリップ・K・ディック
「O・ヘンリー ニューヨーク小説集 街の夢」オー・ヘンリー
「猫を抱いて象と泳ぐ」小川 洋子
「ジュリアン・バトラーの真実の生涯」川本直
「日本語が亡びるとき: 英語の世紀の中で」水村 美苗
「夜の樹」トルーマン・カポーティ
「性と芸術」会田 誠
「ずっとそこにいるつもり?」古矢永 塔子
「欲望という名の電車」テネシー・ウィリアムズ
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!
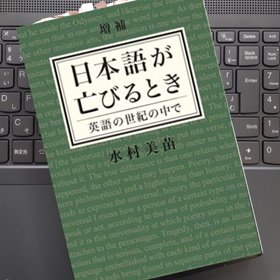
































コメントする