【書評】「今こそ問う 水力発電の価値 ―その恵みを未来に生かすために」国土文化研究所
2020/07/29公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(85点)
要約と感想レビュー
安定した水力発電が有望
日本では再生可能エネルギー買取制度(FIT)により、簡単な手続きで導入できる太陽光が大量導入され続けています。風力も増えてきました。
再生可能エネルギー買取制度(FIT)の買取価格は下がってきていますが、プロジェクトごとに一度決まったFIT買取価格は下がりません。つまり、2012年に認定された太陽光には40円/kWhで20年間もの間、高い買取価格で支払い続ける必要があるのです。(参考:一般家庭料金は25円/kWh程度)
この本では再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)の中で太陽光、風力は不安定電源でそれをカバーする発電設備が常に必要となり、問題が大きいとしています。
そして、他の比較的安定的な電源である水力、地熱、バイオマスを推進すべきであるとしています。その中でも特に「水力発電」が有望だという。海外では水力発電の比率の高い国も多く、ブラジルでは一次エネルギー消費量に占める水力発電の割合は28%、カナダ26%、日本はたったの4%なのです。
太陽光・風力発電などは、気象条件に左右される不安定な電源である。一方で、水力発電は、ほかの発電方法に比べ、安定した電源で、かつ、長期的視点では安価である(p5)
なぜ水力発電が有望なのか
なぜ水力発電が有望なのでしょうか。それは季節ごとに水量は変わるものの水力発電は比較的安定電源であり、発停止も容易にできる調整電源であることです。
また、一度水力発電所を作ってしまえば、燃料費は不要であり、適切な手入れ、補修をしていけば100年以上使えるのです。
ところが、発電コストを計算すると水力発電は高く見えます。これは発電コストの建設費の部分を税金を計算するための法定耐用年数で減価償却しているからだという。(発電方式別の法定耐用年数;水力(ダム:80年、貯水池・水路:57年、発電設備:22年)、太陽光17年、風力17年、火力15年)
つまり、100年使える水路を57年で償却している。50年使える機械装置を22年で償却している。実際の耐用年数で減価償却を計算しないと投資判断を間違ってしまうことはだれでも知っているはずなのにです。
水力発電所は、減価償却資産としての経済性評価を行う際の法定耐用年数には30~50年が用いられている。しかし、水力発電所は・・・適切な維持管理・機器更新を行なえば100年を超えても運転を継続することができる(p26)
私の感覚に近い一冊でした。この本に書いてあることが本当なのか、どこが間違っているのか、研究していきたいと思います。
水力発電は新規地点が少ないとか、水利権や地元の理解が必要など課題もあるようです。そうした点も含めて水力発電を理解できるよう調べていきたいものです。国土文化研究所さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・スイスやオーストリアでは、山間地に点在する小水力発電所が100年以上もの歴史を経て今なお健在であり、良好に維持管理されている・・・地域に根差した日本の水力発電がなぜ発展しなかったのか(p2)
・近年、洪水予測精度が向上してきているため、貯水位を低下させることなく所期の貯水位を維持することで、発電電力量の増加を期待することができる(p8)
・ダム高、流域面積が比較的小さなダムでは、水力発電設備が未設置のケースが多い(p15)
・国・地方自治体が(ダム)管理者である場合には、洪水被害軽減のための治水などを目的とし、水力発電を目的としていないケースも多い。実際に、国土交通省所管の管理ダム545基を対象に発電参画状況をみてみると、545基中282基(約52%)のダムでは、発電が行われておらず、これらのダムは、相対的にダム高が低い(=落差が小さい)、流域面積が小さい(=流量が小さい)という特徴を有している(p90)
・ダムの機能アップを図る「嵩上げ(かさあげ)」は、再開発の目的に応じて、洪水調節容量、利水容量の書く容量を増大できる・・・新桂沢ダムでは、既設の桂沢ダム提体のダム軸を変えずに1.2倍に嵩上げすることにより、ダムの貯水容量を約1.6倍に増加(p103)
・水力発電設備では、取水時に濁度が一定以上に上昇すると、水車の摩耗などが懸念されることから、発電を停止する等、積極的な発電取水を行なわないのが一般的である・・・水車の摩耗に対して、ハードコーティング・・・等)が研究されている(p123)
▼引用は、この本からです
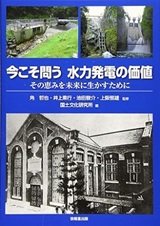
角 哲也, 井上 素行, 池田 駿介, 上阪 恒雄, 国土文化研究所、技報堂出版
【私の評価】★★★★☆(85点)
目次
1章 水力発電の役割
1節 水力発電の歴史的背景
2節 近年の発電事情
3節 水力発電の恵み
2章 水力発電の新たなかたち
1節 再生可能エネルギーの安定化への貢献
2節 リパワリングされる水力発電
3節 環境と共生する水力発電
4節 洪水を防ぐ水力発電ダム
5節 あらためて注目を浴びる小規模な水力発電
3章 水力発電の未来に向けて
1節 既存ダムを賢く使って発電力増強
2節 ダム嵩上げによる発電力増強
3節 ダムの総合活用による再生
4節 気候変動への適応
5節 水力発電のパラダイムシフト
この記事が参考になったと思った方は、
クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓ ![]()
人気ブログランキングへ
| メルマガ[1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』] 3万人が読んでいる定番書評メルマガです。 >>バックナンバー |
| |
この記事が気に入ったらいいね!

































コメントする