【書評】「本当の依存症の話をしよう -ラットパークと薬物戦争」スチュアート・マクミラン、松本俊彦、小原圭司
2025/04/18公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(89点)
要約と感想レビュー
ラットパークとは
過去にギャンブル依存症だった人から、お勧めいただいた一冊です。この本には依存症を理解するために「ラットパーク」と「薬物戦争」のマンガが掲載されています。
まず、「ラットパーク」とは、ネズミを使った依存症の実験のために作られた「遊具や食料が配置された広場」です。数十匹のネズミグループは、このラットパーク(楽園)で自由に遊び、食べて生活します。一方、別のネズミグループは、狭いゲージ(箱)の中に 1 匹ずつ隔離されています。
それぞれのグループにモルヒネ入りの水を飲ませると、ゲージのネズミはモルヒネ水を飲む量が増えていったのに、ラットパークのネズミはモルヒネ水を避け続けたというのです。
さらに、ゲージの中でモルヒネ水だけを飲んでいた依存症ネズミをラットパークへ移したら、そのネズミは広場で遊び、普通の水を飲むようになったという。
このラットパーク実験が示しているのは、薬物依存症とは、薬物の依存性によるものが原因というよりも、集団から孤立していたことが原因であることを示唆しているのです。
ラットパークの個体たちは好き放題にモルヒネが使える状態にもかかわらず、薬物を避け続けていた(p20)
薬物戦争とは
次に「薬物戦争」とは、1971年にニクソン大統領が薬物はアメリカの公衆の敵であると宣言し、薬物を禁止し、薬物を使用した人を犯罪者としたことです。
このマンガでは、ノーベル賞受賞者フリードマン氏の「薬物戦争」への反論が説明されています。フリードマンは、1920年代の禁酒法の失敗を例に示し、薬物を禁止することで同じ失敗を繰り返すだろうと予言しているのです。
つまり、薬物を禁止することによって薬物が「禁断の果実」となり人々を誘惑し、需要はなくならないこと。
そして、犯罪組織が薬物を生産し、薬物が欲しい民衆は、高い金額で犯罪組織から購入することになること。
さらに薬物依存者は犯罪者扱いされているので、助けを求めることができず、破綻するまで一人苦しむことになること。
犯罪組織は大金を手に入れ、金の力で警察や政府関係者に仲間を増やし、勢力争いのための犯罪が増えることになることが予想できるわけです。そして現在、薬物を禁止しても薬物の流通がなくなることはなかったのです。
1920年代に存在した禁酒法・・人々はカポネのような犯罪者が営む闇市場へと足を運ぶようになった(p45)
薬物犯罪防止の勧告
2001年、ポルトガル政府は、薬物の少量保持や使用を許容することを決定しました。その結果、2011年の段階で、薬物の過剰摂取による死亡、HIV感染が大幅減少したのです。10代の若者における薬物経験者の割合も減少したという。
こうした経験をもとに、欧米では2011年、薬物政策国際委員会が、各国政府に、薬物依存症者に対しては刑罰ではなく医療と福祉的支援を提供するよう提言しています。
また、2013年に世界保健機構(WHO)はHIV予防・治療ガイドラインのなかで、各国に規制薬物使用を非犯罪化し、薬物依存症者に適切な治療を提供するよう各国に勧告しているのです。
この本で伝えたいことは、これまでの経験から国際的には法律で薬物を禁止したとしても薬物の需要を減らすことは不可能ということを誰もが知っているということです。
「辱めと排除」による薬物犯罪の防止は、薬物に悩む人をますます孤立させる施策として、いまや国際的には時代遅れ(p77)
日本の薬物犯罪防止の現状
日本では2015年に危険ドラッグが「指定薬物」に指定され,販売が規制されました。その結果は、予想どおりネットでは,販売が続いており、危険ドラッグ依存者は病院に行かなくなり、地下に潜ったのです。
著者の小原圭司氏は、「薬物依存症に対して、なぜ効果のない対策が延々と続けられているのだろうか?」と問いかけています。
「生きづらさ」を抱えて孤立し、依存症になった人は犯罪者となり、さらに孤立させるのが日本の現在の法律なのです。一度、薬物をやってしまえば、それを正直に告白すると逮捕される危険があり、薬物依存症からの回復は容易ではないのです。
大麻合法化が話題になったことがありますが、もう少し調査を進めます。マクミランさん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・アルコール(エチルアルコール)という中枢神経抑制薬は立派な依存症薬物です(p73)
・誰もがみんな死ぬまで飲酒しつづけるでしょうか・・ネズミが死ぬまで薬物を使い続けたのは、薬物自体が持つ毒性・依存症によるものではなく、むしろ檻の中という、孤独で、窮屈かつ不自由な環境のせいではないか(p70)
・「やってしまった」「やめられない」・・正直な気持ちを口にすると、曲解され、攻撃の的にされてしまう社会。そこでは、薬物依存症からの回復は容易ではありません(p84)
・「ギャンブルにつながる引き金を徹底的に避けよう」「どうしても避けきれず、欲求がわいたときは、対処行動をしよう」(p99)
▼引用は、この本からです
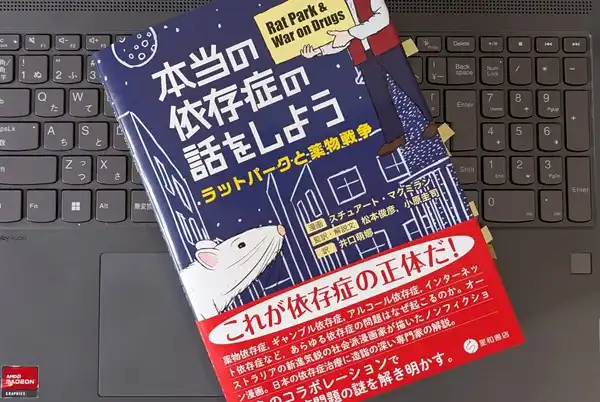
Amazon.co.jpで詳細を見る
スチュアート・マクミラン、松本俊彦、小原圭司(著)、星和書店
【私の評価】★★★★☆(89点)
目次
漫画 Rat Park(ラットパーク;ネズミの楽園)(スチュアート・マクミラン)
漫画 War on Drugs(薬物戦争)(スチュアート・マクミラン)
解説1 薬物依存症は孤立の病―安心して「やめられない」と言える社会を目指して(松本俊彦)
解説2 ギャンブル依存症は回復できる―依存症神話の打破を目指して(小原圭司)
著者経歴
スチュアート・マクミラン(Stuart McMillen)・・・1985年生まれ。オーストラリアのキャンベラに在住する漫画家。クラウドファンディングによって世界中の支援者から資金調達しつつ,科学,生態学,心理学,経済学といった領域にまたがる様々な社会問題をとりあげて,ノンフィクション漫画を執筆し,インターネット上で発表する活動を続けている。
松本 俊彦(まつもと としひこ)・・・国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 部長/薬物依存症センター センター長。1993年佐賀医科大学医学部卒業後,神奈川県立精神医療センター,横浜市立大学医学部附属病院精神科などを経て,2015年より現職。
小原 圭司(こばら けいじ)・・・島根県立心と体の相談センター(精神保健福祉センター)所長。精神保健指定医,精神科専門医。1993年東京大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院,虎の門病院,松沢病院,関東医療少年院などを経て,2012年より現職。2008年より日本精神神経学会の学会英文誌であるPsychiatry and Clinical NeurosciencesのManaging Editorも務めている。
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
この記事が気に入ったらいいね!
































コメントする