【書評】「地球温暖化は本当か? 宇宙から眺めたちょっと先の地球予測」矢沢潔
2015/08/04公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(80点)
要約と感想レビュー
地球温暖化を防止するために日本人は、京都議定書を批准して何兆円ものお金を支払い、今も脱炭素化にお金を出そうとしています。しかし、本当に二酸化炭素が温暖化の原因なのか、証明できていないとする科学者が、昔からたくさんいるのです。
こうした科学的に当たり前のことが当たり前に議論されない日本という国だから、太平洋戦争でアメリカと戦うことになったのかもしれません。アメリカの実力と現実を知って判断すれば、そうした判断にはならないだろうからです。
まだまだ騙せる日本人という表現は、今でも生きているのでしょう。今後の地球温暖化の議論が、どのようになっていくのか見ていきたいと思います。
矢沢さん、良い本をありがとうございました。
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この本で私が共感した名言
・東西に分断されていたドイツはようやく1990年に再統合を果たした・・・翌1991年から温室効果ガス排出量は急速に減少・・・イギリスもまた議定書とは無関係に、それ以前から進んでいたエネルギー政策の転換によって1990年代には温室効果ガス排出量が減ることがわかっていた・・・もともと政治的な建前によって作られた議定書にどこの国が真剣に向き合うことができようか(p46)
・リンゼン教授は次のように答えている。「地球の気候変動は複雑であり、これまで劇的な変化をたえず繰り返してきた。過去70万年のデータは約1万年ごとに氷期がやってきたことを示しており、その間の温暖期にはアメリカ北部のピッツバーグにさえワニが生息していた。こうした気候変動はごくふつうのことだが、コンピューター・モデルはこうした長期的変動を説明できないだけでなく短期的変動も説明できない。水蒸気や雲を取り込れることができないばかりか、狭い地域の気象予測や極地の気温変化も予測できない(p150)
・地球温暖化の議論では、この0.035%の二酸化炭素が毎年1%、つまり大気全体の0.00035%=100万分の35ずつ増加しているという理由で、いまのような歴史的にもまれな人類的パニックが引き起こされている・・・実際には、大気の1~4%という大きな割合を占めている水蒸気のほうが温室効果ははるかに大きい(p171)
【私の評価】★★★★☆(80点)
目次
第1章 地球温暖化の警告から京都議定書まで―それは無名科学者の一篇の論文から始まった
第2章 グリーンランドと南極の氷は溶けているか―溶けているのに厚くなっている南極の氷?
第3章 地球温暖化を主張する科学者のツール―シミュレーション学者は温暖化グラフをこうやって作る
第4章 シュクロー・マナベ、アキオ・アラカワ、地球シミュレータ―470億円の地球シミュレータの社会的価値
第5章 シミュレーションで温暖化を予測できるか―世界最速コンピューターの予測はゲタ投げの天気予報よりはずれる?
第6章 異議を唱える科学者たち―気温の上昇と二酸化炭素の増加、どちらが先か
第7章 地球の気候変動を宇宙から眺める―気温の最大の支配者は太陽の放射エネルギー
第8章 地球温暖化をコントロールする―自らの視点を変えるとき
著者経歴
矢沢潔(やざわ きよし)・・・科学雑誌コズモ創刊編集長を経て1982年より科学情報グループ「矢沢サイエンスオフィス((株)矢沢事務所)」主宰。内外の科学者・研究者、科学ジャーナリスト、編集者、翻訳者などのネットワークを構築し四半世紀にわたり自然科学、生物学、エネルギー技術(核分裂と核融合)、医学、科学哲学、未来文明論、テラフォーミング等に関する情報・執筆・啓蒙活動を続ける。
この記事が参考になったと思った方は、
クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓ ![]()
人気ブログランキングへ
| メルマガ[1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』] 3万人が読んでいる定番書評メルマガです。 >>バックナンバー |
| |
この記事が気に入ったらいいね!
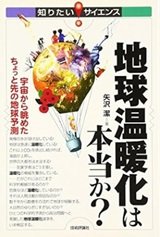

































コメントする