「ビジネスエリートがやっている最高の食習慣」有馬 佳代
2022/11/11公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★★☆(82点)
要約と感想レビュー
アメリカの大学院で栄養学・遺伝学を学んだ著者から、栄養学の視点から「朝食は、食べなくて良い」という根拠を教えてもらいましょう。もちろん「朝食は、食べなくて良い」のは、成長まっさかりの子どもたちは対象外で、体脂肪率が高く机に座ってばかりの大人が対象です。
太古の人間は生きていくために、食べ物を手に入れることに苦労してきました。食べ物がないときでも、血糖値が下がらないように脂肪を溜め込むようになっています。これが肥満です。
ところが、現代社会は常に食べ物が手に入り、血糖値が下がらないという想定外の食環境になってしまいました。人間は、血糖値を下げる調整機能をあまり持っていないのです。血糖値の高い状況が続くと、血糖値を下げるインスリンの効果が低下し、糖尿病になってしまうのです。
・「血糖値が下がらない生活環境」が・・・多くの慢性病を生み出すインスリン抵抗性を発現させます(p105)
そこで、血糖値を下げるために私たちが何ができるかといいえば、運動と絶食です。この本で提案しているのが、断続的断食です。具体的には、食事時間を8~10時間に制限したり、1日ごとに断食したり、週に2日間カロリーを4分の1に減らすなどの方法があります。
朝食を食べなければ、お昼と夕食だけとなり、自然と食事時間を8~10時間に制限することができるというわけです。食べない時間を14~16時間に制限すると、消化器官を毎日休ませることができるというメリットもあるという。
・午前中は「食べずに動く」という短期のストレスは人間本来が持つ「体脂肪をエネルギーに変換する」能力を鍛えます(p137)
食べ過ぎへの対策は、食べないことと運動することというのは、当然のことだと感じました。「朝食は1日で最も重要な食事」という言葉が、1994年にアメリカの食品会社のシリアルの広告だったというのも、さもありなんといったところです。日本では60代で半数の人が血圧を下げる薬を1種類以上服用しているという。著者は、朝食を抜くことで、血圧を下げる薬を飲まなくてもよくなる人が増えるのではないかと予想しています。
食べすぎないために、断続的断食をするというのは、古代の食べ物が少ない時代に戻るということであり、人間本来の力を引き出してくれるのでしょう。血糖病や肥満の人が多い現代社会だからこそこの本に書いてあることが常識になってほしいと感じました。本の評価としては★4とします。有馬さん、良い本をありがとうございました。
この本で私が共感した名言
・食べないで活動すると脳と体が活性化する(p9)
・太古の時代では、誰でも食べずに活動できる力を持っていました・・・食べ物がある時には食べ、ない時には歩いて食べられるものを探す(p44)
・鎌倉時代後期の後醍醐天皇の朝食は正午頃で、夕食は夕方4時頃という記述が残っている(p62)
・朝食スキップ・・・小腸の掃除ができる・・私たちの小腸は、1日に4回ほど、一方通行で内容物を肛門に向かって送り出す(p80)
【私の評価】★★★★☆(82点)
目次
1章 朝食スキップは理にかなった習慣である
2章 朝食スキップで良いサイクルに!
3章 生活にちょっとした行動を付け足して、1日2食を実践!
4章 1日2食生活をサポートするレシピ集
著者経歴
有馬 佳代(ありま かよ)・・・遺伝学・栄養学博士、管理栄養士 徳島大学医学部栄養学科卒業。米国アリゾナ大学大学院博士課程修了。 カリフォルニア大学アーバイン校およびサンディエゴ校での研究活動を経て、ヘルスコンサルティング会社Kayo Dietをカリフォルニア州サンディエゴ市で設立。アメリカでは栄養指導、料理指導、講演・ワークショップ活動を、日本では栄養環境コーディネーター認定講座を考案、 代表講師を務めながらオンラインでの栄養指導も行っている。
この記事が参考になったと思った方は、クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓
![]()
![]()
| 無料メルマガ「1分間書評!『一日一冊:人生の智恵』」(独自配信) 3万人が読んでいる定番書評メルマガ(独自配信)です。「空メール購読」ボタンから空メールを送信してください。「空メール」がうまくいかない人は、「こちら」から登録してください。 |
この記事が気に入ったらいいね!
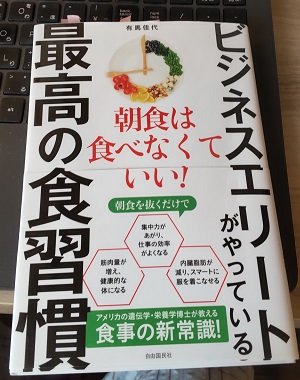

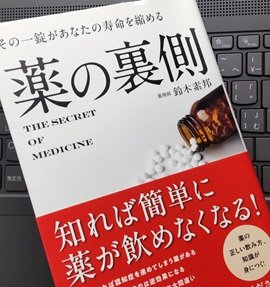
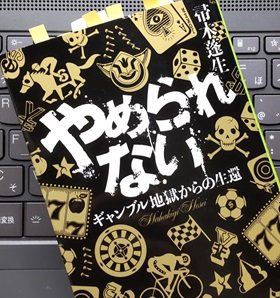
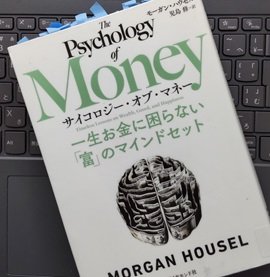
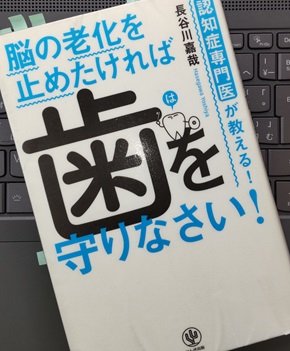
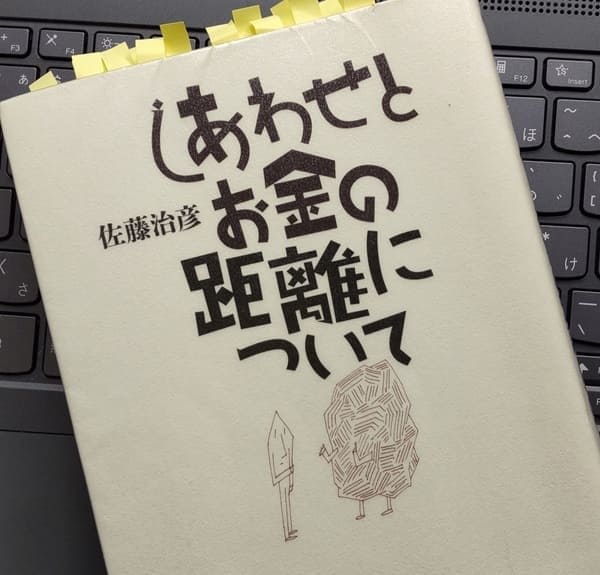
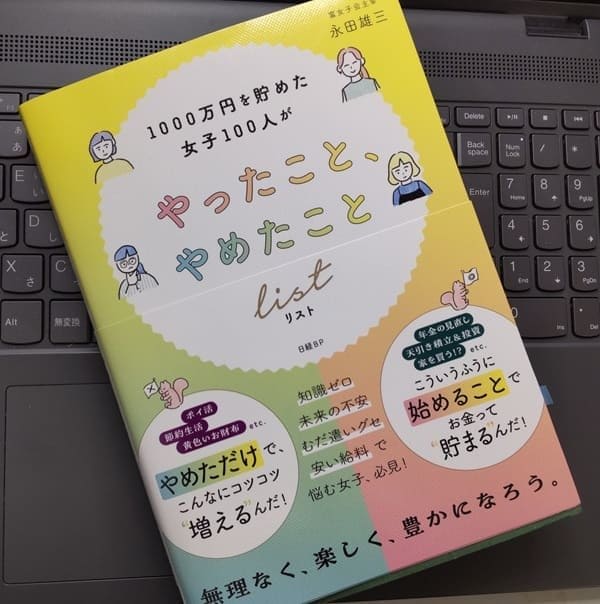
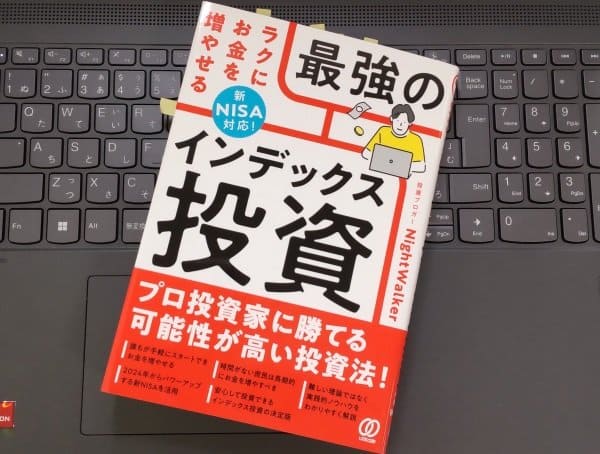
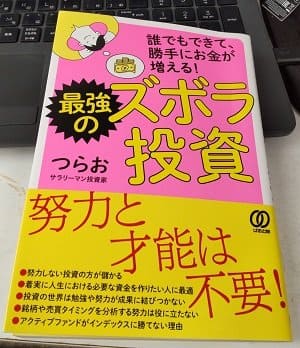








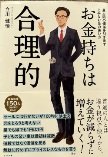














コメントする