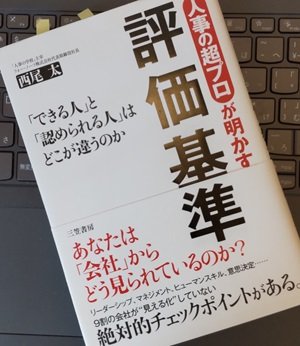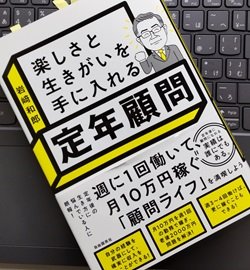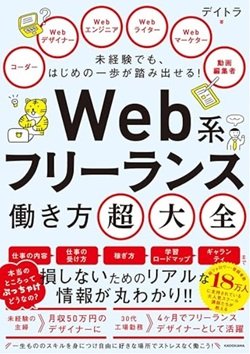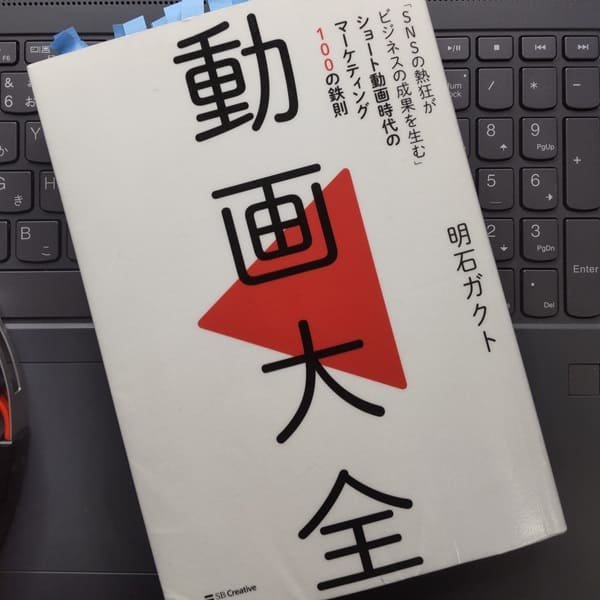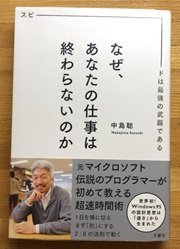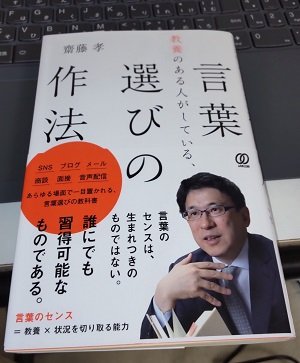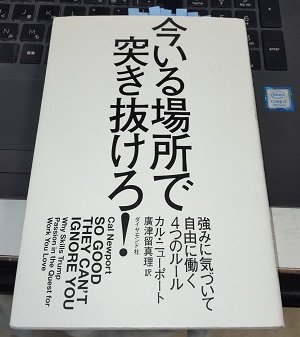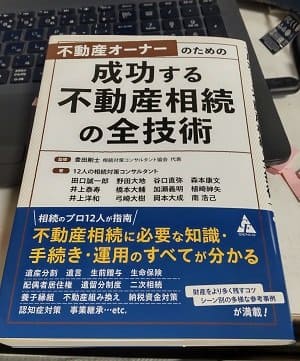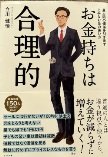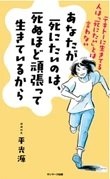「小飼弾の 「仕組み」進化論 」小飼 弾
2017/08/31公開 更新
Tweet
【私の評価】★★★☆☆(78点)
要約と感想レビュー
■多くの本を読んできた小飼さんが、
その知識をどう仕事に活かしてきたのか
教えてくれる一冊です。
情報系の仕事には、
プログラミングと
データセンターがあります。
まず、プログラミングでは、
全員が同じ目標を目指し、
協調して作業を行う
仕組みが必要です。
情報共有ため、メーリングリストを
活用していることが、
印象的でした。
・日報用メーリングリスト・・各人の進捗状況を全員が把握できますから、作業が遅れている人間を別の人間が手伝いやすくなりますし、行き詰まっている人がいたら声をかけることもできます(p120)
■また、データセンターは、
24時間安定運転が当然ですから
発電所のようなものです。
一旦、データセンターで
トラブルが発生したら
全員が即応する必要があります。
そのためパトライトを設置して、
トラブル発生を周知したり、
多能工を育てているとのこと。
・トラブル時の対応力を高めるために、10名いたデータセンターの担当者は、自分の専門以外の業務も一通りこなせるようにしました(p124)
■読んだ本の内容を引用して、
仕事への活用方法を教えてくれるのが
分かりやすい。
こうして活用できれば、
読書も無駄にはなりませんね。
小飼さん
良い本をありがとうございました。
この本で私が共感した名言
・個々のメンバーが最終的な完成イメージを共有していることが欠かせません・・ゴールを見せないことは、各人の知能を無駄にすること(p112)
・プログラミングの世界では、すでにある機能を自分で改めて作ってしまうことを「車輪の再開発」と言って戒めています(p77)
・自分がミスをしたとき、後の行程にどういう迷惑がかかるのかを見せることは自分の役割を意識させるうえで、どんな言葉よりも効果があります・・自分のミスで、同僚にどれくらいの徹夜仕事をさせることになるかがわかっていれば、どう借りを返すべきかも見えてくるはずです(p115)
・業務上の質問を投稿できるメーリングリストも用意し、わかる人間が積極的に回答する体制を整えました(p122)
・優秀なアリはエサを効率よく集めるのですが、新しいエサは発見しにくい。一方、下手なアリはうろうろすることで新しいエサを発見できるチャンスが高まるという推測がなされています(p210)
・十分に発達した仕事は遊びと区別できない(p211)
この記事が参考になったと思った方は、
クリックをお願いいたします。
↓ ↓ ↓ ![]()
![]()
▼引用は下記の書籍からです。
【私の評価】★★★☆☆(78点)
目次
Part0 仕組み作りが仕事になる
Part1 仕組みの仕組み 仕組みを作る前に知っておきたいこと
Part2 仕組みを作り直す 目の前の仕事を20%の力でこなす仕組み
Part3 仕組みを使う 仕組みのコストとテストを考える
Part4 仕組みを合わせる チームで仕組み合うために
Part5 仕組みと生物 「新しい仕組み」を作るヒント
Part6 仕組みの未来
著者経歴
小飼 弾(こがい だん)・・・投資家、プログラマ、ブロガー、書評家。ブログ『404 Blog Not Found』は書評を中心に、月間100万ページビューを誇る。オン・ザ・エッジ(現ライブドア)上場時の取締役最高技術責任者(CTO)を務めた。